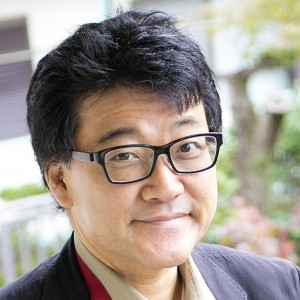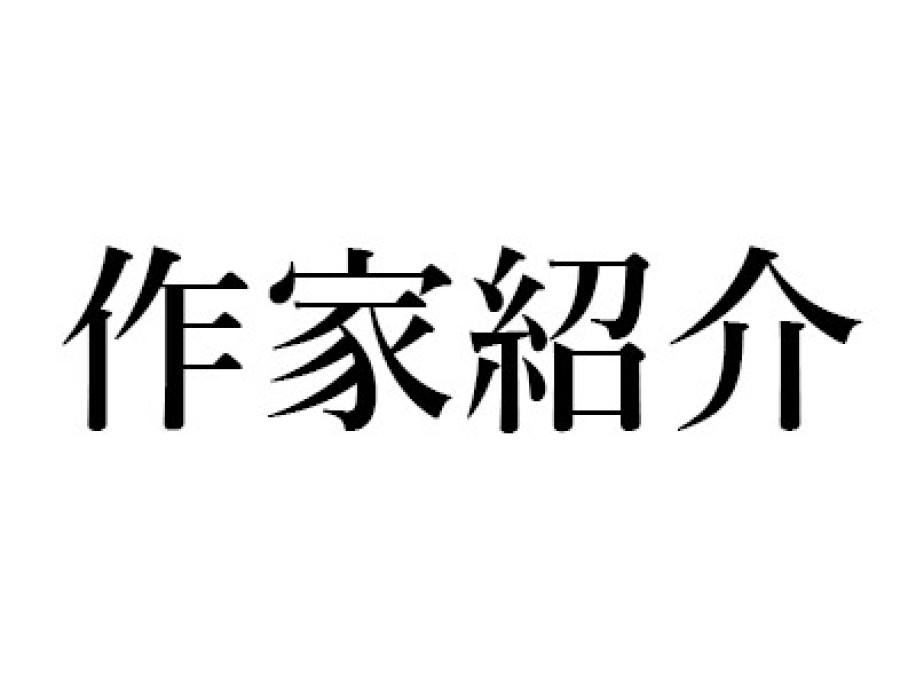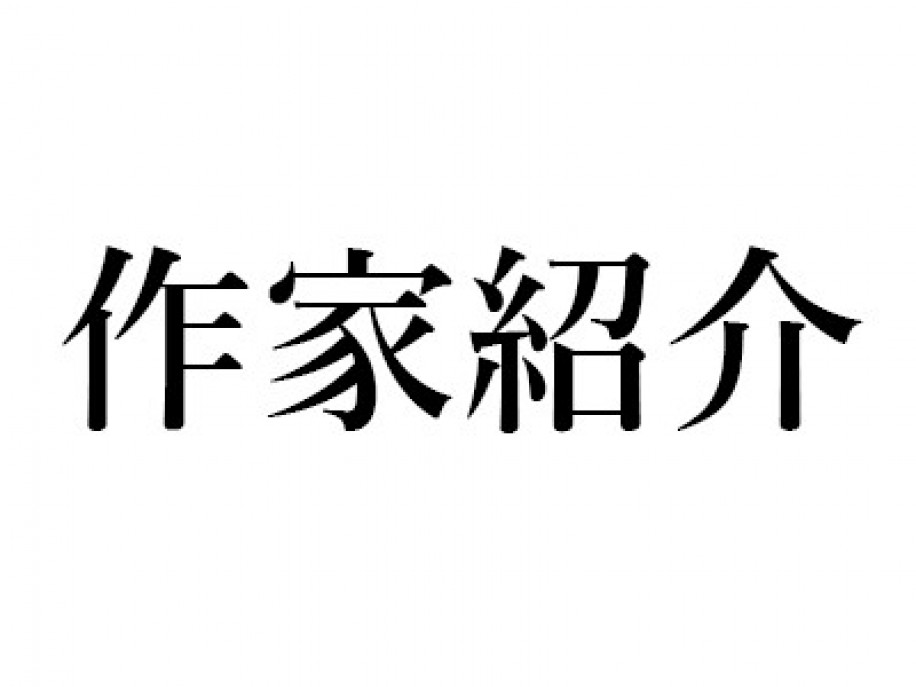書評
『殺人協奏曲』(新潮社)
フワン=ラモン・サラゴサ(Juan-ramon Zaragoza 1938- )
スペインの医学者・作家。生地バレンシアで医学を勉強し、放射線学を専攻する。1971年からセビリア医科大学放射線科教授を務める。新聞や医学雑誌にオスカル・メンデスのペンネームで寄稿し、医学歴史書や一般向け医学啓蒙書もある。『殺人協奏曲』(1981)は、独裁者フランコの死の直後から書きはじめられ三年がかりで完成した。この作品によって、スペインでもっとも権威のある文学賞ナダル賞を受賞。introduction
古い育ちのせいか、どうも尾テイ骨のあたりに教養主義というやつが残っているらしく、ときどき「もっと真面目な文学も読んでおかないとイケないかな」と不安にかられる。もちろん、頭では「文学に真面目も不真面目もあるもんか」と思っている。しかし、「人生について知るべきことのすべてが書かれている」という『カラマーゾフの兄弟』すら読んでいないのは恥ずかしい気がする。もしかすると、この文豪ドストエフスキーの名作を読むのをサボったせいで、いままでまちがった人生をすごしてしまったかもしれない。しかし、カラマーゾフ兄弟が何人なのか知らないけど、見るからに重厚なあの作品を前にするとなかなか食指が動かない。というわけで、ぼくはとりあえず、カート・ヴォネガットやフワン=ラモン・サラゴサを読むところからはじめようと思う。▼ ▼ ▼
カート・ヴォネガットは、第二次大戦中の凄惨なできごとを経て、「だけどもう、『カラマーゾフの兄弟』だけじゃたりないんだ」という心境に達した。あまりにも有名になったこのセリフは、ヴォネガットの代表作のひとつ『スローターハウス5』のなかで、SF狂の皮肉屋エリオット・ローズウォーターによって発せられる。ローズウォーターは大戦に従軍して、ドイツ兵と見誤って十四歳の射殺していた。それが彼の心に消せない傷となる。また、この小説の主人公ビリー・ピルグリムは、ドイツ軍の捕虜となり、ヨーロッパ史上最大の虐殺となったドレスデン無差別爆撃を体験した。このビリーが作者ヴォネガットの分身である。
ヴォネガットにとってドレスデン経験がそうだったように、スペインの作家フワン=ラモン・サラゴサは、フランコ独裁下の単調で重苦しい日々を契機として、十九世紀文学が考えていた人生観とはちがった境地にたどりついたのだろう。そして、ヴォネガットが『スロータハウス5』で試みたように、サラゴサの『殺人協奏曲』も、人生の苦悩や挫折を正面から扱うのではなく、SF的な仕かけを用いて、ちょっと離れた視点から“人生というもの”を描いてみせる。
その仕かけとはこうだ。第一部が紀元七八年のウェスパシアヌス大帝統治下のローマ帝国、第二部が二〇一六年の大統領選挙をひかえたワシントン、第三部が一七七六年フランス革命直前のパリと三部構成で、それぞれの時代で技術者マルコスと革命家アドルフが出会い、おなじ運命を三たび繰りかえす。その顛末の観察者となるのが、霊界法廷の面々である。このあたりの諧謔味も含めて、ヴォネガットに似ている。また、ローマ帝国に蒸気駆動の自動車が登場したり、未来の選挙戦でテレパシーによる票の獲得工作がおこなわれたりと、こまごまとしたアイデアや道具立ての面でも、SFじたてになっている。
マルコスは生まれつきの善人で自分の仕事に没頭するあまり、現実の生活にうとく他人に利用されてしまう。無力だが正義感が強く、悪事がおこなわれていると知れば、勇気まんまん徒手空拳で立ちむかっていく。いわば『ドン・キホーテ』の系譜につらなる存在である。じっさい、この近代スペイン文学の偉大な嚆矢は、作者サラゴサの愛読するところだという。
一方、アドルフは実行力と不屈の精神をそなえ、自分の信じる秩序で人民を支配しようという野望に燃えている。その名前が示しているように、また第一部ではゲルマニア移民として登場することからも、明らかにヒトラーをモデルにしているが、同時に独裁者フランコのイメージもだぶる。もっとも作者は、アドルフをたんに権力欲に憑かれた狂人として描いているのでなく、彼の人格の魅力的な側面についても書きとめている。アドルフもつまるところ、運命の歯車に弄ばれる存在にすぎないのだ。
第一部ではローマ帝国繁栄のための事業の推進力として蒸気機関が企てられ、マルコスが技術担当としてそれに取りくむ。アドルフはプロジェクトの指揮者として計画に参加するが、裏では皇帝の下の息子ドミチアヌスと手を組み、政権を転覆させるべく陰謀を巡らせている。蒸気機関を武器として使おうという算段だったが、計画段階で発覚してしまう。アドルフは追われる身となり、マルコスも自分が利用されていることに気づいたときはすでに遅く、アドルフと行動をともにするはめになる。ローマの市街を蒸気自動車に乗って驀進するふたり。逃げきれるかと思ったとき、一頭の牝牛が行く手をふさぎ、自動車は並木に激突してしまう。
第二部では、マルコスが不審な電気機器メーカーを探るために技術部門に潜入する。そこで一種の洗脳技術・メディアコントロールが開発されていた。それを後押ししているのが、ナショナルデモクラシー党から出馬している大統領候補のアドルフである。自分の研究も知らずしらずのうちにアドルフに荷担していたことを悔いたマルコスは、選挙に仕組まれた不正行為を阻止しようと試みる。アドルフは自らが仕組んだ洗脳テレパシーを逆に受け廃人になるが、マルコスもテレパシーの影響で自殺に追いこまれてしまう。
そして第三部は、アドルフが革命家マラーと手を組み、マルコスは発明されたばかりの起電盤のエンジニアとして登場する。詩人ヴォルテール、物理学者にしてフランス駐在大使ベンジャミン・フランクリン、錬金術師カリオストロ伯爵など、絢爛たる脇役も登場し、物語もひとひねりふたひねりが加わる。しかしけっきょく、マルコスとアドルフは前二回と同様、悲惨で滑稽な最後を遂げることになる。
けっきょく、人間は自分の運命の主役になることはできないのだ。人間性などおかまいなく技術や社会は動き、その大きな慣性のもとで、ひとびとは無益で滑稽なふるまいをつづけるばかりだ。しかし、無益で滑稽とはいえ、それはかけがえのない人生であり、すべてを笑いとばしておわりにできるはずもない。深刻ぶることができる域などとうに超えているから、とにかく笑うしかないけれど、苦い味は消えない。
エンターテインメントならば、この矛盾を口あたりのいい嘘でごまかしてくれるだろう。そういえば、ヴォネガットの登場人物ローズウォーターは、そうした効用を積極的に評価していた。彼は、自分が入院している精神科病棟の担当医に対し、「あんたたちはそろそろ、すてきな新しい嘘をたくさんこしらえなきゃいけないんじゃないか。でないと、みんな生きていくのがいやんなっちまうぜ」と進言している。
しかし、サラゴサは、生きることの矛盾をごまかすことなく、正面から抱えこむ。もちろん、文学というのはフィクションにすぎないが、一時しのぎの安心や慰めを与えるための嘘とはちがう。ドストエフスキーに代表される十九世紀の人間文学であっても、第二次大戦後の新しい世界観のもとで書かれ文学であっても、それはおなじだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする