書評
『レキシントンの幽霊』(文藝春秋)
文藝春秋のPR誌『本の話」で、村上春樹が日本の現代作家の短編作品評論を連載しているのだが、これが滅法勉強になる。プロの作家による批評というよりは作品解題になっているので、すべてが小説を書くテクニックの解き明かしにつながっていて具体的なことこのうえないのだ。さて、そういう文学の方法論において意識的な作家の最新作品集が出た。七編の短編小説が収められた『レキシントンの幽霊』だ。これまで村上氏の仕事において注目されているのは常に長編小説だったんだし、あるいは海外の優れた作家を紹介してくれる水先案内人としての翻訳家としての仕事もまた重要な位置を占めてきたのだと思う。一方、短編小説はというと長編の合間に書く手すさび、といっては失礼かもしれないけれど、まあとにかく地味な存在ではあったのだ。しかし、本書を通読してみてほしい。七作品が内包している深い世界観と現実との距離のおき方に、ちょっと驚いてしまうはずだから。
たとえば表題作。語り手はレキシントンに住む独身の建築家と知り合いになり、彼の屋敷の留守番を頼まれる。そしてその晩、居間でパーティを催しているような賑やかな声や物音を聴く。幽霊だと直感する語り手。やがて物語は、楽しそうに笑いざわめく幽霊たちとは対照的な、友人の孤独に言及していく。そのコントラストは、しかし鮮やかではない。「ついこの間経験したばかりのことなのに」、水彩画のように滲(にじ)みをまとってボンヤリしているのだ。「ひどく遠い場所で起こった出来事のように感じられ」、「その遠さの故に」「ちっとも奇妙なことに思えないのだ」という立場をとっているゆえの雰囲気としての滲み。「遠さ」という距離を用いることで、ヘタをすればいかにも作り物めいた“よくできた話”で終わってしまっていただろう作品に独特の雰囲気をまとわせ、余韻という深みを与えることに成功しているというわけなのだ。
そのほか、子供時代に高波にのまれた親友を見殺しにした罪悪感につきまとわれ、しかし最後には救いを見いだす男の話『七番目の男』や、ボクシングを通じて「深み」を知り、「深みを理解すること」で、沈黙という名のいじめの試練に打ち勝った男の話『沈黙』など、さらっと読めるのに心の中からいつまでも作品世界が去っていかないという余韻を残す秀作ぞろい。PR誌で見せてくれる作品解題の腕そのままに、自作でも素晴らしい成果を静かに上げているのが、さすがは村上春樹というべきか。これでもう少しモラリスト臭が消えてくれたら傑作と呼ぶのに躊躇しないんだけどなあ。
【この書評が収録されている書籍】
たとえば表題作。語り手はレキシントンに住む独身の建築家と知り合いになり、彼の屋敷の留守番を頼まれる。そしてその晩、居間でパーティを催しているような賑やかな声や物音を聴く。幽霊だと直感する語り手。やがて物語は、楽しそうに笑いざわめく幽霊たちとは対照的な、友人の孤独に言及していく。そのコントラストは、しかし鮮やかではない。「ついこの間経験したばかりのことなのに」、水彩画のように滲(にじ)みをまとってボンヤリしているのだ。「ひどく遠い場所で起こった出来事のように感じられ」、「その遠さの故に」「ちっとも奇妙なことに思えないのだ」という立場をとっているゆえの雰囲気としての滲み。「遠さ」という距離を用いることで、ヘタをすればいかにも作り物めいた“よくできた話”で終わってしまっていただろう作品に独特の雰囲気をまとわせ、余韻という深みを与えることに成功しているというわけなのだ。
そのほか、子供時代に高波にのまれた親友を見殺しにした罪悪感につきまとわれ、しかし最後には救いを見いだす男の話『七番目の男』や、ボクシングを通じて「深み」を知り、「深みを理解すること」で、沈黙という名のいじめの試練に打ち勝った男の話『沈黙』など、さらっと読めるのに心の中からいつまでも作品世界が去っていかないという余韻を残す秀作ぞろい。PR誌で見せてくれる作品解題の腕そのままに、自作でも素晴らしい成果を静かに上げているのが、さすがは村上春樹というべきか。これでもう少しモラリスト臭が消えてくれたら傑作と呼ぶのに躊躇しないんだけどなあ。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
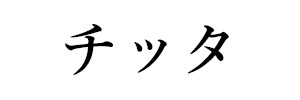
チッタ(終刊) 1997年3月
ALL REVIEWSをフォローする


































