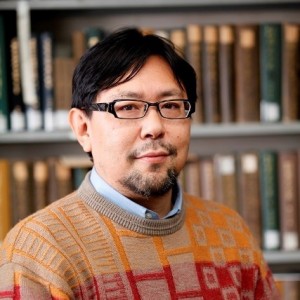書評
『敗れども負けず』(新潮社)
「普通の」人生への判官びいきを超えた共感
判官(ほうがん)びいきという言葉がある。左衛門少尉(高級警察官僚)を判官といい、同職に任じた源義経を九郎判官と呼んだ。成功者たる兄の源頼朝よりも、平家追討の大功をたてながら悲劇的な最期を遂げた義経を日本人は好んだ。転じて、弱い立場にいる者に対して同情する私たちの感性、それを判官びいきと呼ぶ。いや、この説明は十分ではあるまい。弱ければすべからく応援の対象になるか、というとそうではない。現代では時に誤用されるが、本来は、功績をたてた、傑出した力をもっている「にもかかわらず」相応な処遇を受けられない、理解されない。そういった悲運の人に心を寄せるのが判官びいきであった。
この意味からすると、本書が取り上げる人々は、判官びいきの対象にはなり得ない。上杉憲政(のりまさ)、板額御前(はんがくごぜん)、龍造寺隆信(りゅうぞうじたかのぶ)、足利春王丸・安王丸、貞暁(じょうぎょう)法印。九州に大勢力を築いた龍造寺隆信は微妙だが、他は「何も成し遂げていない」、時の奔流に対する弱者として歴史の表舞台から退場した人物であるから。
勝利・栄光を描く時代小説は数多い。だが本書の作者はそうしたものより、挫折であったり、敗北を見つめていく。それは功績や傑出を前提とする判官びいきの範疇(はんちゅう)にとどまらぬ、徹底したリアルの追求である。
現実を生きる私たちのほとんどは、ごく「普通の」人間である。富や名声には縁遠い。では、私たちが生きることに意味はないのか。いや、そんなことはない、と本書は力強く訴えてくる。どんな苦境にあっても、力及ばず敗れても、そこに「何か」があれば、人は負けることはない。
その「何か」はぜひ本書を読んで確かめていただきたい。「普通の」人生への、判官びいきを超えた共感。それが本書のテーマだと私は理解している。
ALL REVIEWSをフォローする