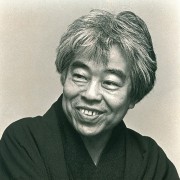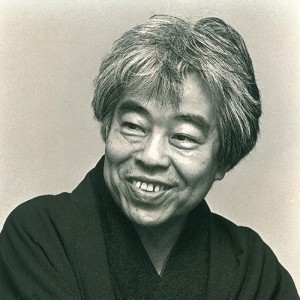書評
『剣のいのち』(文藝春秋)
ネオ剣豪小説に新たな展開
津本陽は剣技の描写にすぐれ、それを作中に生かすことで、ネオ剣豪小説とでもいうべき分野をひらいてきたが、これまでは実在の人物をモデルとしたものが多かったようだ。だが近作の「剣のいのち」では、幕末の激動期を背景に、紀州藩の脱藩者である一青年を創造し、この主人公が勤王とか佐幕とかのイデオロギーよりも、むしろ剣をささえとして時代の波をくぐり抜けてゆく姿を描いており、彼の作品のあらたな展開をみることができる。江戸の伊庭(いば)道場で学び、心形刀(しんぎょうとう)流の使い手となった若い紀州藩士・東使左馬之助は、藩内の因循な空気に飽きはて、脱藩して京へ上り、天下の志士と交わって、尊攘の機運に乗じたいと願った。紀州藩では井伊直弼が暗殺された事件の余波で権力者が交替し、その政変によって父の伊織も小身におとされ、一家の暮らしが苦しくなったこともあって、左馬之助は同志とともに、藩政の腐敗を弾劾する直訴状を幕府に差し出す企てに参加した。しかし二人が脱出した後に藩では三人を捕らえ、残った左馬之助と秋田弥助の身にも危険が迫った。そのため彼らは文久二年十一月十八日の深夜、和歌山城下を離れて風吹峠まで来たが、翌朝あらわれた討手は弥助を倒し、左馬之助を囲んだ。彼は父から譲られた家宝の銘刀、文珠重国をふるって五人を相手に戦い、すべて討ちはたして京へたどり着いた。
無法な浪人たちの横行する京の町で、左馬之助はその数人とぶつかって斬り合う騒ぎもおこるが、このとき祇園の芸妓、佳つ次にかくまわれたのがきっかけで、彼は彼女と結ばれ、後には夫婦となって愛しあう。
先に到着していた伊達宗興や横田次太夫と合流した左馬之助は、その後、江戸へ出、ふたたび京にもどるが、彼らが滞在した薩摩藩邸で中村半次郎と知りあうなど、その剣の腕をひろくみとめられる。こうして紀州藩政を乱す家老を失脚させ、藩論を尊攘派に導くといった動きにはじまり、混沌とした政情のただ中におかれた彼は、やむなく白刃を交えることも少なくない。しかもすぐれた剣技の持ち主であるだけに、尊攘、佐幕といった立場をこえて注目され、それが彼を思わぬ運命にまきこんでゆく。
紀州藩内の状況が好転した後も、左馬之助は帰藩せず、浪士として佳つ次とともに京で暮らすつもりになったが、中村半次郎は彼を薩藩の密偵にしようとした。宗興の義弟で時勢を見抜く眼のある親友の伊達陽之助は、坂本竜馬の話を聞き、勝海舟の海軍操練所で一緒に学ぼうと彼にすすめ、彼も気持ちが動いたものの、佳つ次と野遊びに出たおり襲われて逃れた彼らを、半次郎が助けた義理もあって、たのみを承諾せざるを得ない。そのため左馬之助は新選組に近づき、剣術教授方として壬生(みぶ)の屯所に出入りするようになる。
しかしやがてそこから脱け出し、神戸へ逃れて海軍塾へ入り、一時、長崎へもおもむいたが、神戸へもどった後、さらに竜馬に同行して京へ行き、塾生たちを激発の危険から防ごうとする竜馬を助けて行動する。最後に左馬之助が池田屋事件の渦中から逃れるところで作品は終わるが、こうした彼の変転は、新しい時代に生きようとしながらも、剣に左右され、修羅をかさねてきたものといえよう。
作者は左馬之助と佳つ次の愛に彼の人間味を象徴させながらも、するどい剣のさばきでつぎつぎに相手を倒す剣士としての一面を描きこむと同時に、この主人公を時代の諸事件や諸人物と関連づけて作品の興味をもりあげている。新選組をはじめ幕末期のさまざまな動きについて、くわしく書かれたものは多いが、その間を縫って主人公を自由に活躍させたところに、ロマンとしての工夫がみられるのではなかろうか。
ALL REVIEWSをフォローする