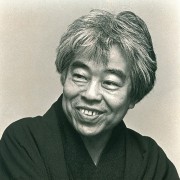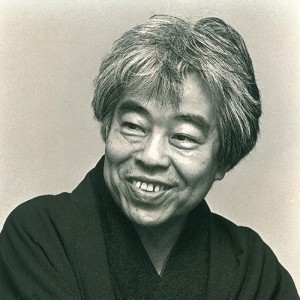書評
『中国歴史の旅 北京から西域へ』(集英社)
悠久の歴史を縦横に読む面白さ
陳舜臣はすでに「敦煌の旅」「シルクロードの旅」「北京の旅」など、何種類かの歴史紀行を出しているが、「中国歴史の旅」はそれらを一冊に要約すると同時に、歴史の旅の醍醐味を教えてくれる好著だ。「人民中国」に連載されたこの文章は、一方で「中国の歴史」(平凡社刊。全十五巻のうち現在、秦・前漢時代の第三巻まで刊行)を書き下ろすうえで、取材の意味をもこめてまとめられたともいえるが、足で歩いた強味が随所に光っている。
むかしは後藤朝太郎の「支那及満洲旅行案内」や米内山庸夫の「支那風土記」、あるいは興亜研究会編の「大陸旅行案内」や新民印書館の「北京案内記」などがよく読まれた。戦後も各種のガイドブックは出ているが、単なる案内書では満たされないむきには、陳舜臣の歴史紀行をすすめたい。
歴史紀行のおもしろさは、その土地に重層する歴史の層の厚味だ。中国のように古い国では、古代から現代まで、時代によって異なった文化や兵乱の跡がみられ、それが一つながりとなって、独特な風土感をかもし出している場合が少なくない。陳舜臣はそれらの異層に目をとめ、そこから人物地誌的なおもしろみを引き出している。その意味では彼の歴史紀行は、青木正児(まさる)の「江南春」や石田幹之助の「長安の春」の味を志向するものといえよう。
たとえば「桂林の山水は天下に甲(こう)たり」といわれる桂林を語って、漓江(りこう)下りや陽朔の景勝にふれると同時に、第五次の渡航に失敗した後、桂林に招かれ、一年ほどその土地にとどまった鑑真や、さらにそれから千年余を経て、太平天国革命に際し、洪秀全の率いる革命軍が、桂林城を攻めあぐねた話におよぶといった調子で、悠久の歴史を縦横に語るおもしろさが、そこに感じられる。
また杭州では春秋末期の呉越の争いから説きおこし、臥薪嘗胆(がしんしょうたん)の故事にふれ、西湖の景観を語り、この土地の地方長官となった白居易や蘇東坡(そとうば)におよび、南宋の岳飛や秦檜(しんかい)の対比、さらにはその地を訪れたマルコ・ポーロに至るといった叙述は、他の本でも見られるが、一九二四年九月二十五日に倒壊した雷峰塔にふれて、魯迅の文章を引用し、瓦礫の野にいるのは悲しむべきではないが、瓦礫の野で古い習慣を繕うことこそ悲しむべきだといい、雷峰塔は地上から消えたが、魯迅の言葉はいつまでも消えないと言っているあたりは、いかにもこの作者らしい目のくばりだ。
「中国歴史の旅」によって、旅へのいざないを感じる人はもちろんだが、中国史への関心をそそられる人は、同じ著者の「中国の歴史」にも目をとおすことで、一層のひろがりを得られるにちがいない。ともに、「ます」「です」調でわかりやすく書かれているのも特長だ。
ALL REVIEWSをフォローする