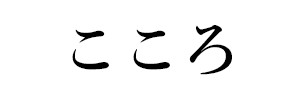書評
『abさんご』(文藝春秋)
「私」が消去された私小説
先日、第一四八回芥川賞に決まった黒田夏子『abさんご』は、まず七十五歳という史上最高齢での受賞が話題になり、次いで特異な書法とその読みにくさが話題になった(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2013年)。芥川賞選評でも選考委員が口々に苦戦したと告白しているほどだから、投げ出す読者がいても不思議はないし、実際途絶してしまった人も少なくないようだ。マスコミでも散々報じられたのである程度知られていると思うが、『abさんご』の書法について今一度、既出の論評や作者のインタビュー、対談なども参照して、少し細かく確認するところから始めよう。
①横書き、②漢字を開く/開かないに対する独自のルールに基づくと思われるひらがなの多用、③カタカナの排除、④カッコをはじめとする記号類の排除、⑤人称代名詞の排除、⑥固有名詞の排除、⑦人物を属性や行為で表す呼称、⑧普通名詞の言い換え、といった特徴が表面からざっと拾い上げられる。⑥まではすぐに確認できるだろう。
⑦は、人物を「おもいちがいをしている者」などと表すことを指す。「受像者」「家事がかり」といった表記も目立つ。「小児」「五十三さい」と年齢を代名詞的に用いるのも頻出する。こうした表現は、人称代名詞を避けたいという動機から導かれたもののようだ(『文學界』二〇一三年三月号の蓮實重彥との対談)。
⑧はたとえば「蚊帳」を「へやの中のへやのようなやわらかい檻」のように言い換えていることを指す。
もう少し読み込むと、⑨登場人物の性別が明らかでないことや、⑩特殊な受け身表現や造語的複合動詞が使われていることなどに気がつく。
⑨は、⑤人称代名詞の排除および⑥固有名詞の排除から派生しているように見える。それにともない「父」「母」「娘」といった一部の普通名詞も使用が避けられているが、逆に、性別を明らかにしたくないがゆえに人称代名詞や固有名詞が避けられることになった可能性も考えられる。
①から⑩までとりあえず並べてみたけれど、こうした要素が絡み合って、「質のよい磨りガラス越しに世界を見ている」(堀江敏幸の選評)ような、精緻でありながら同時に模糊とした『abさんご』の作品世界は実現されている。
幾人もが指摘しているとおり、語られていることはそれほど特殊ではない。煎じ詰めれば回想の物語だ。ただし時間の経過は一律でも直線的でもない。十五の断章は必ずしも時系列で並んではいないし、各章の中でも時間は自在に飛ぶ。
第一の章「受像者」で、「ゆめの受像者」が「半せいき」前にあった岐路を夢に見、目覚めて、選ばれなかった道に思いを巡らす情景から物語は始まる。五十年の間に取り戻しようもなく失われていった、ある親密だった親子の関係と、親子の住んだ家が、物語の主題ということにひとまずはなる。『abさんご』の「ab」とは、終章「こま」で像を結ぶが、選ぶことができなかったり、選ばれ得たかもしれなかったが選ばれなかった、現れては消えていった道の枝々を象徴している。
より具体的に書けばこうなる。子は最初、親(父だろう)と「三そう目」まである、つまり三階建ての、書庫があり使用人が複数いる「首都」の家に住んでいたが、小学校に進む直前五歳のときに戦火を逃れるために「小いえ」に移った。「潮かぜと砂ぼこりとがようしゃなく入りこみ」とあるから、この小さな家は、どこか海岸地帯に位置している。母は子が四歳のときに死んだがその記憶は薄い。子が十五歳、父が五十三歳のときに「家事がかり」と呼ばれる住み込みの使用人が雇い入れられる。この二十七歳の家事がかりは、雇い主と食卓を共にして悪びれない、「習俗の変わり目」を体現した「外来者」だ。家事がかりは、家を改変し、父子の関係を変容させて、ついには父の配偶者に収まる。家事がかりと折り合うことは不可能と覚っており、変質する家を嫌った子は、二十一歳のときに家を出て窮乏した生活を二十年送り、四十一か二歳のときに父の死に瀕することになる。
薄ぼんやりしたようでいながら、ある部分のディテール、とくに年齢や時間には偏執的厳密さがあり、丹念に拾っていけば以上のような確固とした物語を抽出することができる。破天荒な文法で書かれた日本語という予断もあるようだが、個々の文章は実はおおむね尋常な文法に従っている。統語的に独特なところがないわけではないがそれほど多くはない。
では、人々をしてつい「前衛」とか「実験」とか「難解」とかいわしめてしまう要因はどこにあるのか。
ひらがなが目を滑らせる、というのが第一の理由に挙げられることが多いようだ。横書きであることが生理的に受け付けないという向きもあるだろう。たしかにひらがなの横溢が一瞥で語の区切りや文節を捉えることを難しくしているのは間違いないし、作者も、漢字は視覚的である分、意味や機能を限定させるからひらがなに開くといくつかのインタビューで述べている。
閉じる/開くについて作者が明確なルールを持っていることは疑いないものの、第三者には恣意的に映る部分がないではない。その恣意性に正しく拘泥して躓く読者もいるに違いない。おそらく作者が「語源まで遡れるような気がする」(『文藝春秋』二〇一三年三月号)と答えるその「気がする」が重要である。小説というのは、言葉の操作で何かしらの世界を現出させようとする行為なのだから、関数のように律儀に対応する必要はあるまい。
だが、『abさんご』を読みがたいものにしている本当の要因は、たぶん別のところにある。
試みに、漢字に閉じカタカナに置き換え縦書きにして……という具合に直してみても、依然読み手を拒むような捉まえがたさは残るだろう(実際にやってみた)。
では、真に読み手を阻んでいるものは何か。
⑤人称代名詞の排除が究極的な要因であり、またこのことが本作品の本質を決定してもいる、というのが私の見立てである。
さっき抽出した物語を見れば容易に見当がつくように、『abさんご』は、実のところ私小説と見ることができる。それは作者も認めている。
つまり、普通なら「私」という一人称を書けば済むものが、「小児」だの「十五さい」だの「受像者」だの「たえだえのかよいじを足うらに知っていた者」だのと絶えず言い換えられ続けているわけだ。
私小説にとっての核はいうまでもなく「私」である。とするなら、「彼」や「彼女」ひいては「父」「母」が排除されたのも、「私」の道連れだったのではないか。⑥固有名詞の排除や⑧普通名詞の言い換えも、「私」が抹消されたことが波及した帰結なのではないか。
「私」が消され、その他の人称代名詞が消され、「父」「母」が消され、固有名詞が消され、それらが常に「私」同様の言い換えを施され続けるせいで、ちょっと気を許すと数行もしないうちに何を読んでいるのか見失いかねない、読者に極度の集中を強いる文章となって現れているのである。この事態の深刻さに比べれば、ひらがなだとか、横書きだとか、文法的にどうだとかは表面的で副次的なことにすぎない。
ではどうして「私」は消されなければならなかったのか。
おそらく「私」や「父」「母」やその他のものが混沌とした状況、彼我の向こうから現れる「ゆめ」のようなものとしてでなければこの小説は書かれ得なかったからだ。
帰着点がにがすぎればたちあらわれてはならないたぐいのゆめがあった。
父の死後十数年を経てようやく「帰着点」は苦いものではなくなり、いや、それどころか一転甘美なものに変わり「ゆめ」は語られ始めた。
朝の帰着点がさざめきでかざられるようになった者が,ゆめの小べやの戸をあけると,さきに死んだほうの親がふとんに寝ていた.(…)そうだったのか,あけさえすればずっとここにいたのだったかとなっとくした者は,じぶんの長いうかつなおもいこみをやすらかにあきれていた。
この「帰着点」とはまさしく彼岸ではないか? 彼岸において親と再会し「そこからぜんぶをやりなおせるとかんじる」者はむろん死んでいなければならない。だが「私」である者は生きている。ならばせめて「私」を消す、殺すことでしか「ゆめ」を語り始めることはできまい。
『abさんご』は、戦前から平成にまでわたる喪失の物語であると同時に、「私」であることをやめた「私」がその生涯の「やりなおし」を記した再生の物語である。
断言するけれど、この小説は、是非とも最後まで読み通さねばならない。でないと、話題作りを狙った実験もどきの奇異な小説という浅薄な理解で終わってしまいかねない。
終章「こま」の終わりで、父に連れられた「小児」が道の分岐に差しかかり、目をつむりこまのように回って止まったほうへ行こうという遊びをしている。小児には「aの道」からも「bの道」からもさまざまな匂いが溢れ寄せて楽しげだ。小児はそのどちらも選ぶことができるだろう。だが「aの道」「bの道」は、五十年の間に無数にあり選ばれなかったすべての岐路の集約なのだ。この希望と諦念が重ね合わさった岐路と、そこを覆う苦い歓喜に至るたびに、私はきっと何度でも胸を詰まらせるだろう。