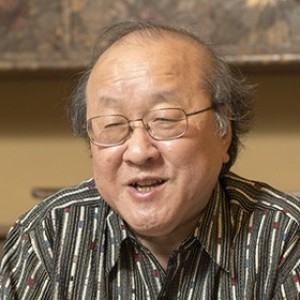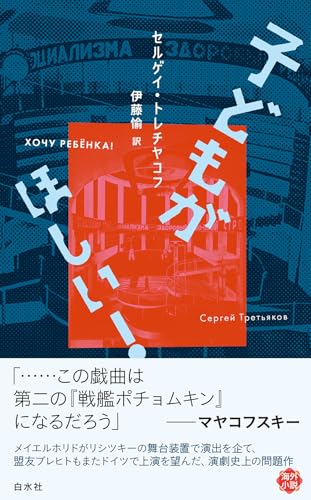書評
『ある男』(文藝春秋)
理知と繊細な情感の融合
平野啓一郎の新作長編『ある男』は、意表をつくようなシンプルなタイトルとは裏腹に、様々な要素を複雑に絡み合わせ、小説家の技と知識を駆使して練り上げた作品である。理知的な論理構成と、社会問題に対する鋭い意識、そして人の心の襞(ひだ)によりそう繊細な情感が溶け合った作品だ。物語は、少し古風に小説家自身と思(おぼ)しき人物が登場する「序」を前置きにして、東日本大震災の年の秋、宮崎県の過疎化が進んだある小さな町から始まる。最初の主役は、首都圏での結婚と離婚を経て、息子を連れてこの町に戻り、親の店を切り盛りするようになった「文房具屋の里枝(りえ)ちゃん」だ。ここで彼女は、どこからか流れ着いて、黙々と林業の仕事に精を出す谷口大祐(たにぐちだいすけ)という男と出会い、再婚する。大祐はじつは伊香保温泉の旅館の次男なのだが、家族との不和が高じて家を捨てたのだという。こうして里枝は大祐と、さびれた地方都市で、ささやかながらも幸せな結婚生活を送り始めるのだが、それも束(つか)の間、四年も経(た)たないうちに大祐は伐採の作業中に事故死してしまう。
ここまでだけでもじつに見事な短編になっているのだが、小説のこの先の展開は目がくらむほどだ。里枝と結婚していた大祐を名乗る男は、じつは伊香保温泉の旅館の次男になりすました別人だったということが分かり、里枝の依頼を受けて、弁護士の城戸(きど)が探偵さながらの調査にのめり込んでいく。その結果次第に分かってくるのは(ネタばれになるので、はっきりは書かないが)、戸籍を交換し「身許(みもと)のロンダリング」をする人々の存在である。
ここまで設定を説明してきて、この小説があまりにも多面的で、このように限られた紙面ではその魅力の全容をとても紹介できないことを痛感する。確かに、この作品は身許不明の男“X”の正体を探る一種のミステリー小説として第一級のものだが、それは一本の縦糸に過ぎない。戸籍の交換によって他人の生を生きるとはどういうことか、つまり「自分とは何か?」という存在論的な問題が突き詰められる一方で、在日三世である城戸という弁護士を通じて、民族差別やヘイトスピーチが横行する現代日本の社会問題が鋭く照射される。“X”の父の犯したおぞましい過去の犯罪があぶり出されるとともに、死刑制度に対する問いかけも生じる。そして死刑囚の息子“X”がすさんだ家庭環境から逃げ出そうとし、ボクサーとして栄光をつかみかけながら、転落していったというドラマもある。
そうかと思えば、在日三世である城戸と日本人であるその妻の関係がしだいにぎくしゃくしていき、離婚の縁まで行きながら、辛うじて踏みとどまっている、いわば「大人の愛」も緻密に描かれる。そして城戸が調査の過程で知り合った美涼(みすず)(大祐の元恋人)との間に芽生えかけた恋愛感情が断念される様子は、あまりに切ない。さらに、城戸や里枝のそれぞれの幼い子供たちの姿に精彩があり、そのこと自体が小説を明るく照らすメッセージにもなっている。
人間とは多面的なもので、ある一つの属性のレッテルを張っても理解できない――というのが本書を貫く人間観である。だからこそタイトルも「ある男」なのだろう。それは本書で描かれる「愛」についても、そしてこの「小説」についても同様である。この小説を何と呼ぶにせよ、これほど小説を読んだという手ごたえを与えてくれる作品は稀(まれ)である。いま小説にしかできないことを、平野啓一郎は見事に成し遂げた。
ALL REVIEWSをフォローする