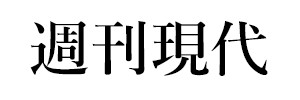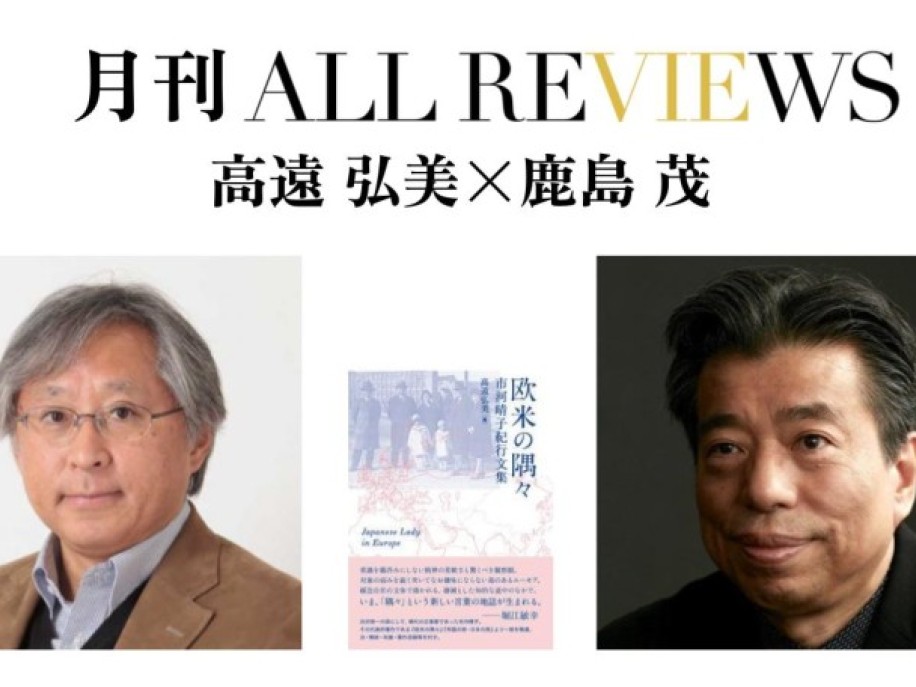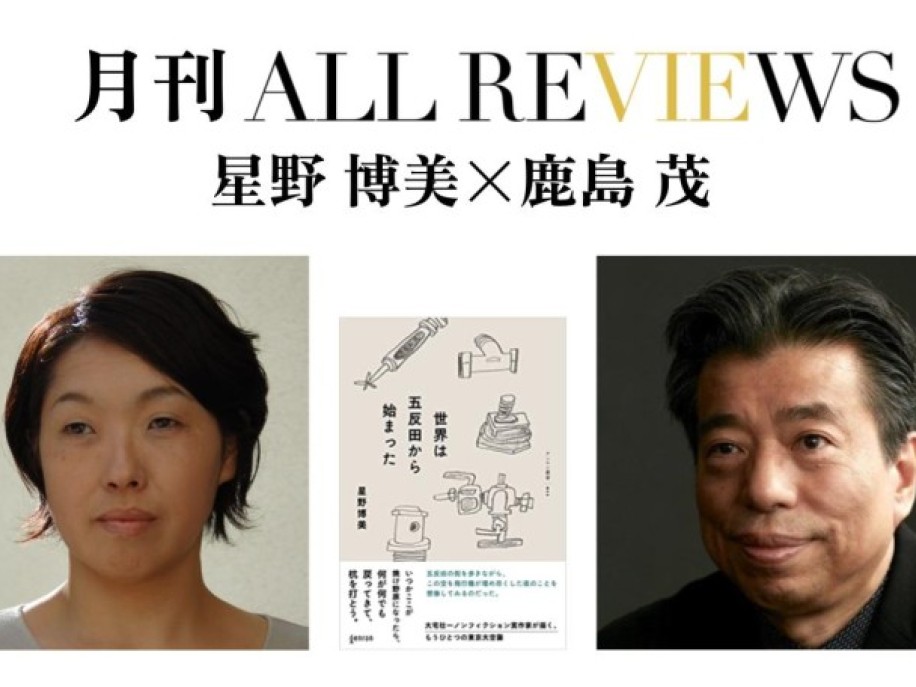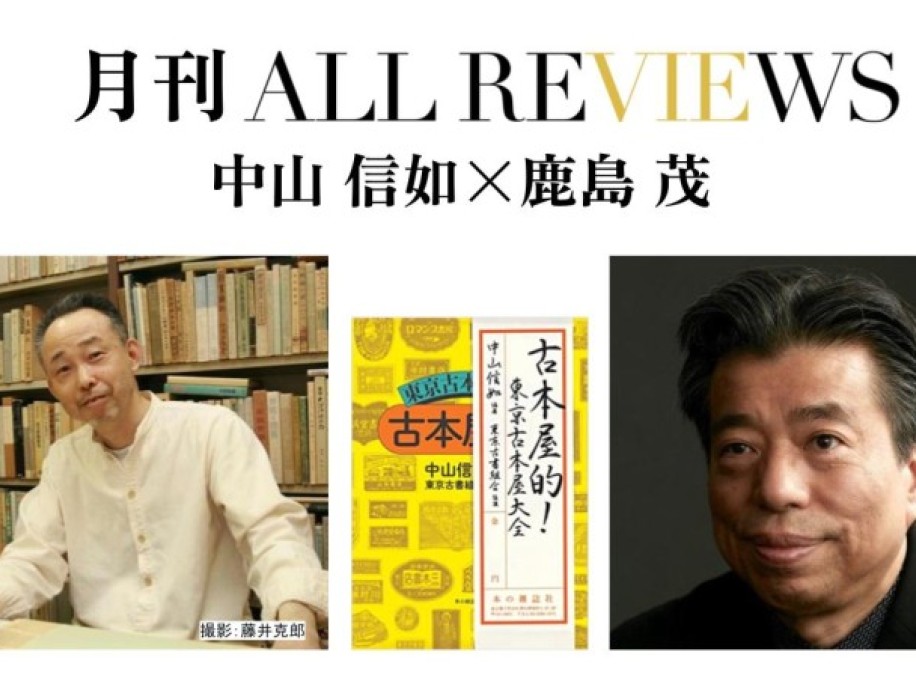書評
『小林一三 - 日本が生んだ偉大なる経営イノベーター』(中央公論新社)
人口急増そのものがビジネスになる――日本の大衆消費社会の基盤をつくった男
昭和の高度経済成長の時代、首都圏のサラリーマンは通勤苦に見舞われた。遠・狭・高、遠くて狭いうえ住宅購入には年収の5倍以上を見込まねばならなかった。だが旺盛な購買意欲はいつしか減退、高齢化と人口減少で住宅事情が変わりつつある。平成時代は、親が苦労してローンを払い終えた空き家に住めばよく、あるいは通勤2時間の分譲住宅を嫌い銀座まで15分の埋立地の高層賃貸マンションを選ぶ。
人々のライフスタイルが人口動態によって振り回されるようになったのは日本が近代社会に突入してからだ。
明治時代に人口の急増そのものがビジネスとなると気づいたのは阪急の創業者というより宝塚少女歌劇の考案者として知られる小林一三であった。ならば現代の人口急減もまたビジネスになり得ると著者が考え本書が発想された。
風光明媚で未開拓の割安な分譲地を仕入れ、そこに鉄道を敷くことで都心のスラム化した環境に代わる快適な住空間とコミュニティー、そして娯楽を提供する。日本はこうしてヨーロッパ近代とは異なる日本独自の大衆消費社会の基盤を作ったのである。
明治6年生まれの小林が大阪で実現させたモデルは、東京では明治15年生まれの五島慶太により鉄道路線の伸長と住宅開発をひとかたまりにした不動産ビジネスモデル・田園都市構想として展開し(拙著『土地の神話』)、明治22年生まれの堤康次郎が電車の終点の彼方に拓かれた箱根・軽井沢などホテル・リゾート開発として結実(『ミカドの肖像』)させた。
五島や堤など後続部隊が活躍できたのは若い時分に作家を志した小林一三のリベラルアーツの素養が思想化されたからだった。だがやがて時代が転変、太平洋戦争突入の時代へと移る。統制経済を主導する革新官僚“昭和の妖怪”岸信介と自由主義者小林一三の激突ぶりを活写する著者鹿島茂の筆は冴える。残念ながら日本の近代は常に官僚の壁に突き当たるのである 。
ALL REVIEWSをフォローする