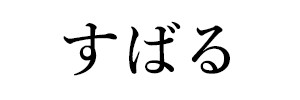書評
『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(文藝春秋)
世代を違えてリフレインされた喪失と疎外
過去の作品のエコーがそこここに響いている最新長篇である(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2013年)。多崎つくるは三十六歳で駅舎の設計士をしている。つくるは高校時代「特別なケミストリー」により結びついた親友四人からなる共同体に属していた。彼らは男女二人ずつでみな名前に色が含まれていたが、つくるだけ色を欠いていた。ところが大学二年のとき、四人から突然一方的に理由も明かされずに激しく拒絶される。深く衝撃を受けたつくるは死に取り憑かれた五ヶ月を過ごし、何とか生の側に戻るのだが、容姿も精神もすっかり別人のように変わってしまう。
その後、灰田というやはり名前に色を持つ二歳年下の友人ができるが、灰田もまた彼の前から突然姿を消す。
四人と音信を断ってから十六年後、沙羅という二歳年上の女性と出会ったつくるは、彼女に過去の出来事を話す。沙羅はつくるがその問題を解決しない限りこれ以上の関係には進めないと宣告し、真相究明を促す。ここから始まるつくるの旅がすなわち「巡礼」である。
四人それぞれとの再会を果たすごとに過去の謎は明らかになっていくが完全には解明されない。灰田のその後も書かれないし、沙羅との顛末もオープンエンドだ。こうした落着の付け方にも読者は過去作品のエコーを聞くだろうし、人物も類型的ではある。異界の影もあるし、リトル・ピープルみたいな「悪いこびと」も出てくる。三十六歳という年齢に着目すると、初期短篇「プールサイド」も連想される。
何より既視感をもたらすのは、主人公の喪失感や疎外感が、デビュー作以来のモチーフの反復に見えることだろう。
だが見逃せない相違も存在する。それは主人公の属する世代だ。これまでは喪失感や疎外感を抱えた主人公の多くは作者と同世代でありその分身だった。一方、今作のつくるは、いわば作者の子供の世代にあたる。そのことは灰田の父のエピソードで示唆されてもいる。
灰田の父が緑川というジャズ・ピアニストに悪魔の取り引きを持ちかけられるシーンは、小説から浮き上がっているものの、かつての主題を集約して後景に退かせたものと見ることができ存外に重要な箇所である。「色彩」の暗示するものが具体的に開示されるくだりでもある。
したがって問題はこう書き換えることができるだろう。世代を違えた相似形の主題が二重写しでリフレインされているのは何故か、何を描こうとしているのかと。
一見シンプルで軽めながら、重層的な主題と構造を持った作品である。
ALL REVIEWSをフォローする