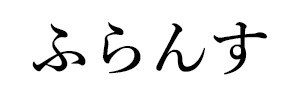書評
『プルースト/バタイユ/ブランショ―十字路のエクリチュール』(水声社)
待機することの厳しさ
いまロジェ・ラポルトの名を口にするのは、かなり危険なことかもしれない。一九六三年の『不眠』以来、ひとつの文学ジャンルを超えた自伝とも伝記ともつかない、Biographieとあえて原綴で記すべき宙づりの言語を紡ぎつづけているこの作家の仕事は、フランスはもとより現在の日本の「書物」が置かれている状況のなかで、彼の名をあえて無視する以外に身を持す道はないという、怖ろしく悲観的な認識を読者にもたらすからである。プルースト、バタイユ、ブランショをめぐる飾り気のない言葉がならぶこの美しい書物には、著者の声に耳を傾ける人々を増やすかわりに、そんな声など聞こえないかのごとくやり過ごすしかないとの諦念をひろめる要素に満ちている。破滅を導くセイレーンの歌を聴く勇気を持ち合わせていない人間が触れてはならない性質の書物であることはまちがいなく、その意味で本稿もまた、脆弱な沈黙に堕さざるをえないだろう。冒頭に収められたプルースト論の、一個の人生との関連ではなくこれから書かれる「作品」にのみ結ばれた強靱な本能とでも呼ぶべき姿勢としての「倫理」の追及や、バタイユの内的体験を徴づける「満足の不在」とその持続への関心、さらには「到来せぬものであり、あらゆる到来を宙づりにした」ブランショの言う「災厄」への注視は、ラポルトその人の執筆活動と深く連動している。これは哲学や批評といったジャンル分けに属さないひとつの賭けに近い行為なのだ。一九七〇年の『フーガ』ののち、みずから書きつづけることによって維持してきた「中性的」なものへの意志どころか、書物という終着点を目指しての執筆に対する欲望が消え失せ、それこそ「災厄」の張りつめた気配を感じとれなくなったラポルトにとって、文学を正当化する秘蹟を理解できぬまま一行も「書けない」話者の物語に半生を費やしたプルーストの苦悩は、規模こそ異なるものの、ほとんど自分自身の問題として深く刻まれていただろう。
起源に近づけば近づくほど遠ざかり、断じて形にならない書物を準備しつづけること。一冊のすばらしい書物を世に問うたあと突然の沈黙期に入り、書かない詩人、書かない小説家、書かない思想家を演じて隠然たる影響力を周囲に及ぼすよりも、いまだ誰も目にしたことのない書物に向けて永遠に書きつづけ、おそらくは死によってしか切断されえない未完の苦行に身を投ずるほうがずっと困難なのだ。至高の一点が同時に貧しさの極点であり、その極点がたえまなく先にずらされているとしたら、それほどの難行に立ち向かう者が存在しないことを嘆く権利など、誰にもありはしないだろう。
ラポルトに寄り添いながら熱のこもった注記で訳者が語るように、たとえばバタイユの「私は幸福になること(救われること)を拒絶する」といった言葉を注釈や紹介から離れた次元で現実に日本語に移植した例があったかと自問するとき、徳目を超えているはずの「倫理」は、やはり字義どおりの「倫理」をも含まざるをえない。ラポルトが実践する永遠の《待機》の厳しさは、急ぎ足の書物を生むだけの私たちをたじろがせるにじゅうぶんなものである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする