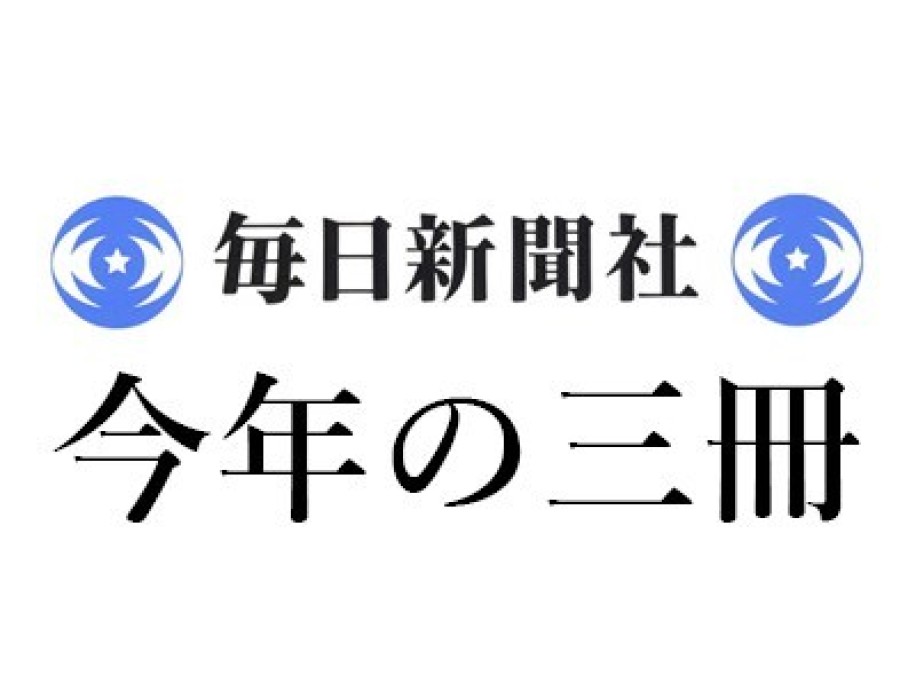書評
『ヨーロッパとゲルマン部族国家』(白水社)
現代の異民族問題考える手がかりに
ヨーロッパに行くと、しばしば冗談じみた話を耳にする。「ワイン愛好者は文明人、ビール愛好者は野蛮人」「ライン河の南側は文明の地、北側は野蛮地帯」など。なるほどローマ帝国の領土拡大はぶどう栽培地の拡(ひろ)がりとほぼ重なっているのだ。昨今、移民・難民問題が取り沙汰されるせいか、しばしば古代末期以降のゲルマン民族の大移動が注目される。たしかに、異民族と接触するとなると、どこか不気味さがつきまとう。それも大移動となると、その混迷の様は想像を絶する。だが、近年の研究の示唆するところでは、「大移動」とは神話にすぎないという。じっさい、「蛮族」とよばれる異民族とローマ人は対立こそしていたが、それと同じくらい意思疎通も度重ねていたらしい。
三世紀からローマ軍にとって徴兵問題は慢性化していた。異民族に有能な戦闘員がいることが知られ、彼らはすんなりとローマ軍に雇われていた。しばしば注目される三七六年とは、ゴート族の一部が河を渡って帝国内に入ることを認められたことである。ローマ法に服しながら、数万の戦闘員を擁する異民族集団が定住することになった。
ところが、異民族管理を請け負う官吏のなかには職権乱用をくりかえし、ゴート族の食糧を横領したり、子供を奴隷として売りとばす輩(やから)もいたという。このような不届きな行為が反感を招き、ときに反乱にいたる。ローマ軍人と「蛮族」との対立の発端にはこのような出来事があった。
三七八年、反乱の鎮圧にあたったローマ軍が大敗し、ローマ不敗の神話が幕を閉じた。「蛮族」は自信をもつようになり、ローマの政界においても勢いづく。五世紀になると、世界の中心であるローマが略奪され、大都市カルタゴも略奪された。やがて、四七六年、幼い西ローマ皇帝が「蛮族」の手で廃位させられたが、それはほとんど目立たぬ幕切れにすぎなかった。
帝国の晩年ともいえる時代について、かつて市民意識の長期的衰退が最後の崩壊にいたるまで帝国を弱体化したと言われていた。しかし、この崩壊の原因は、「蛮族」の側にあると本書は指摘する。恐るべき軍事力をもつ族長が登場したこと、勝利のみが正当性をもつ社会ではローマ人による反「蛮族」イデオロギーの宣伝がかえって不利になったこと、異民族の部族集団はもはや帝国にではなく財力のある個人になびいたことなどが挙げられる。
四世紀以降、ローマ帝国では、キリスト教が公認され、やがて国教とされた。興味深いことに、神々を奉じていたはずの「蛮族」だったが、かなり容易にキリスト教を受け容(い)れている。おそらく移動をくりかえすなかで伝来の慣習がすたれ、改宗しやすかったのではないだろうか。しかし「蛮族」はカトリック正統派ではなく、異端のアリウス派を信奉したという。その方が帝国教会の序列から独立した聖職者を立てることができたのである。
五世紀末になると、「蛮族」の諸勢力は、ローマ文明の伝統の大方を存続させながら、帝国のかつての属州の地にそれぞれ自立した形で部族国家を形成したのである。たとえば、ローマ法の粋をまとめた『西ゴート族のローマ法』を実現して、その規範の下で法秩序を回復した。このような拡がりのなかで、西方の諸部族国家は徐々に安定していくのだが、それにはなによりも「蛮族」がローマ・カトリックに改宗したことが注目される。
古代末期・中世初期という時代にヨーロッパが形を成しつつあったときに、これらの「蛮族」の生態は、異民族問題で立ちすくむ現代にもなんらかの手がかりを与えてくれそうである。
ALL REVIEWSをフォローする