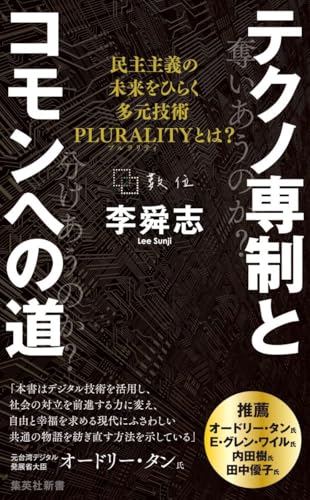書評
『俺たちはどう生きるか』(集英社)
他者を問い詰めながら返す刀で自問自答する
著者がパーソナリティーを務めるラジオに2年近く出演している。隔週で10分弱、主に時事問題について話しに出向く。スタジオに入り、喋り、そのまま出るので、スタジオ以外の場でじっくり話したことはない。あちらがグッと身を乗り出す瞬間がある。身を乗り出して持論を述べるのではない。身を乗り出して話を聞こうとするのだ。仕事柄、様々な年長者に会うが、年が半分くらいの若造にそういう態度で接してくれる人は少ない。傾聴し、受け止めてから、自分の考えを切り出してくる。
俺にはわからないことがある、という態度が自身の起点にある。それが、野心としてうごめいている。「私はどこにもくみする者ではない」「誰も答えてはくれない。一人なのだから。人は一人なのだから」、こういう断言が顔を出すのに、読み進めていくと、その断言がたちまち溶け、いつまでも迷っている。
世の中がきな臭いままだ。その時に、臭さの原因を手厳しく問い詰めながら、でも、もしかして臭さの原因は自分にもあるのではないかと悩む。それって、視野が広い。こんな世の中はどうなのか、と語った後に、そんなことを言っている自分はどうなのか、と自問自答する。回り道の途中で迷っている自分をわざわざ知らせてくる。
「心底、庶民の側に立っていたいとの気持ちでやってきたが、全世界を敵にまわしたい欲望にもかられる今日この頃である」とある。善意と悪意というのは反対側にあるのではなく、隣で座っているものなのかもしれない。「すまん。若者よ。君たちに伝える言葉をこの年寄りは持っていなかった」。あの大竹まことがまだ答えに迷っているのである。じゃあ、自分は、当然、まだ迷っていいと思える。勇気の与え方がとても優しい一冊だ。
ALL REVIEWSをフォローする