書評
『男女という制度』(岩波書店)
子供の頃、お転婆だったわたしの遊び相手はもっぱら男子。でもって、自分のことを「あたし」って言うたび内心「ゲェーッ」とか思ってた。中学に上がった時も「ゲェーッ」。
野球部には入れずソフトボール部で我慢させられ、スカートなんかはきたくないのに可愛らしいセーラー服着せられて。なんで自分は「あたし」なんだろ、己の存在そのものに違和感を覚えるほどのアイデンティティーの揺らぎを体験させられたのである。その時に見いだした妥協点が「わたし」。それなら男も使うし、英語における「I(アイ)」に一番近かろうと思ったのだ。今でも、わたしは「あたし」を遠ざけている。「あたし」は自分じゃないと思ってる。
『妊娠小説』や『紅一点論』等の、小気味よい著書で知られる斎藤美奈子氏が編者となっている『男女という制度』は、そんな男子と女子の間に立ちふさがる“ベルリンの壁”に気づいて意気消沈していた頃の自分に読ませてやりたいジェンダー批評集だ。作家・藤野千夜氏による「日本語とセクシュアリティ」なんか特に。
藤野氏は現代日本語の小説言語における男女差を考えている。人称や語尾の違いだけでなく、話の内容ひとつとっても、話者の性差によって無意識裡に書き分けてきた日本の小説。それを易しい例文を挙げながら、ユーモラスな筆致で検証していくのだ。この肩の力の入らなさ加減がいい。幼い頃から、スカートとズボンをはじめとする社会の男女棲み分け構造に悩んできたわりに、実は攻撃的フェミニズムが苦手なわたしは、キィキィ怒った声が行間から聞こえてきそうな角張った論を読んでいると、「あんたたちだけが悪いわけじゃない」と男をかばってやりたくなってしまうのだ。
でも、冒頭にある「編者から読者へ」という斎藤氏の一文の中に、〈フェミニズム批評ないしジェンダー批評は、わずか一〇年あまりでカンブリア紀から白亜紀くらいまでの急激な飛躍をとげた感があります〉とあるように、本書に収められている全九論にはそんな旧態依然とした一方的な攻撃はほとんど見られない。たとえば、作家・川上弘美氏の「『あたし』という恋愛体質論」。恋愛体質という抽象概念を語り手に、男女が愛し合って結ばれるのを健全とする近代の概念“ロマンチック・ラブ・イデオロギー”に、アイロニカルなメスを入れたこの短編小説風エッセイがかもすおかしみは絶品だ。
「ホルモンのせいね」とおばさんはあたしに向かって言った。
「ホルモンて、なに」
「エストラジオールっていう名前なんですって、脊椎動物の発情ホルモンは」おばさんはあたしの問いを無視して、つぶやいた。
「あの子ったらホルモンのせいで浮かれてるだけなのにねえ。恋だの愛だの言っちゃってさ」
この、あまりにも身も蓋もないエピソードが綴られている欄外に、川上氏が自註として提出しているのが、なんとエストラジオールとかいう物質の化学式なのである。この茶目っ気! そんな柔らかでしなやかな姿勢こそが〈学問の領域に閉じこめられつつあるジェンダー批評を、より広範な読者と共有する回路〉を目指して本書を編んだ斎藤氏の志というものではないだろうか。
さて、書評をする立場の者としては性差別表現があろうが、それ自身は小説の善し悪しを判定する材料にはならないと考えている。だから金井景子氏の「ジェンダー・フリー教材をさがしに」を読み、教科書で『伊豆の踊り子』の女性差別に抵触する表現が削除されていることを知った時は脱力してしまった。金井氏も書いているとおり、そうした言説に触れることで逆にジェンダー意識について学ぶことができるはずなのに。臭いものには蓋をしろ的発想って、いまだにすたれてないんですかね~。
これは、そんなこんなの大事なことを色々考えるきっかけになってくれる、開かれた評論集なのだ。と、「わたし」は思うんだけど、「あたし」はどう思う?
【この書評が収録されている書籍】
野球部には入れずソフトボール部で我慢させられ、スカートなんかはきたくないのに可愛らしいセーラー服着せられて。なんで自分は「あたし」なんだろ、己の存在そのものに違和感を覚えるほどのアイデンティティーの揺らぎを体験させられたのである。その時に見いだした妥協点が「わたし」。それなら男も使うし、英語における「I(アイ)」に一番近かろうと思ったのだ。今でも、わたしは「あたし」を遠ざけている。「あたし」は自分じゃないと思ってる。
『妊娠小説』や『紅一点論』等の、小気味よい著書で知られる斎藤美奈子氏が編者となっている『男女という制度』は、そんな男子と女子の間に立ちふさがる“ベルリンの壁”に気づいて意気消沈していた頃の自分に読ませてやりたいジェンダー批評集だ。作家・藤野千夜氏による「日本語とセクシュアリティ」なんか特に。
藤野氏は現代日本語の小説言語における男女差を考えている。人称や語尾の違いだけでなく、話の内容ひとつとっても、話者の性差によって無意識裡に書き分けてきた日本の小説。それを易しい例文を挙げながら、ユーモラスな筆致で検証していくのだ。この肩の力の入らなさ加減がいい。幼い頃から、スカートとズボンをはじめとする社会の男女棲み分け構造に悩んできたわりに、実は攻撃的フェミニズムが苦手なわたしは、キィキィ怒った声が行間から聞こえてきそうな角張った論を読んでいると、「あんたたちだけが悪いわけじゃない」と男をかばってやりたくなってしまうのだ。
でも、冒頭にある「編者から読者へ」という斎藤氏の一文の中に、〈フェミニズム批評ないしジェンダー批評は、わずか一〇年あまりでカンブリア紀から白亜紀くらいまでの急激な飛躍をとげた感があります〉とあるように、本書に収められている全九論にはそんな旧態依然とした一方的な攻撃はほとんど見られない。たとえば、作家・川上弘美氏の「『あたし』という恋愛体質論」。恋愛体質という抽象概念を語り手に、男女が愛し合って結ばれるのを健全とする近代の概念“ロマンチック・ラブ・イデオロギー”に、アイロニカルなメスを入れたこの短編小説風エッセイがかもすおかしみは絶品だ。
「ホルモンのせいね」とおばさんはあたしに向かって言った。
「ホルモンて、なに」
「エストラジオールっていう名前なんですって、脊椎動物の発情ホルモンは」おばさんはあたしの問いを無視して、つぶやいた。
「あの子ったらホルモンのせいで浮かれてるだけなのにねえ。恋だの愛だの言っちゃってさ」
この、あまりにも身も蓋もないエピソードが綴られている欄外に、川上氏が自註として提出しているのが、なんとエストラジオールとかいう物質の化学式なのである。この茶目っ気! そんな柔らかでしなやかな姿勢こそが〈学問の領域に閉じこめられつつあるジェンダー批評を、より広範な読者と共有する回路〉を目指して本書を編んだ斎藤氏の志というものではないだろうか。
さて、書評をする立場の者としては性差別表現があろうが、それ自身は小説の善し悪しを判定する材料にはならないと考えている。だから金井景子氏の「ジェンダー・フリー教材をさがしに」を読み、教科書で『伊豆の踊り子』の女性差別に抵触する表現が削除されていることを知った時は脱力してしまった。金井氏も書いているとおり、そうした言説に触れることで逆にジェンダー意識について学ぶことができるはずなのに。臭いものには蓋をしろ的発想って、いまだにすたれてないんですかね~。
これは、そんなこんなの大事なことを色々考えるきっかけになってくれる、開かれた評論集なのだ。と、「わたし」は思うんだけど、「あたし」はどう思う?
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
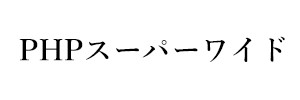
PHPスーパーワイド(終刊) 2002年3月号
ALL REVIEWSをフォローする






































