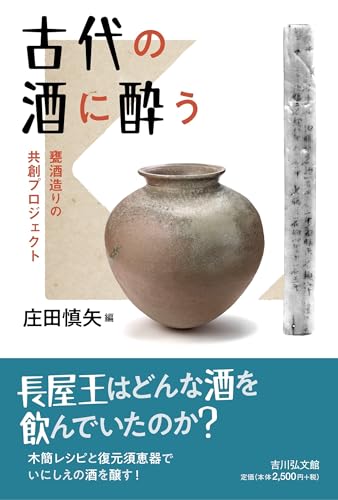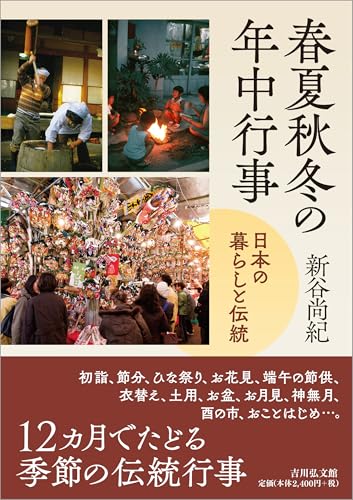書評
『パリの廃墟』(みすず書房)
冬、六時頃、たいてい私は通りを左手にくだって公園を抜けていくのだが、椅子や小さな茂みに足を取られてしまうのは、愛のごとく理解しがたい空が近づき、私の目をすっかり吸い込んでいるからだ。
空の詩人、ジャック・レダの限りなく詩に近い散文集『パリの廃嘘』は、こんな美しい一文から幕をあける。パリとその郊外をそぞろ歩き、目に留まった光景や、その折々の心境を〈ピチカート〉のリズムで描くレダ。彼が好んで歩くのはゴミが浮かぶ運河沿い、空き地、廃線跡など観光客が見向きもしないような場所ばかりだし、彼の目に映るのは囃し歌をうたっている小さな女の子たちや、瓦礫の中でいろんなものを拾っている自らのご同類、じょうろを手にした女性、木立の中に立ち尽くす灰色の馬といった日常の光景だ。レダはその意図を、郊外で出会った老人に明かす。
〈これほどの荒廃と無秩序の侵攻(あなたの小屋や菜園、工場、人川、建物二棟、別邸、樹林、タイヤ三百個)が気に入っているのは、一種の天啓がそこで準備されているという、あるいはそれが約束されているという確信があるからです〉と。移動手段は徒歩、モーター付き自転車ソレックス、バス、列車と様々だ。とはいえ、レダは〈そこでぐずぐずしたりはしない〉。
どんな場所でも私は長居しないのである。すぐにべつの場所にいることを想像してしまうからだ。到着する時間があれば、出発する時間がある。両者のはざまで、私はあっという間におのれの存在という概念を失う。たぶん私は、私を待っている他者なのだろう。
一箇所にとどまらないレダは、光景や時間のうつろいの中に、表現者としてのエゴなんていう俗な代物ではなく、永遠普遍のかけらを見いだす。そして、書く。そんな詩人が歩き、ソレックスで走り抜けるパリは、だから、わたしたちの知らないパリだ。……いや、もしかすると、レダの視線を失った後には、存在すらしないnowhereなのかもしれない。堀江敏幸氏の訳を得て、どの散文も素晴らしく味わい深い。冬の長い夜を共に過ごす相手として申し分のない一冊なのである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする