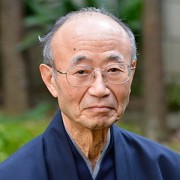書評
『蕨野行』(文藝春秋)
死へ旅立つ年寄り、語りの威力
ババ捨てジジ捨ての物語である。深沢七郎の「楢山節考」が世にあらわれてから、すでに長い歳月が流れている。あのころ、このテーマはまだ異郷の奇譚に近かった。だが今日それは、とても絵空事とは思えない現実味を帯びて、この世の定めを浮かびあがらせる主題となっているのではないだろうか。
時は藩という言葉がまだ生きていたころ、所はどこにでもみられたであろう通常の村。そこでは男も女も六十の峠をこえると、ワラビ野という山間の台地に入って生を終えることになっていた。家々の食いぶちを節約するためであり、若い世代の存続を願ってのことだ。
その年の春先、九人のジジババが連れ立って山に入った。破れ小屋に寝起きをともにする日々が始まる。朝になると里に下り、野良仕事のかわりに一日の糧をもらって山に帰る。里に下っても、もとの家族と言葉を交わすことはできない。そういう掟になっている。
暑い夏をへて、やがて雪の降りしきる冬へと季節が移っていく。足腰がなえて里下りのできない者がでる。眼が見えなくなる者、呆(ぼ)けのためウロウロする者、山の中に木の実を求め野鳥や川魚を追って飢えをみたそうとする者……。だがそれも束の間のこと、一人去り二人去りして、みんなあの世に旅立っていく。
物語はワラビ野に入った姑と家にのこされた嫁が、たがいに思いのたけを語りかける形で、展開していく。その語りの独特の言葉遣いが異常な効果を発揮して生動している。逝く者が食を絶って最後を迎える恍惚の一瞬、盲いたジジが若き日のババを幻視してからだを寄せていく一刻、などが、その語りのリズムの中からつむぎだされていく。なかでも語り手の姑が、死んでのち魂魄(こんぱく)となって嫁の胎内に宿り、新しい生をえて家族を守りつづけようと遺言するところが、胸をうつ。
磨きぬかれた文章と深い内省に裏打ちされた構想によって、この作品は間違いなく時代の水準を超えていると、私は思う。
ALL REVIEWSをフォローする