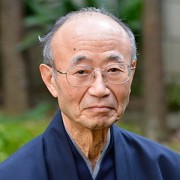書評
『教皇庁の闇の奥―キリストの代理人たち』(リブロポート)
“パンドラの箱”を果敢に開く
ローマのバチカン(教皇庁)は、たしかに世界の摩天楼だ。なぜならそこには、人類のあらゆる叡知(えいち)と狡知(こうち)、一切の残虐と淫蕩(いんとう)が、まるで腸詰めのようにぎっしりつまっているからである。本書はその宝庫のような、パンドラの箱のような深奥の内部を、白日の下に照らしだそうとした果敢な試みである。戦前アンドレ・ジッドが「法王庁の抜け穴」を書いてバチカンを戯画化し、第二次大戦後はR・ホーホフートが「神の代理人」を創作して、ナチのユダヤ人迫害に沈黙を守った教皇を告発したことが思いだされる。
むろん本書はこの二著のように創作ではない。ちゃんとした歴史的事実にもとづくノンフィクションである。訳書の分量が九百ページに及ぶ大作だが、叙述は平明であり、効果をねらった劇的な展開が興趣をそそる。
著者のキャリアがまた異色だ。ローマのグレゴリオ大学を卒業し、ウェストミンスター神学校で形而上(けいじじょう)学と倫理学の教授を六年間、コルプス・クリスティ大学で神学部長を六年間務めたのちに、聖職を去っている。おそらく著者自身の結婚問題がからんでいたものと思われる。
本書を通読していて驚かされるのは、バチカンの歴史をひもとくことはほとんど全ヨーロッパに及ぶ政治・経済史、軍事史、法制史のすべてにふれることになるという発見である。それだけではない。ミケランジェロを中心とする芸術、ガリレオ裁判にまつわる科学と宗教の闘争、あげくのはてに酸鼻のきわみとしかいいようのない魔女狩りの実態……。
なかでも前半を占める歴代教皇の列伝は、西欧「三国志」さながらの権謀と怪奇にみちあふれ、後半では聖職者独身制の問題が離婚、避妊、人工中絶などの今日的テーマとともに大きくクローズアップされ、執拗(しつよう)に論じられている。そこには著者の体験がにじみでており、教皇庁にたいする渇くような期待感が通奏低音のように鳴りひびいている。遠藤利国訳。
ALL REVIEWSをフォローする