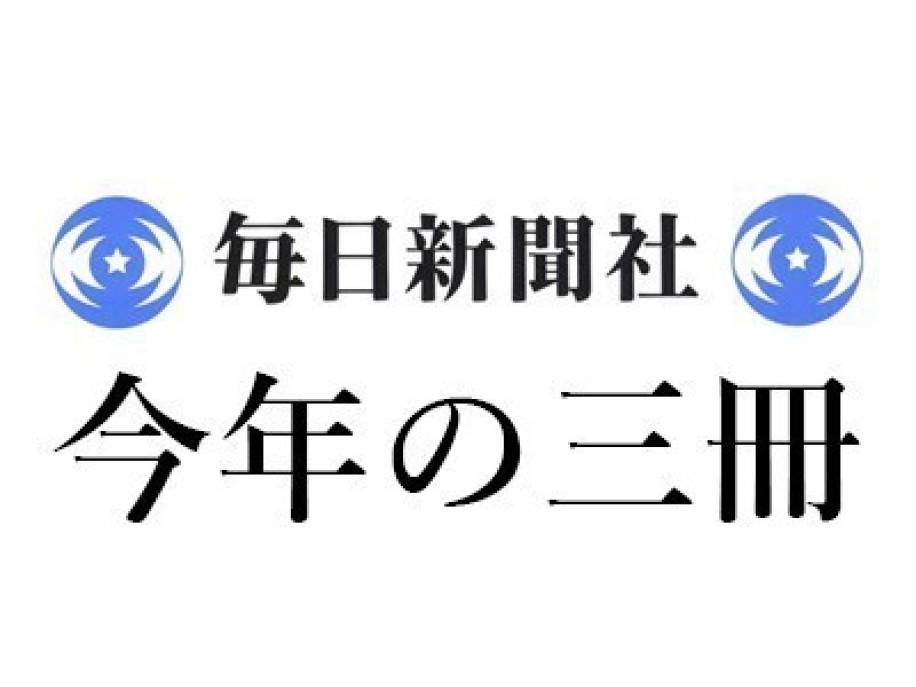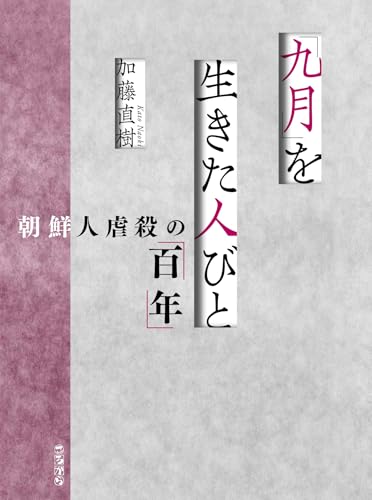書評
『オリーヴァ・デナーロ』(小学館)
「償い婚」にノー、その勇気と尊厳
1960年代、シチリア島の小さな村に住む少女、オリーヴァ・デナーロが主人公だ。「女は水差しだから、割った人のところにもらわれていくもの」
それがこの時代の常識だった。オリーヴァの姉は自分を強姦した男の元へ嫁ぎ、夫の暴力に遭い、妊娠した子を流産する。
小さな村のできごとは、なんでも筒抜けになってしまう。姉の夫のジェロが女という女に手を出していることも、町で有名な菓子店の息子がさかんにオリーヴァに色目を使うことも、オリーヴァが友だちのリリアーナに誘われてコミュニストの集会に行ってみたことも、オリーヴァに目の見えない男爵からの縁談が来たことも。
事件はオリーヴァの16歳の誕生日に起こった。夕方、用事を思い出した母と別れて家に帰ろうとしたオリーヴァは、大通りを歩いていたときに、何者かに力ずくで車にひっぱり込まれてしまう。そのまま連れ去られ、監禁された挙げ句に性被害を受ける――。
当時、イタリアには「刑法第544条」というものがあり、強姦の加害者が「償い」のために被害者と結婚した場合は、「罪は消滅する」とされた。酷い人権侵害だが、1981年に廃止されるまで存在したそうだ。
警察官は言う。
「ひとたび法廷に召集されたら、娘さんは聴衆の前で、起こったことを克明に話さなくてはならないんだ。相手方の弁護士は裁判官の前で言うだろう。娘さんも合意のうえだった、それどころか、以前から彼と親密な関係にあったのだ、と。そして、彼のしたことは暴行ではなく、深い愛情の表現だったと弁明する」
読んでいて胸に杭を打ち込まれるような思いがしたのは、これが60年前のイタリアの話だとばかりは思えなかったからだ。
21世紀の日本で、「被害者は抵抗しなかった」「合意があったと思っていた」と加害者が主張する場面は多く、この警察官と同じ言葉で受忍を説く声も消えない。水差しが割れたのは、水差しが悪いのだという非難もなくならない。被害を訴えることには、いまだに、とても高いハードルがある。
オリーヴァはノーを選ぶ。
「いいえ(ノー)。私はあの人とは結婚したくない」
彼女は男を告訴し、すべてを体験する。警察官の言葉も、村人たちの心無い陰口も。いわれなき自責にも苦しめられる。一方で、優秀な活動家や弁護士にも出会う。
この物語は実話をもとにしているのだそうだ。けれど、印象的なのは、「償い婚」にノーを突きつけて裁判で画期的な勝訴を得た最初の女性がモデルではないことだ。作家は、「最初の女性」以前にも裁判を起こした勇気ある女性がいたことを知り、それが必ずしも華々しい勝訴を得られてはいないことに注目して、この作品を書いたのだという。
小説は、少女オリーヴァの身に起こった事件を扱いながら、その繊細な心の揺らぎを、彼女の意志が変えていく周囲を、彼女の尊厳そのものを、丹念に描き出す。
勇気をもって立ち上がったのに正義が下されなかったという思いを抱いた者たち、立ち上がる前に声を封じられた者たち、オリーヴァの背後からは無数の聞かれなかった声が立ち上がってくる。
ALL REVIEWSをフォローする