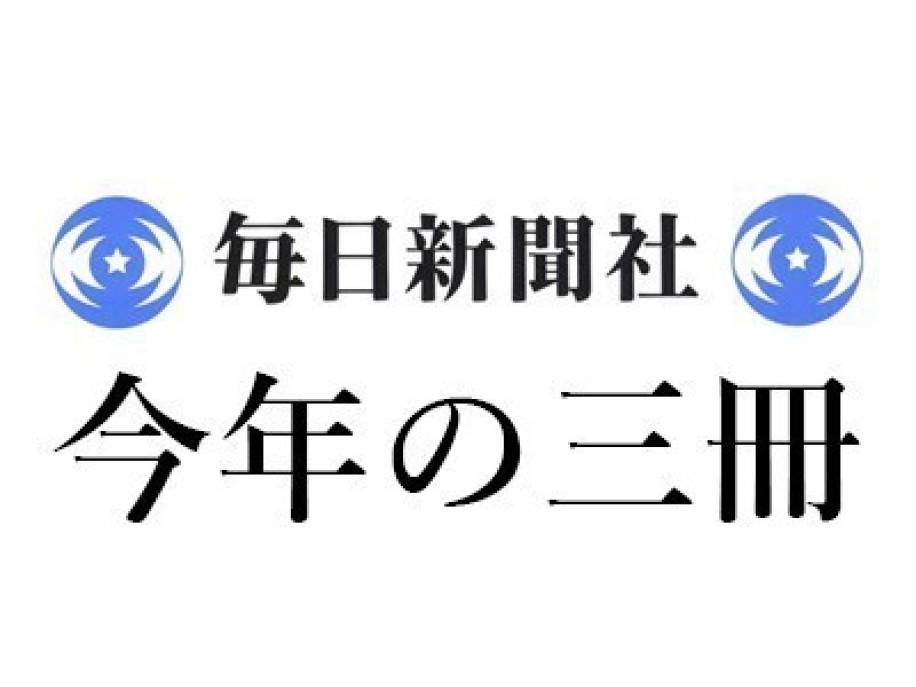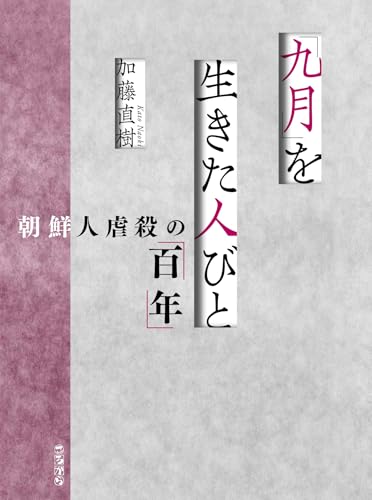書評
『戻ってきた娘』(小学館)
二人の母に捨てられた13歳の勇気
語り手の十三歳の女の子が、それまで会ったことのない「妹」に迎えられるシーンから小説は始まる。短いイントロのような、しかし強烈なそのシーンの次に彼女が向き合うのは、「わたしを産んだ女」である。乱暴に「荷物、置きな」と声をかけるその女は、語り手の生物学上の「母」らしいのだが、いったいどうしてそんなことになったのか。十三歳の語り手に、はっきりとした理由は誰からも説明されない。波乱含みの、緊張感あふれる出だしだ。作者はイタリア、アブルッツォ州の州都ラクイラで小児歯科医をしているという。五十代になるころから小説を書き始め、いくつもの文学賞を受賞したいまも、歯科医の仕事を続けているらしい。
描かれる少女たちの感情が心の襞に沿うように沁み入ってくるのは、作家の天性の資質ゆえではあろうけれど、日常的にその年代の子どもたちと接している、観察眼も生かされているかもしれない。
中流家庭の一人娘として大事に育てられた「わたし」は、ある日突然、実は我々はおまえの親ではないのだと、両親に告げられる。そして、これからいっしょに暮らすことになるのが本当の親兄弟だと言われ、極貧の家族のもとに送り還されてしまう。
子だくさんの家では、余計な食い扶持を増やしたやっかい者のように扱われ、隣近所の人々には「戻ってきた娘」と指をさされる。「わたし」は、産みの母と育ての母を持ちながら、心の絆を結べる母という存在を、決定的に失ってしまう。育ての母がなぜ彼女を手放したのかは、小説の終盤で明かされるが、どんな理由があろうと彼女は母に捨てられたのであり、しかも、それ以前に、産みの母からも捨てられていたことになる。
舞台になるのは、アブルッツォ州の山間の村。古い因習の残る、貧しい村だという。「わたし」が育った海辺の町からは五十キロほど離れ、町と村では階層が違う。
家の中で父や三人の兄たちは、殴り合うこともしょっちゅうで、母も妹を遠慮なく叩くし、妹は十歳なのにおねしょが治らない。いちばん下の弟は、世話をされなかったせいで発達が遅れている。
理不尽に苦しみながらも、「わたし」はその多感な季節を、ただ打ちのめされて過ごすわけではない。ほのかな恋めいた感情があり、小さな冒険があり、成長と、真実に立ち向かおうとする勇気がある。
語り手は「わたし」と書かれるだけで名が明かされないのだが、妹の名はアドリアーナという。たいていの読者は、この妹の魅力にやられてしまうに違いない。元気で、よく笑い、おねしょは治らないけれども頭がよく、機転が利いて、意外なことに姉思いだ。男ばかりの家で育ったアドリアーナにとって、「姉」の出現がどんなに嬉しかったかは、そうと直接は書かれなくても、彼女の行動から伝わって来る。自分とよく似た顔をした、しかし性格のまるで違う「妹」の存在が、傷ついた「わたし」にとって唯一の救いだったことも。
イタリアでベストセラーとなり、映画化も決まっているという小説。読後、忘れられない余韻を残し、どこか古典のような趣がある。
この小説の舞台となるのは一九七五年からの二年間だが、姉妹のその後を描いた続編もあるのだそうで、そちらもぜひ読んでみたい。
ALL REVIEWSをフォローする