書評
『航路』(早川書房)
心停止後に蘇生した人間の約六割が共通して訴える特異な体験、臨死体験(NDE)。暗いトンネルや光、三途の川、花畑、優しく出迎えてくれる死んだはずの家族のイメージ、というのが典型的なパターンで、なかには天使や神を見たり幽体離脱を体験したという報告をする患者も少なくない。
彼らが力説するように、本当に死後の世界は存在するのか。それとも科学者が主張するとおり、臨死体験は死にゆく脳の中で起きる生化学的な反応にすぎないのか。死んだ後に何が起きるのか知るためには死ななければならない。ところが、死んでしまえばその報告はできないというジレンマ! 解明不可能なこの謎に敢然と挑んだ傑作がコニー・ウィリスの『航路』なのだ。
舞台となるのはコロラド州の総合病院。認知心理学者のジョアンナは、医学的・科学的見地から臨死体験を分析するために、心停止の連絡があるたび患者のもとに駆けつけ、蘇生後の快復を待って話を聞いている。そのジョアンナと対立する立場にあるのがノンフィクション作家のマンドレイク。彼の書いた臨死体験に宗教的な意味を与える著作は、全世界で一千万部以上売れている。マンドレイクもまた第二作の取材のためにこの病院に滞在中なのだが、誘導尋問によって自説に都合のいい回答を引き出す彼の取材方法に、ジョアンナは激しく反発している。
そのジョアンナに研究の協力を依頼するのが神経内科医のリチャード。脳科学の立場から臨死体験を研究している彼は、臨死体験は死に直面した脳のサバイバル・メカニズムではないかと考えている。人体には無害な薬物ジテタミンが被験者の脳に臨死体験そっくりの幻覚を誘発することを発見したリチャードは、被験者に対する聞き取り調査をジョアンナに依頼したのだ。この仕組みを解明すれば、心停止した患者の蘇生率を高めることができるかもしれない。重度の心臓病で入退院を繰り返している少女メイジーを思い浮かべたジョアンナは、彼女を助けたいという思いもあってリチャードに協力することに。
ところが、被験同意者のほとんどが、マンドレイクの息のかかったインチキ臨死体験の信者であることが判明。そこでジョアンナは、自分が被験者になることを提案。一回目のセッションでは暗いトンネルを歩くだけだったジョアンナだが、回を重ねるうちにもっと複雑でリアルな体験を報告するようになる。白い服を着た見知らぬ男女が言葉を交わしている。そのディテールが明らかになっていくにつれ、彼女の心に確信が芽生える。わたしはこの場所を知っている。行ったことはないけれど、たしかに知っている――。
おっと、これ以上は何ひとつ明かすことができません。この後、第一部の最後に用意されている「!」と、第二部のラストに置かれた「!!」、そして全ての伏線が一気に本流に流れ込んでくる怒濤の展開の中、ついに臨死体験の謎が解き明かされる第三部。その驚きを半減させるようなほのめかしを少しでもしたなら、作者と訳者から袋叩きにあうこと必定。まったくもって書評家泣かせの逸品なのだ。この小説の数々の美点に触れたくても、ネタバレの怖れがあるために思うように取り上げることができないときてるんだから。
でも、その隔靴掻痒(かっかそうよう)を超えてでも紹介したい、これはそれほど素晴らしい物語なのだ。自分の命も顧みず他人の命を救うために尽力した勇気ある人々のエピソードがもたらす感動、死にまつわるたくさんのメタファーを駆使した深い洞察、巧妙な伏線が張り巡らされたスリリングなストーリー展開、時折挿入される温かな笑いを生むユーモラスなシーンや会話、映画にまつわる愉快な蘊蓄(うんちく)、そして3Dみたいに立体的なキャラクター造形。とりわけ、心臓病の少女メイジーが愛おしい。災害おたくにしてブラックユーモアの達人の彼女がもたらす笑いと、第三部に入ってからの活躍ぶり、そこから生じる落涙必至のエピソードといったら! 裏主人公といっても過言ではない一読忘れがたいキャラクターなのである。
まさに愉しみどころ満載、一気通読のロードコースター・ノヴェルなので、この長さがまるで気にならないはず。いや、むしろ「もう終わっちゃうの」、この長さが不満に思えてくるほどなのだ。あ、そうだ。愉しみどころといえば、各章の初めに紹介されている、たくさんの人たちの“最期の言葉”だけ拾って読むのもまた一興。ちなみにわたしのお気に入りは、ワイアット・アープの友人だった拳銃使いドク・ホリデイの臨終の一言「妙だな」。……え~っ、何が妙なのぉ? 知りた~い、でも、死にたくな~い。これもまたジレンマなんである。
【下巻】
【この書評が収録されている書籍】
彼らが力説するように、本当に死後の世界は存在するのか。それとも科学者が主張するとおり、臨死体験は死にゆく脳の中で起きる生化学的な反応にすぎないのか。死んだ後に何が起きるのか知るためには死ななければならない。ところが、死んでしまえばその報告はできないというジレンマ! 解明不可能なこの謎に敢然と挑んだ傑作がコニー・ウィリスの『航路』なのだ。
舞台となるのはコロラド州の総合病院。認知心理学者のジョアンナは、医学的・科学的見地から臨死体験を分析するために、心停止の連絡があるたび患者のもとに駆けつけ、蘇生後の快復を待って話を聞いている。そのジョアンナと対立する立場にあるのがノンフィクション作家のマンドレイク。彼の書いた臨死体験に宗教的な意味を与える著作は、全世界で一千万部以上売れている。マンドレイクもまた第二作の取材のためにこの病院に滞在中なのだが、誘導尋問によって自説に都合のいい回答を引き出す彼の取材方法に、ジョアンナは激しく反発している。
そのジョアンナに研究の協力を依頼するのが神経内科医のリチャード。脳科学の立場から臨死体験を研究している彼は、臨死体験は死に直面した脳のサバイバル・メカニズムではないかと考えている。人体には無害な薬物ジテタミンが被験者の脳に臨死体験そっくりの幻覚を誘発することを発見したリチャードは、被験者に対する聞き取り調査をジョアンナに依頼したのだ。この仕組みを解明すれば、心停止した患者の蘇生率を高めることができるかもしれない。重度の心臓病で入退院を繰り返している少女メイジーを思い浮かべたジョアンナは、彼女を助けたいという思いもあってリチャードに協力することに。
ところが、被験同意者のほとんどが、マンドレイクの息のかかったインチキ臨死体験の信者であることが判明。そこでジョアンナは、自分が被験者になることを提案。一回目のセッションでは暗いトンネルを歩くだけだったジョアンナだが、回を重ねるうちにもっと複雑でリアルな体験を報告するようになる。白い服を着た見知らぬ男女が言葉を交わしている。そのディテールが明らかになっていくにつれ、彼女の心に確信が芽生える。わたしはこの場所を知っている。行ったことはないけれど、たしかに知っている――。
おっと、これ以上は何ひとつ明かすことができません。この後、第一部の最後に用意されている「!」と、第二部のラストに置かれた「!!」、そして全ての伏線が一気に本流に流れ込んでくる怒濤の展開の中、ついに臨死体験の謎が解き明かされる第三部。その驚きを半減させるようなほのめかしを少しでもしたなら、作者と訳者から袋叩きにあうこと必定。まったくもって書評家泣かせの逸品なのだ。この小説の数々の美点に触れたくても、ネタバレの怖れがあるために思うように取り上げることができないときてるんだから。
でも、その隔靴掻痒(かっかそうよう)を超えてでも紹介したい、これはそれほど素晴らしい物語なのだ。自分の命も顧みず他人の命を救うために尽力した勇気ある人々のエピソードがもたらす感動、死にまつわるたくさんのメタファーを駆使した深い洞察、巧妙な伏線が張り巡らされたスリリングなストーリー展開、時折挿入される温かな笑いを生むユーモラスなシーンや会話、映画にまつわる愉快な蘊蓄(うんちく)、そして3Dみたいに立体的なキャラクター造形。とりわけ、心臓病の少女メイジーが愛おしい。災害おたくにしてブラックユーモアの達人の彼女がもたらす笑いと、第三部に入ってからの活躍ぶり、そこから生じる落涙必至のエピソードといったら! 裏主人公といっても過言ではない一読忘れがたいキャラクターなのである。
まさに愉しみどころ満載、一気通読のロードコースター・ノヴェルなので、この長さがまるで気にならないはず。いや、むしろ「もう終わっちゃうの」、この長さが不満に思えてくるほどなのだ。あ、そうだ。愉しみどころといえば、各章の初めに紹介されている、たくさんの人たちの“最期の言葉”だけ拾って読むのもまた一興。ちなみにわたしのお気に入りは、ワイアット・アープの友人だった拳銃使いドク・ホリデイの臨終の一言「妙だな」。……え~っ、何が妙なのぉ? 知りた~い、でも、死にたくな~い。これもまたジレンマなんである。
【下巻】
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
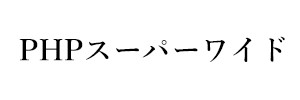
PHPスーパーワイド(終刊) PHPスーパーワイド
ALL REVIEWSをフォローする



































