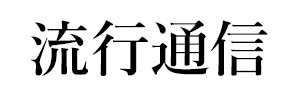書評
『音楽のレッスン』(河出書房新社)
音楽がテーマだったり、大切な小道具として扱われている小説は多々ある。たとえば、ルイス・シャイナー『グリンプス』(創元SF文庫)。人生に行き詰まった中年男が、六十年代に過ごした挫折の日々を思い返すうちに、当時様々な理由から未完に終わったジミ・ヘンドリックスやビーチ・ボーイズなどの楽曲の完成版を作る特異な能力に目覚め、幻のアルバムの音作りのために六十年代にタイムトリップする――というロックファンなら随喜の涙を流す傑作SFなのだ。
でも、音楽を扱った優れた小説は数あれど、音楽そのものを描ききっている小説は滅多にない。パスカル・キニャールの作品はその希有な例だ。自身、チェロをたしなむこの作家が書く作品のほとんどは、直接手に触れることができない音、そのとらえ難さと美しさのイメージを作品世界の通奏低音として響かせている。
それを綴る文章の明晰さ、美しさがまた格別。楽譜に記されたただの記号が、歌われることで、奏でられることで、たえなる調べと化すかのようにキニャールは音楽を文字化するのだ。映画化されたことでポピュラーになった『めぐり逢う朝』(早川書房)、自分の分身であることを匂わせるバロック音楽家を語り手にした『ヴュルテンベルクのサロン』(早川書房)等々、キニャールの作品を読むたびに、わたしはピアニストのポゴレリチやヴァイオリニストのクレーメルといった、クラシック奏者たちの名演を思い返さずにはいられない。
『音楽のレッスン』はそんな作品群の中でも、とびきり難解で、とびきり美しい一冊だ。
声変わりというボーイソプラノと幼年期の喪失に関する考察に始まり、十七世紀に実在したヴィオール奏者マラン・マレの生涯から古代ギリシャの哲人アリストテレス、古代中国の伝説的な音楽の名人へとうつろう主題。それら断章の合間に、‟喪失”という全体テーマが奏でられ、生(性)と死、音楽と言語についての思索がアクセントをつける。史実でもなければフィクションでもない、とはいえエッセーとも言い切れない。あらゆるジャンルからはみ出してしまう、情熱と思惟(しい)を融合させた、とんでもなくカッコイイ作品。ゆっくりじっくり読んでほしい一冊だ。
【この書評が収録されている書籍】
でも、音楽を扱った優れた小説は数あれど、音楽そのものを描ききっている小説は滅多にない。パスカル・キニャールの作品はその希有な例だ。自身、チェロをたしなむこの作家が書く作品のほとんどは、直接手に触れることができない音、そのとらえ難さと美しさのイメージを作品世界の通奏低音として響かせている。
それを綴る文章の明晰さ、美しさがまた格別。楽譜に記されたただの記号が、歌われることで、奏でられることで、たえなる調べと化すかのようにキニャールは音楽を文字化するのだ。映画化されたことでポピュラーになった『めぐり逢う朝』(早川書房)、自分の分身であることを匂わせるバロック音楽家を語り手にした『ヴュルテンベルクのサロン』(早川書房)等々、キニャールの作品を読むたびに、わたしはピアニストのポゴレリチやヴァイオリニストのクレーメルといった、クラシック奏者たちの名演を思い返さずにはいられない。
『音楽のレッスン』はそんな作品群の中でも、とびきり難解で、とびきり美しい一冊だ。
声変わりというボーイソプラノと幼年期の喪失に関する考察に始まり、十七世紀に実在したヴィオール奏者マラン・マレの生涯から古代ギリシャの哲人アリストテレス、古代中国の伝説的な音楽の名人へとうつろう主題。それら断章の合間に、‟喪失”という全体テーマが奏でられ、生(性)と死、音楽と言語についての思索がアクセントをつける。史実でもなければフィクションでもない、とはいえエッセーとも言い切れない。あらゆるジャンルからはみ出してしまう、情熱と思惟(しい)を融合させた、とんでもなくカッコイイ作品。ゆっくりじっくり読んでほしい一冊だ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする