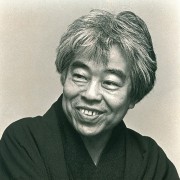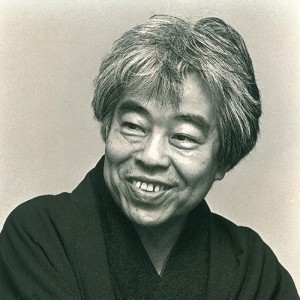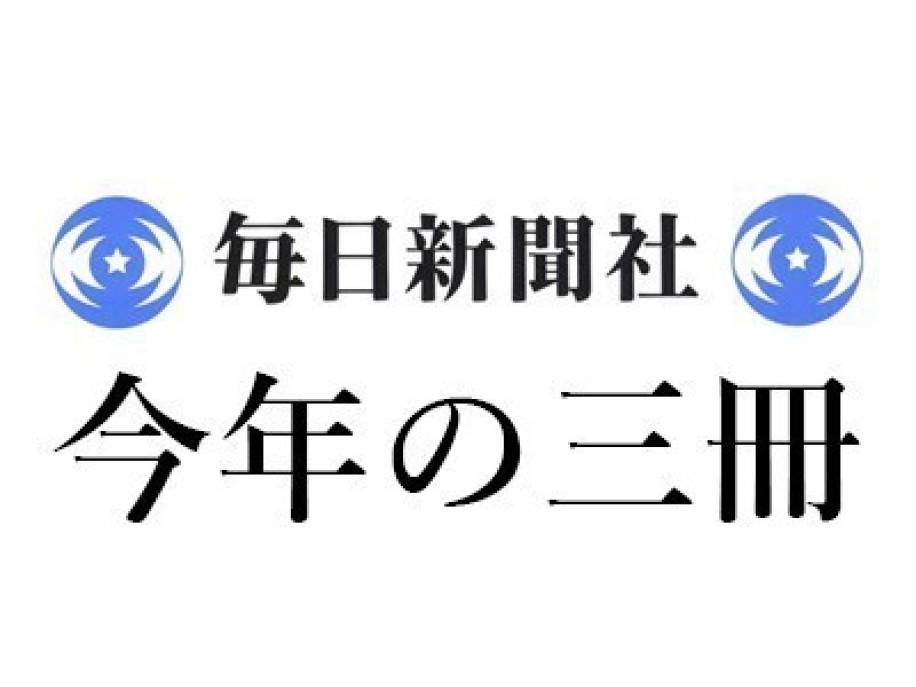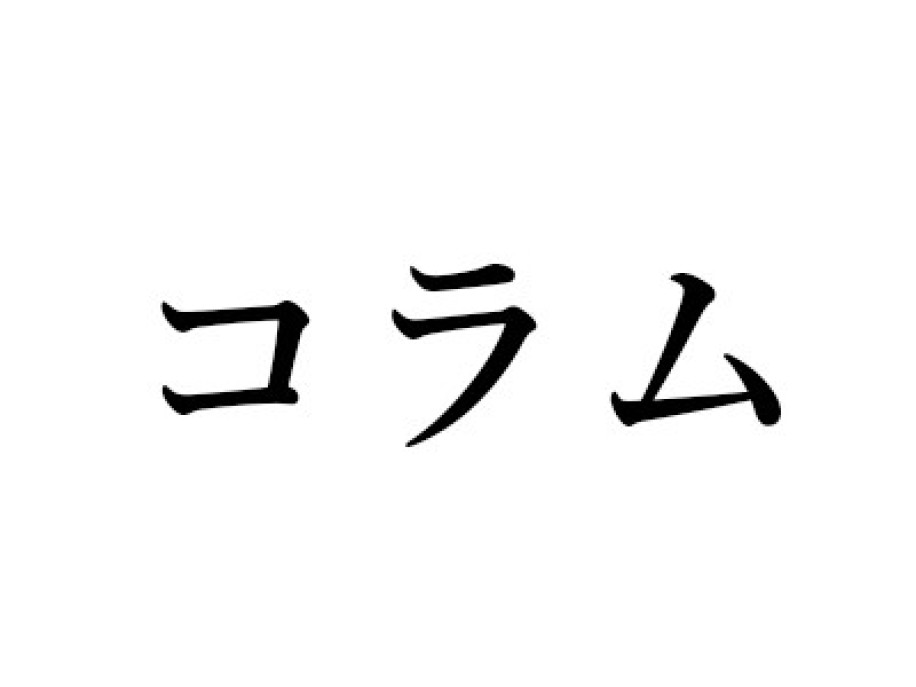書評
『未踏の時代』(早川書房)
SFにすべて捧げたパイオニア
福島正実は文字どおりSFのオニだった。ベムと評した人もいる。「SFマガジン」の初代編集長として、SFにたいする誤解や偏見のつよかった時代に、敢然としてたたかっただけでなく、一人何役かの仕事をはたした人である。ジュヴナイルSFをはじめとして、多くの創作や翻訳、そして評論の筆をとり、死にいたるまでの日々を、すべてSFにささげたパイオニアだった。その彼が四十七歳の若さで亡くなったのは昨年四月のことであり、病床で筆をとりつづけた回想「未踏の時代」は、一九六七年のくだりで未完に終わった(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1977年)。彼は挫折した第一回国際SF作家会議の経過を述べ、それから四年後に、万博をきっかけとして国際SF作家シンポジウムが実現したことにふれ、「だが、それすら、すでに数年前の――古びた過去のこととなった」と結んでいる。
たしかに彼が「SFマガジン」の創世紀に孤軍奮闘したたたかいの姿は、むかしのこととなった。しかしその歴史があったからこそ、今日のSFの隆盛も可能だったわけであり、あの当時の福島正実の肩ひじ張ったやや狷介(けんかい)ともみえる態度は、そのけんめいなたたかいぶりのあらわれでもあったのだ。そのことがなつかしく思い出される。
「SFマガジン」が市場にあらわれたのは一九五九年十一月、月号の表示は翌年二月号であった。それまでSFの企画はいずれも不調であり、SF雑誌の創刊にたいしては悲観的だった彼は、その雑誌をともかくも成功させるためには、SFファンだけを読者対象としてあてにしてはならないと考えたという。
だが、それはおそろしく孤独な作業であり、すべてをゼロからはじめなければならない状態だった。彼は翻訳家たちの関心をSFにあつめるために、熱っぽくその魅力について説明し、海外のSFの紹介に力を入れると同時に、日本のSFを背負って立つ新しい書き手の発掘と養成にあたった。現在のSF界の中核をなしている作家たちのほとんどが、二度にわたるSFコンテストによって登場したことを思えば、彼の直接間接の影響は無視できない。
それだけに彼は自己の信念に忠実であり、頑固なまでにその考えをおしとおした。荒正人との間でかわされた論争も、「宇宙塵」の主宰者である柴野拓美らの考えかたにたいする反論も、その必然のあらわれだった。
SFファンを広く組織することにより、SF全体の向上をはかろうとする「宇宙塵」の方向にたいして、福島はSFプロの優位を主張し、SF作家クラブの設立に漕ぎつけるが、そういった一連の経過を、彼自身の歩みに即してたどっている。表題を「未踏の時代」と名づけた気負いも、またこうした彼の姿勢を物語るようだ。
ALL REVIEWSをフォローする