書評
『志ん朝の落語〈1〉男と女』(筑摩書房)
二〇〇一年十月一日。古今亭志ん朝さんが六十三歳でこの世を去った。それから二年、志ん朝さんの名演を一字一句ゆるがせにせずに記録した本が「ちくま文庫」版で次々と出版されている、『志ん朝の落語』と題された全六巻のシリーズで、九月から来年二月まで毎月一冊ずつの刊行だ(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2003年)。各巻には十二席前後の噺が収録されている。
編集・解説にあたったのが京須偕充(きょうすともみつ)さんというのが、まず、うれしい。現在市販されている志ん朝さんの高座の録音(ソニー版)はすべて、京須さんがプロデューサーとして手がけたもの。志ん朝さんが自分の芸をのこすにあたっては最も信頼を置いていた人だと思うから。
読み始めてすぐに、やっぱり京須さんでよかったと思う。志ん朝さんの、いや、江戸下町言葉の口調や発声法をあの手この手を使って、ギリギリまでリアルに再現しているからだ。例えば、十八番の「文七元結(ぶんしちもっとい)」で見るなら、「ああ寒(さぶ)いッ」「本当(んとう)にもう」とルビをつけたり、「こんな汚ェところイよくおいでくださいました」とか、「若えンだから、先は長ェや」とカタカナで表わしたり。たちまち志ん朝さんの高座が目に浮かぶ。幻の声が聴こえてくる。
解説も、濃い。とりわけ心を打たれたのは、時代遅れといえぱ時代遅れの話「甲府(こうふ)い」についての解説(第二巻)だ。
京須さんは志ん朝さんがこの噺の中で豆腐屋に「味噌汁の実ならば豆腐を塞の目に、清汁(すましじる)ならば削ぎに」と言わせ、さりげなく食文化本来の形を述べているところに注目し、「何もかもが無造作無原則に乱れていく傾向を憂いながら、表立って口にしない。志ん朝さんはそういう人だった」「そんな志ん朝さんだから、この古風な噺に小細工を加え、余分な笑いをとることはなかった。穏やかな噺は、真っ直ぐまともにやる。それでこそ落語は、穏やかならざる不安の時代に、一服の清涼剤となるのではないだろうか」――と書いている。
こういうところにこそ志ん朝さんの聡明さと大きさがあったのだ、と改めて思った。
【この書評が収録されている書籍】
編集・解説にあたったのが京須偕充(きょうすともみつ)さんというのが、まず、うれしい。現在市販されている志ん朝さんの高座の録音(ソニー版)はすべて、京須さんがプロデューサーとして手がけたもの。志ん朝さんが自分の芸をのこすにあたっては最も信頼を置いていた人だと思うから。
読み始めてすぐに、やっぱり京須さんでよかったと思う。志ん朝さんの、いや、江戸下町言葉の口調や発声法をあの手この手を使って、ギリギリまでリアルに再現しているからだ。例えば、十八番の「文七元結(ぶんしちもっとい)」で見るなら、「ああ寒(さぶ)いッ」「本当(んとう)にもう」とルビをつけたり、「こんな汚ェところイよくおいでくださいました」とか、「若えンだから、先は長ェや」とカタカナで表わしたり。たちまち志ん朝さんの高座が目に浮かぶ。幻の声が聴こえてくる。
解説も、濃い。とりわけ心を打たれたのは、時代遅れといえぱ時代遅れの話「甲府(こうふ)い」についての解説(第二巻)だ。
京須さんは志ん朝さんがこの噺の中で豆腐屋に「味噌汁の実ならば豆腐を塞の目に、清汁(すましじる)ならば削ぎに」と言わせ、さりげなく食文化本来の形を述べているところに注目し、「何もかもが無造作無原則に乱れていく傾向を憂いながら、表立って口にしない。志ん朝さんはそういう人だった」「そんな志ん朝さんだから、この古風な噺に小細工を加え、余分な笑いをとることはなかった。穏やかな噺は、真っ直ぐまともにやる。それでこそ落語は、穏やかならざる不安の時代に、一服の清涼剤となるのではないだろうか」――と書いている。
こういうところにこそ志ん朝さんの聡明さと大きさがあったのだ、と改めて思った。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
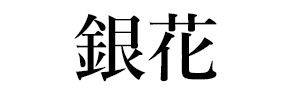
銀花(終刊) 2003年12月
ALL REVIEWSをフォローする





































