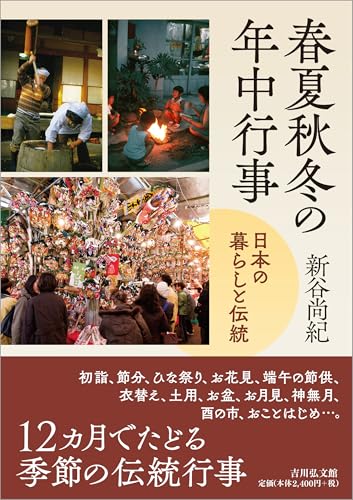内容紹介
『アメリカ 流転の1950ー2010s 映画から読む超大国の欲望』(祥伝社)
アメリカとは、何者なのか?私たちにとって、いかなる存在なのか?
戦後50年代から2 0 1 0年代まで、超大国アメリカの変化を、映画のスクリーンから、あるいは時代を彩った流行、事件などから、大衆の欲望の歴史として読み解き、時代を呼吸した人々の息づかいを感じ取ることを試みる、NHK『世界サブカルチャー史 欲望の系譜』。番組発の2冊目となる本書では、まず第1部として戦後50年代から60年代まで、第2部では70年代から90年代まで、そして第3部で2000年代から10年代までの3部構成で、時代の輪郭を描き出す。
ポップ、サブ、社会の空気の変遷の物語、人々の心の変化を促すものの正体を捕まえようとする試論だ。本稿では、本書の第1章から一部抜粋して、お届けする。
いざ、想像力の旅へ。
ヘプバーン演じる、とある国の王女は、ローマ滞在中に窮屈な王室の生活に我慢がならなくなり、夜中に城を抜け出す。そこで出会ったグレゴリー・ペック扮するアメリカ人記者との淡いロマンスを描いた作品だ。
そのオープニングクレジットには、「この作品は全てイタリアで撮影された」という一文がある。今でこそロケは当たり前だが、この時代はスタジオでの撮影が常識だった。『ローマの休日』は、ハリウッド史上初の全編海外ロケで制作された映画だった。
華麗なる、海外ロケ。だが、決して資金が潤沢にあったなどの理由ではない。その背景には、戦後のアメリカに差した暗い影があった。
『ローマの休日』公開6年前の1947年3月、トルーマン大統領は共産主義封じ込め政策「トルーマン・ドクトリン」を発表する。戦後、経済的、軍事的に台頭したソ連の存在はもはや無視できないものとなっていた。冷戦時代の幕開けである。東ヨーロッパの国々も次々と社会主義化していく中、共産主義の脅威がアメリカを脅かし始めていた。
そして、その脅威は国内の共産主義者の摘発、いわゆる「赤狩り」を招く。
その急先鋒となったのが非米活動委員会だ。彼らがターゲットとしたのは、国民に強い影響力を持つハリウッドだった。ワシントンで開かれた公聴会では、脚本家ジョン・ハワードら、多くのスターや映画関係者たちが次々に召喚された。
召喚される人物は「密告」で決められていったと、政治とサブカルチャーの関係性を研究、ボストン大学教授にして歴史家のブルース・シュルマンは、次のように述べる。
「非米活動委員会の公聴会は一種の道徳劇のようなもので、元共産主義者が過去の失敗を認め誤りから学び、いかに愛国的なアメリカ人になったかを語るという形で行なわれました。そしてその忠誠心を証明するため、かつての共産主義者の仲間の名前を言わなければならないのです。多くのハリウッドの著名人がそうした密告を行ないました」
例えば、ウォルト・ディズニーは公聴会で次のように証言している。
「我が社の労働組合のソラール氏は共産主義者だと思います。彼は共産党から資金援助を受けストライキを行なったのです」
この公聴会に召喚された一人に、当時、売れっ子脚本家だったダルトン・トランボがいた。『ジョニーは戦場へ行った』などの小説作品でも知られる。
彼は戦時中に共産党に所属し、政治的な信条を公にすることなく仕事をしていた。第二次大戦では、ソ連はアメリカと共にファシズムと戦う連合国だ。アメリカ国内にも共産主義の理想に共感するものは、決して少なくなかった。
「あなたは共産党員ですか? かつて共産党員だったことはありますか?」
こう問われたトランボは次のように言った。
「あなたはいかなる理由でその質問をしているのですか?」
質問を質問で返し証言を拒んだトランボは、ハリウッドを追放されてしまう。歴史に残る名作『ローマの休日』は、実はトランボが正体を隠し、友人の脚本家イアン・ハンターの名を借りて40年代末に書き上げた作品だった。
1949年、ソ連が核実験に成功。アメリカによる核の占有は崩れ去り、「偉大なるアメリカ」の自画像も大きく揺らいだ。同じ年には、共産党政権による中華人民共和国も成立した。翌1950年、朝鮮戦争が勃発。自由主義陣営と共産主義陣営の直接対決がついに始まる。
そんな中、トランボの名を伏せたまま『ローマの休日』の制作は決定された。監督を務めることになったのはウイリアム・ワイラー。彼もまた、赤狩りと闘う人物だった。
当時のハリウッドは、共産主義と関わりのある者のブラックリストを作成し、「反共」の姿勢を前面に押し出していた。閉塞感に覆われた現場に嫌気がさしたワイラーは、赤狩りに抗議すべく、有志たちとリベラルな映画人組織を立ち上げていた。
当時、ワイラーはラジオ番組でこう述べている。
「非米活動委員会は人々に脅威をもたらし、意見を抑え込んでいます。ハリウッドに恐怖を生み、表現を麻痺させているのです」
ワイラーは赤狩りへの抵抗として、共同プロデューサーのレスター・コーニッグをはじめ、ブラックリストに載りハリウッドを追放されていたスタッフたちを起用した。そして彼らを守るために、映画会社の目が届きにくいイタリアの地で撮影することにしたのだった。
さらにワイラーは、トランボの脚本になかった場面を現地で付け加える。真実の口に手を入れるという有名なシーンだ。
「〝真実の口〞だ。噓つきが手を入れると咬まれるという言い伝えがある」
「怖いのね」
もちろん石像が動くはずはない。お互いに噓をつき、正体を隠した2人の物語。ワイラーが描き出したのは、疑心暗鬼を超えた信頼の形なのかもしれない。
シュルマンはこの映画の意義を次のように強調する。
「『ローマの休日』は素晴らしいロマンティックコメディの映画であると同時に、共産主義者に対する恐怖と猜疑心が、いかに1950年代の空気を形作っていたかを示す作品なのです。あの時代のハリウッドではブラックリストが作成されていました。トランボもそのリストに載せられていた『ハリウッド・テン』の一人です。ただ、この作品は例外的にそのリストに載せられていた人たちによって制作され、成功を収めたのです」
噓と猜疑心。誰もが本心を隠して生きる重苦しい空気が、アメリカ社会を覆っていた。
「ソ連が核装備を行ない、共産主義の脅威は現実にそこにある問題となっていました。戦時中の同盟国は、いまや強大な敵となりました。そして、それに対する過剰反応や脅威の誇張は、右翼にとって有益だったのです。
右派や極右の人々は、自分たちの政治的目的を達成する手段として、共産主義への恐怖を煽(あお)りました。特にマッカーシーはひどい人間で、ひねくれたデマゴーグでした。
彼は人々の陰謀論への弱さを助長しました。
現実世界の複雑さは、時に人々をいらだたせ、困惑させます。その時に多くの人が白か黒かをはっきりさせ、大きな敵を持ちたいという願望を持ってしまう。彼はそれを助長したのです。悪魔のように巨大な敵がいることで、全てが単純化されるからです。
アメリカ人は基本的に単純であることを好みますから、誰を憎めばいいのか? という問いに答えを与えてくれる人を望んだのです。
アメリカ人が様々なヒステリー、特に外国人に関するヒステリーに弱いということは昔から見られます。1800年代における敵はフランス人やカトリック信者で、その後はユダヤ系やドイツ人になり、関わっている戦争によって対象が変化していきました。1840年代から50年代にかけてアイルランドから大きな移民の流入があった際は、彼らが嫌悪の対象になりました。そういう歴史があります。
そして、1947年ぐらいからソ連が崩壊する1991年までは、私たちの恐怖や嫌悪の矛先は一つに集中していました。これは科学の時代にあって宗教的とも言えるほど強い感情でした」
いつも「外」に敵を欲する、アメリカの人々の心の内。開放的な自由の国・アメリカのもう一つの顔が浮かび上がる。
[書き手]丸山俊一
戦後50年代から2 0 1 0年代まで、超大国アメリカの変化を、映画のスクリーンから、あるいは時代を彩った流行、事件などから、大衆の欲望の歴史として読み解き、時代を呼吸した人々の息づかいを感じ取ることを試みる、NHK『世界サブカルチャー史 欲望の系譜』。番組発の2冊目となる本書では、まず第1部として戦後50年代から60年代まで、第2部では70年代から90年代まで、そして第3部で2000年代から10年代までの3部構成で、時代の輪郭を描き出す。
ポップ、サブ、社会の空気の変遷の物語、人々の心の変化を促すものの正体を捕まえようとする試論だ。本稿では、本書の第1章から一部抜粋して、お届けする。
いざ、想像力の旅へ。
戦後アメリカに差した暗い影―ブルース・シュルマンの証言
1950年代、日本の女性たちの間であるヘアスタイルが大流行した。軽快なショートカットの名は「ヘプバーンスタイル」。女優オードリー・ヘプバーンのスタイルを真似たものだ。『ローマの休日』(1953、日本公開は1954)のヒットにより、この流行はあっという間に広まった。ヘプバーン演じる、とある国の王女は、ローマ滞在中に窮屈な王室の生活に我慢がならなくなり、夜中に城を抜け出す。そこで出会ったグレゴリー・ペック扮するアメリカ人記者との淡いロマンスを描いた作品だ。
そのオープニングクレジットには、「この作品は全てイタリアで撮影された」という一文がある。今でこそロケは当たり前だが、この時代はスタジオでの撮影が常識だった。『ローマの休日』は、ハリウッド史上初の全編海外ロケで制作された映画だった。
華麗なる、海外ロケ。だが、決して資金が潤沢にあったなどの理由ではない。その背景には、戦後のアメリカに差した暗い影があった。
『ローマの休日』公開6年前の1947年3月、トルーマン大統領は共産主義封じ込め政策「トルーマン・ドクトリン」を発表する。戦後、経済的、軍事的に台頭したソ連の存在はもはや無視できないものとなっていた。冷戦時代の幕開けである。東ヨーロッパの国々も次々と社会主義化していく中、共産主義の脅威がアメリカを脅かし始めていた。
そして、その脅威は国内の共産主義者の摘発、いわゆる「赤狩り」を招く。
その急先鋒となったのが非米活動委員会だ。彼らがターゲットとしたのは、国民に強い影響力を持つハリウッドだった。ワシントンで開かれた公聴会では、脚本家ジョン・ハワードら、多くのスターや映画関係者たちが次々に召喚された。
召喚される人物は「密告」で決められていったと、政治とサブカルチャーの関係性を研究、ボストン大学教授にして歴史家のブルース・シュルマンは、次のように述べる。
「非米活動委員会の公聴会は一種の道徳劇のようなもので、元共産主義者が過去の失敗を認め誤りから学び、いかに愛国的なアメリカ人になったかを語るという形で行なわれました。そしてその忠誠心を証明するため、かつての共産主義者の仲間の名前を言わなければならないのです。多くのハリウッドの著名人がそうした密告を行ないました」
例えば、ウォルト・ディズニーは公聴会で次のように証言している。
「我が社の労働組合のソラール氏は共産主義者だと思います。彼は共産党から資金援助を受けストライキを行なったのです」
この公聴会に召喚された一人に、当時、売れっ子脚本家だったダルトン・トランボがいた。『ジョニーは戦場へ行った』などの小説作品でも知られる。
彼は戦時中に共産党に所属し、政治的な信条を公にすることなく仕事をしていた。第二次大戦では、ソ連はアメリカと共にファシズムと戦う連合国だ。アメリカ国内にも共産主義の理想に共感するものは、決して少なくなかった。
「あなたは共産党員ですか? かつて共産党員だったことはありますか?」
こう問われたトランボは次のように言った。
「あなたはいかなる理由でその質問をしているのですか?」
質問を質問で返し証言を拒んだトランボは、ハリウッドを追放されてしまう。歴史に残る名作『ローマの休日』は、実はトランボが正体を隠し、友人の脚本家イアン・ハンターの名を借りて40年代末に書き上げた作品だった。
映画史に残る名シーン“真実の口”のもう一つの真実
その頃、東西冷戦の緊張は日増しに高まっていた。1949年、ソ連が核実験に成功。アメリカによる核の占有は崩れ去り、「偉大なるアメリカ」の自画像も大きく揺らいだ。同じ年には、共産党政権による中華人民共和国も成立した。翌1950年、朝鮮戦争が勃発。自由主義陣営と共産主義陣営の直接対決がついに始まる。
そんな中、トランボの名を伏せたまま『ローマの休日』の制作は決定された。監督を務めることになったのはウイリアム・ワイラー。彼もまた、赤狩りと闘う人物だった。
当時のハリウッドは、共産主義と関わりのある者のブラックリストを作成し、「反共」の姿勢を前面に押し出していた。閉塞感に覆われた現場に嫌気がさしたワイラーは、赤狩りに抗議すべく、有志たちとリベラルな映画人組織を立ち上げていた。
当時、ワイラーはラジオ番組でこう述べている。
「非米活動委員会は人々に脅威をもたらし、意見を抑え込んでいます。ハリウッドに恐怖を生み、表現を麻痺させているのです」
ワイラーは赤狩りへの抵抗として、共同プロデューサーのレスター・コーニッグをはじめ、ブラックリストに載りハリウッドを追放されていたスタッフたちを起用した。そして彼らを守るために、映画会社の目が届きにくいイタリアの地で撮影することにしたのだった。
さらにワイラーは、トランボの脚本になかった場面を現地で付け加える。真実の口に手を入れるという有名なシーンだ。
「〝真実の口〞だ。噓つきが手を入れると咬まれるという言い伝えがある」
「怖いのね」
もちろん石像が動くはずはない。お互いに噓をつき、正体を隠した2人の物語。ワイラーが描き出したのは、疑心暗鬼を超えた信頼の形なのかもしれない。
シュルマンはこの映画の意義を次のように強調する。
「『ローマの休日』は素晴らしいロマンティックコメディの映画であると同時に、共産主義者に対する恐怖と猜疑心が、いかに1950年代の空気を形作っていたかを示す作品なのです。あの時代のハリウッドではブラックリストが作成されていました。トランボもそのリストに載せられていた『ハリウッド・テン』の一人です。ただ、この作品は例外的にそのリストに載せられていた人たちによって制作され、成功を収めたのです」
噓と猜疑心。誰もが本心を隠して生きる重苦しい空気が、アメリカ社会を覆っていた。
共産主義への恐怖を煽ったのは誰か―カート・アンダーセンの証言
洒脱で風刺の効いた語り口で知られる、「ニューヨーク・マガジン」元編集長で作家のカート・アンダーセンは語る。「ソ連が核装備を行ない、共産主義の脅威は現実にそこにある問題となっていました。戦時中の同盟国は、いまや強大な敵となりました。そして、それに対する過剰反応や脅威の誇張は、右翼にとって有益だったのです。
右派や極右の人々は、自分たちの政治的目的を達成する手段として、共産主義への恐怖を煽(あお)りました。特にマッカーシーはひどい人間で、ひねくれたデマゴーグでした。
彼は人々の陰謀論への弱さを助長しました。
現実世界の複雑さは、時に人々をいらだたせ、困惑させます。その時に多くの人が白か黒かをはっきりさせ、大きな敵を持ちたいという願望を持ってしまう。彼はそれを助長したのです。悪魔のように巨大な敵がいることで、全てが単純化されるからです。
アメリカ人は基本的に単純であることを好みますから、誰を憎めばいいのか? という問いに答えを与えてくれる人を望んだのです。
アメリカ人が様々なヒステリー、特に外国人に関するヒステリーに弱いということは昔から見られます。1800年代における敵はフランス人やカトリック信者で、その後はユダヤ系やドイツ人になり、関わっている戦争によって対象が変化していきました。1840年代から50年代にかけてアイルランドから大きな移民の流入があった際は、彼らが嫌悪の対象になりました。そういう歴史があります。
そして、1947年ぐらいからソ連が崩壊する1991年までは、私たちの恐怖や嫌悪の矛先は一つに集中していました。これは科学の時代にあって宗教的とも言えるほど強い感情でした」
いつも「外」に敵を欲する、アメリカの人々の心の内。開放的な自由の国・アメリカのもう一つの顔が浮かび上がる。
[書き手]丸山俊一
ALL REVIEWSをフォローする