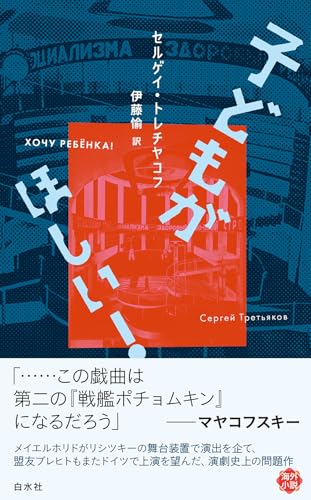書評
『首相が撃たれた日に』(河出書房新社)
「良識の限界」新文学誕生の予感
ウズィ・ヴァイルは一九六四年生まれのイスラエルの作家。ポストモダン世代の人気作家という。本書は短編や、コラムなどから一九編の作品を選んだ日本版オリジナルの作品集である。いずれも現代イスラエルの重苦しい社会情勢を背景にしながら、それを突き抜けてしまうようなユーモアとアイロニーがある。表題作の「首相が撃たれた日に」は、兵役を終えても社会に行き場が見つからない若者の「ぼく」を語り手とする。彼が泊まる場所を探していたちょうどその日、首相が撃たれるという大事件が起こった。イスラエルではこの小説の書かれた四年後の一九九五年に、銃撃によるラビン首相暗殺事件が起きた。予言的な作品と言われるゆえんである。しかし小説の「ぼく」は「無関心だった」とあっさり言い切る。「どっちにしても、この国じゃ、撃つか、政治の話をするかで、ぼくはそのどっちにも関心がない」というのだ。
宗教に対する主人公の態度もなげやりのように見える。「ぼくは神と話そうとしたが、神は応えてくれなかった。だから、すべていいようにやってくれ、あんたを信じているからな、何があっても、ぼくはあんたの味方なんだから、と言うにとどめた」
大きな社会的事件よりも、宗教よりも、その日をどう生きるかという私的な問題のほうが大事だという、著者の姿勢が鮮やかに出ている。「ぼく」が転がり込んだ建物には、自分よりはるかに若い娘に狂ったように老いらくの恋をして、夜な夜な一人で泣いている老コミュニストの忘れがたい姿も出てくるが、破れた革命の理想よりも、報われない恋の苦しみのほうが切実な問題なのだ。
「嘆きの壁を移した男」は、ユダヤ人の聖地である「嘆きの壁」をエルサレムから商業の中心として繁栄するテルアビブに移してしまうという、途方もない話。こんなふうにヴァイルの小説では、普通動かないものが一夜のうちに簡単に動かされてしまう。
そして「もうひとつのラブストーリー」では、近未来のイスラエルで、ヒトラーとアンネ・フランクのアンドロイドが恋に落ちる。アンネは言うまでもなく、ホロコーストの犠牲となった少女だ。結ばれた二人は年に一度仲良く「古き良きヨーロッパ」へ旅行する。そして、ヒトラーは窓から地上を指さしてアンネに言う。「ほら、見てごらん、ベルギーだ。かつては私のものだったんだよ」
それにしても、ヒトラーとアンネが結ばれるなどという不謹慎というか、冒瀆的と言ってもいいような物語がいまのイスラエルで許されるのだろうか? そういった読者の心配に作者がみずから答えるかのように、「良識の限界」ではあけすけなセックスも、ホロコーストも、そしてテロさえ茶化すような書き方が試みられ、「良識の限界」がどこにあるのか、問いかけている。ここで語られているのは「テロを笑いに変えるユーモア」なのだと著者は言う。
こんな調子で、著者は、現代イスラエルにとって深刻な話題である政治からも宗教からもあっさり距離をとり、タブーをものともせず、巧みなストーリーテリングを通して、イスラエルの現実を鮮やかに切り取って見せてくれる。その現実は混沌としたものだが、そこから新しい文学が生まれつつあることを感じさせてくれる一冊だ。
ALL REVIEWSをフォローする