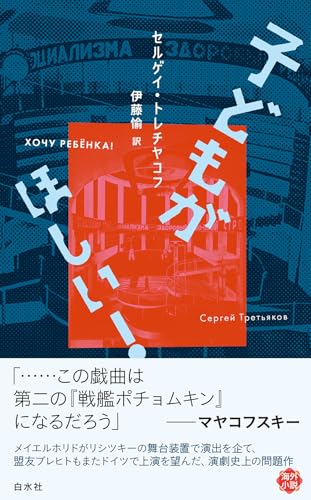書評
『缶詰サーディンの謎』(国書刊行会)
ことばの手触りをつきつけられる
じつにへんてこりんな小説だ。冒頭に登場するのは、ロンドンのフラットを仕事場として、秘書と浮気しながら、憎しみに突き動かされて小説を書きまくる作家。彼は週末に田舎の家に戻ると、温かい村人たちに囲まれて穏やかな時間を過ごす。このような設定なら、まだ「ありそうな」話だ。ところがある時、作家は息子に言われた一言をきっかけに性格が豹変し、列車の中で急死してしまう。葬儀の後、作家の妻はロンドンのフラットにやってきて、作家の秘書だった女性に対面する。普通ならここで、一悶着ありそうなものだが、なんと二人はいきなりベッドで数時間も激しく愛し合うのだ。
ここまでで読者は「あれあれ、この展開は?」と十分に驚くはずだが、これはまだほんの序の口。二人の女性はスペインのマヨルカ島に行き、ダンスホールで踊る「ダンシング・レディーズ」として有名になる。場面の切り替えは映画のようにぱっぱっと早く、描かれていることの意味について、読者に考え込むことを許さない。
次に場面は、ある哲学教授一家が住む海辺の家に移る。教授の妻は「この地球はぜんぶ偽物」で、「本物の地球は空に浮かんで、太陽の周りを超高速で回っている」と信じている。哲学教授の家に謎の黒いプードルがやってきて、いきなり爆発、哲学教授は両足を失う。この爆弾テロを行ったテロリストのグループには、冒頭に登場した作家の娘も加わっていたらしい。足を失った哲学教授と妻子は保養のため、マヨルカ島へ行く。
その後、小説の後半で舞台はポーランドに移る。さらに、手相占い師、将軍、些末大臣(ミニスター・オブ・インポンデラビリア)、といったいずれも一癖も二癖もある人物が入り乱れ……いや、だめ、だめ。こんな風にあらすじを説明しようとしても、小説は手をすりぬけてしまう。ばらばらに見えていた登場人物たちはやがてビリヤードの玉のように、いやぶちまけられたおもちゃ箱の中身のように、ぶつかりあって、奇抜な模様を描き出す。表題にある「缶詰サーディン」については、最後にSF的とも言える謎解きが示されるのだが、読者は呆然とするばかり。まさか、こんな風に終わっていいのか!?
そもそもこれは、あらすじを説明してわかるような小説ではない。じゃあ、何なのか?この小説はいたるところ、どこまで真面目なのかわからない哲学談義をちりばめ(若くして亡くなった天才数学少年が残した「ユークリッドはマヌケだった」という論文も収録されている)、様々な芸術や文学作品を引き合いに出しながら、ことばそのものの手触りを読者につきつけてくる。まさにそのことによって、現代世界に蔓延する政治的イデオロギーに毒された社会に対する解毒剤として作用するのだ。
今回が遅ればせながらの本邦初紹介になる著者テメルソン(一九一〇―八八)は、この小説を英語で書き、八六年にイギリスで出版しているが、ポーランド人である。第二次世界大戦前ポーランドで妻フランチシュカとともに、絵本や実験映画を手がけ、前衛芸術運動の一翼を担った後、フランスを経てイギリスに渡った。なるほど、固定観念に縛られないこの自由さはそういう背景から来ているのか、と納得。
小説はもっと自由でいいということを教えてくれる一冊だ。
ALL REVIEWSをフォローする