書評
『わたしの家族の明治日本』(文藝春秋)
明治の日本に暮らした外国人の記録は結構たくさん残っている。すぐ思いつくだけでもお雇い外国人医師の「ベルツの日記」、人類学者モースの「日本その日その日」、福澤家に嫁に入った「クララの明治日記」などがある。
本書は日記そのものではなく、アメリカ人で最年少、かつ女性初のOECD事務次長を務めた著者が、牧師だった高祖父の日本布教日記を紐解き、解説を施したものである。
ジョアンナさんの曽祖父トーマス・アレクサンダーは1977年、というと明治10年、西南戦争の年、妻のエマとともに長老派教会宣教師として日本に向った。テネシー州から機関車で大陸を横断、サンフランシスコから三週間の航海で横浜に着いた。「日本人は皆、まじめで、信心深い人たちのようです」とエマは家族に書き送った。
「イギリスの商人は、日本との儲からない商取引に見切りをつけていった」「(武士という)この生産性のない上流階級の大集団の中には、堕落した怠惰な生活を送るものもいた」「一連の激しい内戦の後、反乱軍がついに将軍を倒し、天皇を唯一の統治者として権力の頂点に復帰させた」。日本の近世・近代史への外国人ならでは、また政治経済の専門家ならではの、マクロな把握が興味深い。
トムとエマは海に面した低地、築地居留地に暮らす。トムは下関や金沢で、「西洋人嫌い」に直面しながら布教を続けた。エマは次々と子どもを産んだが、火事や水害の多さ、ネズミや虫にも悩まされ、夫が不在がちの中でくたびれ、明るさを失っていく。
宣教師たちが、自由民権運動や、国会開設要求に巻き込まれたくだりは面白い。「自由党党首の板垣退助氏は随分前からキリスト教に関心を持っている。洗礼を受ける気はないようだが、故郷の土佐で不況が広がることを望んでいる」とトムは、日記に書いた。1885年、トムは高知に赴き、教会を組織、十三人に洗礼を授ける。愛媛でも広島でも信者は増えていった。
悲しいこともあった。長女で教会オルガニストも務めたエラは16歳で死去する。一家は国内外の政治に翻弄された。条約改正、憲法発布、日清戦争、その度に高まるナショナリズム。トムは明治学院の教師となる。そこでも、宗教教育を続けるミッションスクールは各種学校扱いとなり、学生が「上級学校への進学や徴兵猶予の特典」を失うという問題に直面した。しかも宣教師の中にも、出世や良い待遇を求める者がおり、派閥や争いもあって、トムはストレスから体調をくずす。
この本は理想と情熱を持って日本にキリスト教を伝えようとした一人の伝道師が、50歳で最後の任地京都を離れ、ホノルルで客死するまでの生涯を描いている。最後の手紙でこう述べた。「もしこの世で神に仕える二十五年間が十回あるのなら、私はよろこんですべてを日本に捧げるでしょう」
日本語を流暢に話す彼は多くの日本人に慕われ、青山彦太郎は「稀に見る温厚で誠実な人、いつも微笑んでいて、優しい父親であるかのようだった」、植村正久は「高潔で優しく、学ぶことが好きな人」と評している。
次女ヤングエマは父と同じく伝道の道を選び、女子学院に赴任するも20代で腸チフスに倒れている。青山墓地の彼女の墓の使用料は今も女子学院が払い続けているという話に胸が熱くなった。三女メアリーは東京女子大学で教え、ライシャワー博士の同僚だった。著者は五女エヴィーの孫にあたる。実に興味深い家族の樹である。
本書は日記そのものではなく、アメリカ人で最年少、かつ女性初のOECD事務次長を務めた著者が、牧師だった高祖父の日本布教日記を紐解き、解説を施したものである。
ジョアンナさんの曽祖父トーマス・アレクサンダーは1977年、というと明治10年、西南戦争の年、妻のエマとともに長老派教会宣教師として日本に向った。テネシー州から機関車で大陸を横断、サンフランシスコから三週間の航海で横浜に着いた。「日本人は皆、まじめで、信心深い人たちのようです」とエマは家族に書き送った。
「イギリスの商人は、日本との儲からない商取引に見切りをつけていった」「(武士という)この生産性のない上流階級の大集団の中には、堕落した怠惰な生活を送るものもいた」「一連の激しい内戦の後、反乱軍がついに将軍を倒し、天皇を唯一の統治者として権力の頂点に復帰させた」。日本の近世・近代史への外国人ならでは、また政治経済の専門家ならではの、マクロな把握が興味深い。
トムとエマは海に面した低地、築地居留地に暮らす。トムは下関や金沢で、「西洋人嫌い」に直面しながら布教を続けた。エマは次々と子どもを産んだが、火事や水害の多さ、ネズミや虫にも悩まされ、夫が不在がちの中でくたびれ、明るさを失っていく。
宣教師たちが、自由民権運動や、国会開設要求に巻き込まれたくだりは面白い。「自由党党首の板垣退助氏は随分前からキリスト教に関心を持っている。洗礼を受ける気はないようだが、故郷の土佐で不況が広がることを望んでいる」とトムは、日記に書いた。1885年、トムは高知に赴き、教会を組織、十三人に洗礼を授ける。愛媛でも広島でも信者は増えていった。
悲しいこともあった。長女で教会オルガニストも務めたエラは16歳で死去する。一家は国内外の政治に翻弄された。条約改正、憲法発布、日清戦争、その度に高まるナショナリズム。トムは明治学院の教師となる。そこでも、宗教教育を続けるミッションスクールは各種学校扱いとなり、学生が「上級学校への進学や徴兵猶予の特典」を失うという問題に直面した。しかも宣教師の中にも、出世や良い待遇を求める者がおり、派閥や争いもあって、トムはストレスから体調をくずす。
この本は理想と情熱を持って日本にキリスト教を伝えようとした一人の伝道師が、50歳で最後の任地京都を離れ、ホノルルで客死するまでの生涯を描いている。最後の手紙でこう述べた。「もしこの世で神に仕える二十五年間が十回あるのなら、私はよろこんですべてを日本に捧げるでしょう」
日本語を流暢に話す彼は多くの日本人に慕われ、青山彦太郎は「稀に見る温厚で誠実な人、いつも微笑んでいて、優しい父親であるかのようだった」、植村正久は「高潔で優しく、学ぶことが好きな人」と評している。
次女ヤングエマは父と同じく伝道の道を選び、女子学院に赴任するも20代で腸チフスに倒れている。青山墓地の彼女の墓の使用料は今も女子学院が払い続けているという話に胸が熱くなった。三女メアリーは東京女子大学で教え、ライシャワー博士の同僚だった。著者は五女エヴィーの孫にあたる。実に興味深い家族の樹である。
初出メディア
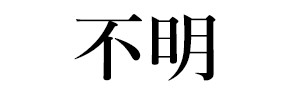
初出媒体など不明
正しい情報をご存知でしたらお知らせください。
ALL REVIEWSをフォローする

































