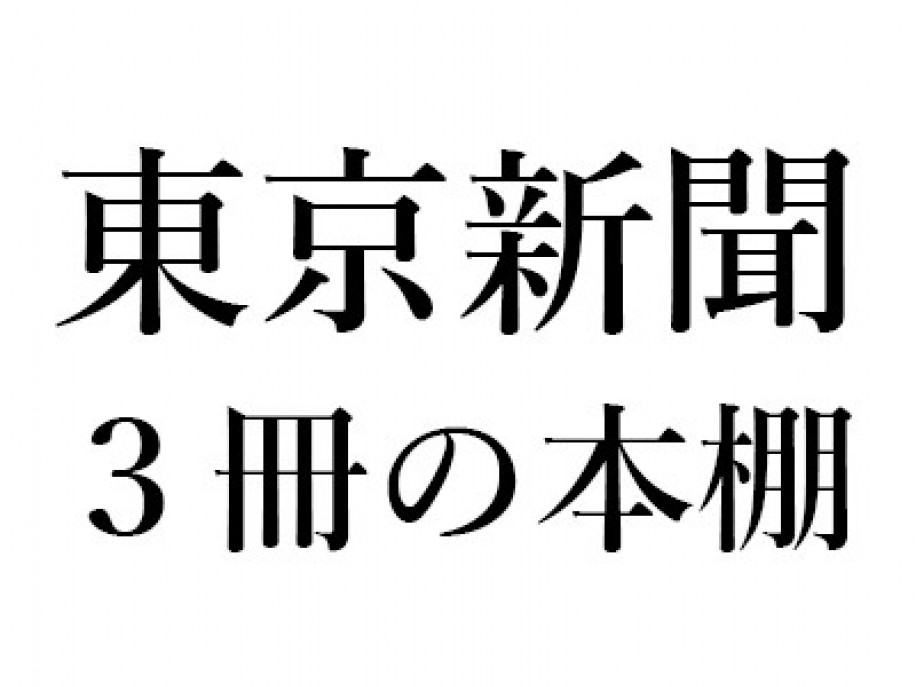書評
『新装版 青い壺』(文藝春秋)
新式の『女の一生」
現に生きている人たちを、「小説の中に」呼び入れて、そのまま「小説の中で」生活させる。たまにはそんな工夫の小説を読んでみたい、というむきには、有吉佐和子の『青い壼』をおすすめする。小説の中でただ生活してもらうだけでは芸も愛想もなさすぎるので、きれいなものでもそばに置いてあげましょうと、どこかから青磁の壼を探してきて、ぽんと置いた、とでもいいたくなるようなさりげなさがこの本からにじみでている。そう、さりげなさがこの場合たいせつだ。
日常生活のつづきからすっとはじまるようなこの作品を隣に置いたら、いまどきの小説の大半はでっちあげとからくりだらけ、けれんみ過多にみえてくるからふしぎだ。ありそうもない話、読者が身につまされないような話を書く。そうでなきゃ頭が悪いといわんばかりの隆盛ぶりだ。
有吉佐和子は、ありそうな話の最右翼の書き手だった。よく読まれたのは、身につまされなくてなんで小説なんか読みますか、というそのころの大方の読者の支持を得たからだ.もっとも僕がこの「青い壼』を読もうとしていたとき、かつてのベストセラー『恍惚の人』を何度も読んでいるという人から、「あの人は安心できるから」と言われて、そのときはちょっと妙な気がした。
さて目の前にある青い壼は、篤実なだけがとりえの無名の陶工の窯からある日ひょっこり生まれた。まがいの古色をつけられて道具屋の手に渡されそうになるところを危うく助けられて、デパートの美術コーナーのケースに置かれた。
そうしたいきさつを枕に、ひとつの壼を狂言回しに使って、十二の話を読み切りで綴ってゆくオペラ・ハット形式の、この本のしゃれた趣向は、月刊誌に一年間にわたって連載するために編みだされた。
デパートで包んでもらった壼をかかえて、定年退職した男が世話になった副社長のもとにお礼にうかがうサラリーマン怪談(第二話)。副社長夫人がその壼に花を活けながら夫の不品行に気づかされそうになる、さらに怖い話(第三話)。
「できれば一日でも私があなたより先に死んでほしいんだって、はっきり言いましたよ、雅子が。税率からいって、その方がトクなんですって」
そんなことを娘に言われたと妻に訴えられて副社長が絶句する、もっと怖い話(第四話)。
壼は、第四話で、副社長の一喝でお払い箱にされ、さらに人手から人手へと渡る。壼という性質上、渡る先には茶の間やアパートの一室。つまり女の城。女性も三歳の幼女から八十歳の老女まで取り揃えてある。就職したての若い女もいる。嫁も姑もいる。
壼をだしにして、作者は新式の『女の一生』をもくろんだのかもしれない。モーパッサン流に一人のヒロインの生涯を追うだけでは足りない。何人もの女性に、女の一生を受けもってもらって、十九世紀的手法ではつかまえきれない複雑な世相を描ききろうとした。
有吉佐和子にはそういう気概があった。
青磁の壼が女の身辺に置かれることで、生活の奥に働く力、抗しがたく癒しがたい時の流れがむきだしになる。十二話の至るところで無常の鐘が鳴る。
壼はスペインまで渡り、日本にもどってきたときには本物の古色までついて、十二世紀の宋の龍泉窯の逸品に化けている。
壼の成長物語にもなっているのだが、そのくだりまで読み進んできて、この物語自体が逸品に化けていることにいやでも気づかされる。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする