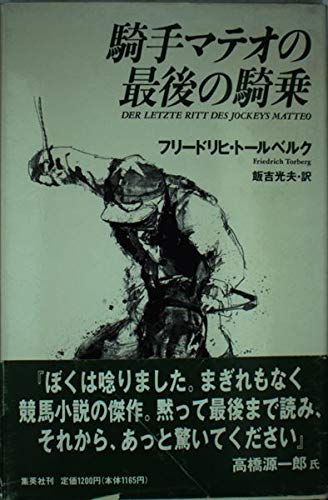書評
『死神とのインタヴュー: 短篇集』(岩波書店)
世界を語りつくせ
三月十日、といわれても、ピンとこない東京っ子が大半になった。一九四五年三月十日、米軍の大空襲で東京の下町は壊滅した。五月には東京は焦土と化して空襲リストからはずされ、他の都市が次々と襲われた。
神戸はとくにひどかった。このあいだの震災もひどかったが、五十年前にも神戸は一度滅亡してしまっていたのだ。
日本の都市がはじめてではない。すでにドイツの大都市がいためつけられていた。
いまのハンブルクは、東京同様、そんなことがありましたかという顔をしているが、東京の「三月十日」の二年前に、三度にわたる絨緞爆撃で市街地の六十八パーセントが破壊された。焼失した家屋は三十万戸。死者は十万におよぶ。
そのときの被災の様子をルポルタージュ風に綴った「滅亡」という貴重な作品がある。
作者はハンス・エーリッヒ・ノサック。当時四十二歳で、父親の貿易会社に勤めていた。「滅亡」を書いて以後、苛酷すぎる運命に見舞われて平穏な人生からいきなり引き剥がされてしまった人間、という重い主題にわけいって、『遅くとも十一月には』、『盗まれたメロディ』などの名作を書いて、ドイツ現代文学の最重要な作家と目されるようになった。
絨緞爆撃もしくは飽和爆撃方式という、都市を火攻めにするために開発された新戦法で襲われたのだといまではわかっている。被害の大きさも数字でくくられている。だがそういうことは後の整理の仕方にすぎない。
作者が体験したのはまず轟音だった。作者と妻はハンブルク市内に住んでいたのだが、その日は郊外にある貸家にいた。それはハンブルク市にむかう二千機近くの爆撃機の轟音だった。そして、火災によって下から赤く照らされた市をおおう煙雲。
作者夫婦は二度目の空襲のあとトラックに便乗して市内にむかい、異様な光景を目にする。以前なら視線が建物の壁にさえぎられるところに、無言の平面が果てしなくひろがっているのだ。つい先日までなじんでいた故郷の町は、屍ともいえない姿になってしまった。墓場ともいえない。
わたしを取りまくものは、けっして失われたものを思い起こさせたりするものではなかった。それはなにか別のもの、異質のもの、本来あり得ないものであった。
作者たちの住居も焼け落ちていた。過去とも未来とも切り離された奇怪な時間がはじまる。炭と化した家財道具のにおいのなかで、ドブネズミとハエに悩まされながら。作品は空襲から三ヵ月後に書かれた。ドイツ降伏はまだまだ先のことだ。
僕らはいま太平楽な本にとりまかれている。新聞で大々的に予告広告されて、例のサリン地下鉄悲劇をドキュメントしたと称する大部な本もじつに客あしらいがいい。時にそうした本に倦むと、僕はこの作品を開く。そのたびに、世界はここに語りつくされているという気になる。
作者は、『東京大空襲』を書いたわが早乙女勝元のように猛火をくぐったわけではない。だがまぎれもなく滅亡を体験した。書き出しは、「わたしはハンブルクの滅亡を傍観者として体験した」である。
空襲体験のない僕にも、この作品を読むと、あらかじめなにかを失っているという思いにかられる。そして気を取り直す。
ハンブルク空襲の指揮官はカーチス・ルメイ。三月十日以後の日本空襲を指揮した将軍だ。その将軍に日本政府は勲一等旭日大綬章を贈っている。よほどの功があったのだろう。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする