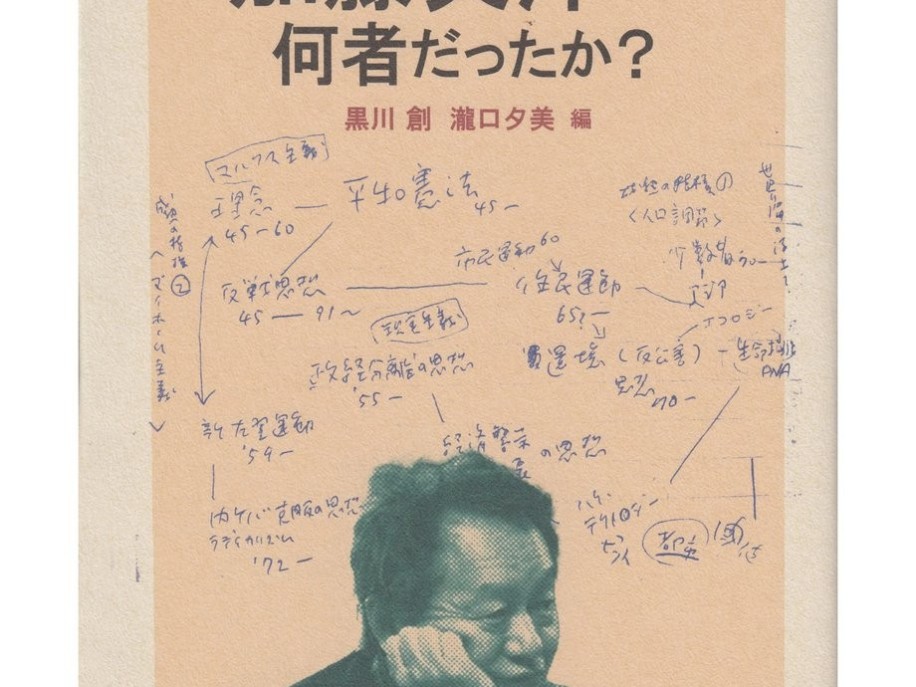書評
『僕が批評家になったわけ (ことばのために)』(岩波書店)
批評をうしろ側から覗かせるような書名だが、そうではない、批評とは何かについて語ったものだ。
なぜいま批評なのか。
かつて批評といえば、文芸批評を意味し、しかつめらしいものが多かった。しかし、いつの間にか読者たちは遠ざかり、批評家たちも自閉的な空間にこもりがちになった。
かりにそれを批評の危機としてとらえるならば、通常二つの反応が見られる。批評の大切さを強調するか、さもなければ教養がないとだめだと読者を恫喝することだ。しかし、著者はそのどちらの態度も取らなかった。
なぜ批評が必要なのかについては一言も触れていない。そのかわり、かりに批評がなかったら、日本の近代がどうなったかをシミュレーションして見せた。すると、殺伐とした思考の砂漠が目の前にくり広げられた。
現代社会にとって批評はやはり必要だ。ただ、批評は風邪を引いた。
読者を取り戻し、批評を元気にさせるためにはどうすればよいか。風邪の症状を和らげるのではなく、熱が出る原因を取り除くための薬が処方された。
著者の関心の根底にあるのは、おそらく文学批評であろう。しかし、本書で批評について語るとき、いっさい仕切りを作らない。逆に「批評の酵母」は言語生活のほとんどの局面に遍在している、と主張する。市民社会のあらゆる言論活動を囲い込むことによって、かつての文芸批評が再編成され、新たな可能性が生まれてきた。
批評の方法について、「思いついたこと」をそのまま書けばよい、と力説した。重要なのは独自の思考があるかどうかで、批評自体は高級でなくても、精緻でなくてもよい。モンテーニュ『随想録』ではなく、吉田兼好が引き合いに出されたのはそのためだ。むろん『徒然草』に批評の原型を見いだしたのは、西欧起源の批評的精神を否定するためではない。そこには二番目の戦略が隠されている。中世の日本は随筆という方法によって、「漢文の教養」から自由になった。同じように、いま「気ままに書く」ことによって、欧文脈的な思考から自由になることができる。
三つ目は専門家よりも公衆や世間を意識することだ。ほんらい批評は読者があってはじめて成り立つものだ。ところが、方法論の深化と言語の精錬によって、批評のことばは専門家のあいだの方言になった。思考の硬直化から脱却するためには、いったん批評の外側に出る。すると、素人っぽさが批評をリセットする有効な手段になった。
この本はシリーズ「ことばのために」の一巻として刊行された。批評とは何か、という問題意識と同時に、ことばも主要なテーマの一つである。
ことばをめぐる急激な環境変化はインターネットの言語活動に顕著に現れている。サイバー空間では「声」と文章の境界が曖昧になり、「声」がそのまま書かれるものになることで、言論の粗雑化をもたらした一面は確かにある。一方、通信技術が「声」と文章のあいだの権力関係を崩壊させ、書き手の序列を無効にしたのも事実だ。活字の世界では、編集者が選別の役割を果たしてきたが、この新しい発表のメディアでは第三者が介在しない。『徒然草』的な批評はサイバースペースにもぴったりの表現様式である。
文芸批評というと、何やら肩の凝った文章を連想するが、本書はまったく違う。内容が濃密なわりには、文章は軽やかだ。心に浮かぶまま書き留められているから、全体としては読みやすくて面白い。著者が提唱する随想風の批評にもよい手本を示した。
【この書評が収録されている書籍】
なぜいま批評なのか。
かつて批評といえば、文芸批評を意味し、しかつめらしいものが多かった。しかし、いつの間にか読者たちは遠ざかり、批評家たちも自閉的な空間にこもりがちになった。
かりにそれを批評の危機としてとらえるならば、通常二つの反応が見られる。批評の大切さを強調するか、さもなければ教養がないとだめだと読者を恫喝することだ。しかし、著者はそのどちらの態度も取らなかった。
なぜ批評が必要なのかについては一言も触れていない。そのかわり、かりに批評がなかったら、日本の近代がどうなったかをシミュレーションして見せた。すると、殺伐とした思考の砂漠が目の前にくり広げられた。
現代社会にとって批評はやはり必要だ。ただ、批評は風邪を引いた。
読者を取り戻し、批評を元気にさせるためにはどうすればよいか。風邪の症状を和らげるのではなく、熱が出る原因を取り除くための薬が処方された。
著者の関心の根底にあるのは、おそらく文学批評であろう。しかし、本書で批評について語るとき、いっさい仕切りを作らない。逆に「批評の酵母」は言語生活のほとんどの局面に遍在している、と主張する。市民社会のあらゆる言論活動を囲い込むことによって、かつての文芸批評が再編成され、新たな可能性が生まれてきた。
批評の方法について、「思いついたこと」をそのまま書けばよい、と力説した。重要なのは独自の思考があるかどうかで、批評自体は高級でなくても、精緻でなくてもよい。モンテーニュ『随想録』ではなく、吉田兼好が引き合いに出されたのはそのためだ。むろん『徒然草』に批評の原型を見いだしたのは、西欧起源の批評的精神を否定するためではない。そこには二番目の戦略が隠されている。中世の日本は随筆という方法によって、「漢文の教養」から自由になった。同じように、いま「気ままに書く」ことによって、欧文脈的な思考から自由になることができる。
三つ目は専門家よりも公衆や世間を意識することだ。ほんらい批評は読者があってはじめて成り立つものだ。ところが、方法論の深化と言語の精錬によって、批評のことばは専門家のあいだの方言になった。思考の硬直化から脱却するためには、いったん批評の外側に出る。すると、素人っぽさが批評をリセットする有効な手段になった。
この本はシリーズ「ことばのために」の一巻として刊行された。批評とは何か、という問題意識と同時に、ことばも主要なテーマの一つである。
ことばをめぐる急激な環境変化はインターネットの言語活動に顕著に現れている。サイバー空間では「声」と文章の境界が曖昧になり、「声」がそのまま書かれるものになることで、言論の粗雑化をもたらした一面は確かにある。一方、通信技術が「声」と文章のあいだの権力関係を崩壊させ、書き手の序列を無効にしたのも事実だ。活字の世界では、編集者が選別の役割を果たしてきたが、この新しい発表のメディアでは第三者が介在しない。『徒然草』的な批評はサイバースペースにもぴったりの表現様式である。
文芸批評というと、何やら肩の凝った文章を連想するが、本書はまったく違う。内容が濃密なわりには、文章は軽やかだ。心に浮かぶまま書き留められているから、全体としては読みやすくて面白い。著者が提唱する随想風の批評にもよい手本を示した。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする