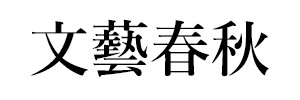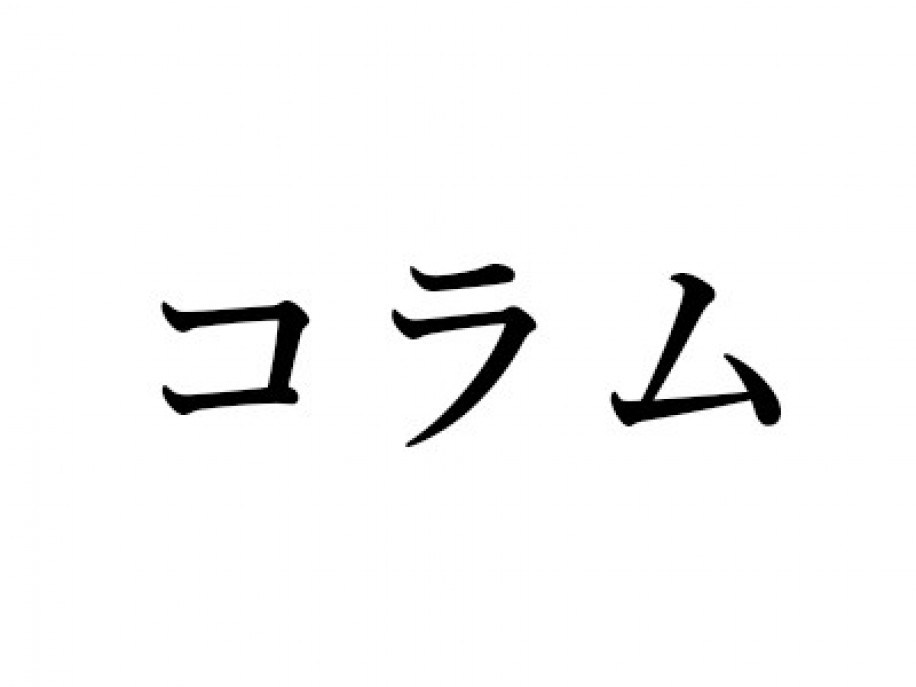対談・鼎談
角田忠信『日本人の脳』(大修館書店)|丸谷才一+木村尚三郎+山崎正和の読書鼎談
丸谷 最近は、日本人論が非常に盛んで、書店にはその手のものが氾濫してますが、日本人および日本文化の特殊性を最も基本的なところからとらえたのがこの本じゃないか、と思います。この角田さんの説が正しいかどうかを医学的に判断する力は、もちろん、ぼくにありませんし、多分、木村さんにも山崎さんにもないと思います(笑)。しかし、ぼくには非常におもしろかったし、なるほど、そういうわけだったのか、といろいろ合点がいく本なんですね。
角田さんの説は、わたしの理解できた範囲では、こうなります。
人間の脳は、左半球が言語の表現や理解、それから数学で代表されるような論理的思考を扱います。そして右半球は、空間的な広がりとか、顔や形や、図形の認知、音楽などを扱う。これは大脳生理学でわかっていることなんですね。
ところが、角田さんは耳鼻科のお医者さんで、聴覚や言語障害を調べているうちに、一つの重大な発見をした。それは、日本人と日本人以外とでは、左右の脳が音を分担するしかたが大違いだということです。
西欧人の場合には、音楽、単なる母音、人の声、虫の音などが、みんな右の脳で扱われる。ところが日本人では、言語の子音や母音、あらゆる人の声、虫や動物の鳴き声が左の脳に入るんですね。
つまり、西欧人と日本人とでは脳の働き方が違う。そしてこれは、遺伝によるものではなく、十歳までに日本語で育ったか否かで決まるんだそうです。さらに、角田さんが調べた結果によると、朝鮮人は、西欧人型なんです。そして日本で育った朝鮮人の二世は、日本人型になる。とすると、これは日本語が脳の働きに作用すると考えるしかない。
日本語には、母音が非常に多い。時には、母音だけの有意音――たとえばアイ(愛)とか、ウエ(飢え)――がある。母音支配的な言語であることが、こういう結果をもたらしたと考えられる。
とにかく、読んでアッと驚く衝撃的な本ですよね。
山崎 古いタイプの日本人論というのは、基本的に日本人を東洋文化の中に位置づけ、それを西洋文化と対置させるという立場をとっていたんですね。岡倉天心や三宅雪嶺にしてもそうですが、日本人を近代における東洋精神の代表者として考えて、西洋文化に対して何らかの優位性を確保しようというのが多かった。
ところが戦後の傾向として、日本人は、東洋の中でもかなり違った民族だという論をなす人がふえてきた。わたくしなども、実は、そういう立場をとるひとりですが、この本が日本人は、大脳の機能からして、西欧人と違う程度に、他の東洋人とも違うということを立証してくれたので、たいへん心強く思いました。
木村 しかし、ちょっと疑間もあるんです。たとえば、こう書いてある。
要するに、われわれが母音を使う以上、日本人は変らないんだということですね。
しかし、ヨーロッパ人は、昔から論理的、科学的に思考していたでしょうか。西ヨーロッパで科学的精神が発達したのは、十六、十七世紀以降で、中世の人は、森を見ると恐怖感を覚えたし、星を見てそこに天体の音楽を聴いた。
いわば自然に対する情感を帯びた科学ともいうべき魔法学が、中世、近世にはたいへんに力をもっていたわけで、ヨーロッパ人が初めからいまのように論理的に考えていたとは、必ずしも思わないんです。
山崎 そうそう。
木村 そうしますと、ヨーロッパ人の論理的、科学的思考も、彼らの脳が、はたしてここに書いてあるように、左半球が言語ないし論理的なもの、右半球が音楽的なもの、という分担をしていたからかという素朴な疑問が生じます。
もう一つは、朝鮮とか、東南アジア、インドなどが、西欧型の脳の反応をしめすという点です。それにもかかわらず、これらの地域では、必ずしも西欧文明のような合理的なものが発達しているとはいい難い。この問題をどう解釈したらよいのか。
丸谷 同感ですね。たとえばロゴス的なものとパトス的なものというのは、はたしてこんなふうに単純に分けることができるものだろうか。だれかがロゴスとパトスに分けたから、分けられたのであって、もし分けなければ一つである。三つに分ければ三つなわけでしょう。つまり、観念操作の問題にすぎないわけですよね。
山崎 大体、人間の精神機能をロゴスとパトスの二つに分けるというのは、西洋でも十七世紀ないし十八世紀以前の考え方で、十八世紀以降になると、だいたい三分法になるんですね。純粋な理性の分野、純粋な感性の分野、その中間に想像力の分野というものを別個に立てる考え方のほうが有力なんですね。
丸谷 カントの考え方……。
山崎 ええ、カントの考え方がその典型でしょうね。
いまはむしろ、三分法で考えるほうが有力になっていますから、それに大脳の右、左を対応させるのは、ちょっと無理だろうと思う。大脳は残念ながら二つしかないから、二分法になるわけですが……。
丸谷 いや、大脳だって三つに分けることができるんじゃないの。
山崎 ええ?(笑)
丸谷 これはまずいかな(笑)。
(次ページに続く)
角田さんの説は、わたしの理解できた範囲では、こうなります。
人間の脳は、左半球が言語の表現や理解、それから数学で代表されるような論理的思考を扱います。そして右半球は、空間的な広がりとか、顔や形や、図形の認知、音楽などを扱う。これは大脳生理学でわかっていることなんですね。
ところが、角田さんは耳鼻科のお医者さんで、聴覚や言語障害を調べているうちに、一つの重大な発見をした。それは、日本人と日本人以外とでは、左右の脳が音を分担するしかたが大違いだということです。
西欧人の場合には、音楽、単なる母音、人の声、虫の音などが、みんな右の脳で扱われる。ところが日本人では、言語の子音や母音、あらゆる人の声、虫や動物の鳴き声が左の脳に入るんですね。
つまり、西欧人と日本人とでは脳の働き方が違う。そしてこれは、遺伝によるものではなく、十歳までに日本語で育ったか否かで決まるんだそうです。さらに、角田さんが調べた結果によると、朝鮮人は、西欧人型なんです。そして日本で育った朝鮮人の二世は、日本人型になる。とすると、これは日本語が脳の働きに作用すると考えるしかない。
日本語には、母音が非常に多い。時には、母音だけの有意音――たとえばアイ(愛)とか、ウエ(飢え)――がある。母音支配的な言語であることが、こういう結果をもたらしたと考えられる。
とにかく、読んでアッと驚く衝撃的な本ですよね。
山崎 古いタイプの日本人論というのは、基本的に日本人を東洋文化の中に位置づけ、それを西洋文化と対置させるという立場をとっていたんですね。岡倉天心や三宅雪嶺にしてもそうですが、日本人を近代における東洋精神の代表者として考えて、西洋文化に対して何らかの優位性を確保しようというのが多かった。
ところが戦後の傾向として、日本人は、東洋の中でもかなり違った民族だという論をなす人がふえてきた。わたくしなども、実は、そういう立場をとるひとりですが、この本が日本人は、大脳の機能からして、西欧人と違う程度に、他の東洋人とも違うということを立証してくれたので、たいへん心強く思いました。
木村 しかし、ちょっと疑間もあるんです。たとえば、こう書いてある。
私の「精神構造母音説」からすると、我々日本人の精神構造は日本語が続く限り、過去・未来を含めて共通した基本的特徴を持続するものと考えられる
要するに、われわれが母音を使う以上、日本人は変らないんだということですね。
しかし、ヨーロッパ人は、昔から論理的、科学的に思考していたでしょうか。西ヨーロッパで科学的精神が発達したのは、十六、十七世紀以降で、中世の人は、森を見ると恐怖感を覚えたし、星を見てそこに天体の音楽を聴いた。
いわば自然に対する情感を帯びた科学ともいうべき魔法学が、中世、近世にはたいへんに力をもっていたわけで、ヨーロッパ人が初めからいまのように論理的に考えていたとは、必ずしも思わないんです。
山崎 そうそう。
木村 そうしますと、ヨーロッパ人の論理的、科学的思考も、彼らの脳が、はたしてここに書いてあるように、左半球が言語ないし論理的なもの、右半球が音楽的なもの、という分担をしていたからかという素朴な疑問が生じます。
もう一つは、朝鮮とか、東南アジア、インドなどが、西欧型の脳の反応をしめすという点です。それにもかかわらず、これらの地域では、必ずしも西欧文明のような合理的なものが発達しているとはいい難い。この問題をどう解釈したらよいのか。
丸谷 同感ですね。たとえばロゴス的なものとパトス的なものというのは、はたしてこんなふうに単純に分けることができるものだろうか。だれかがロゴスとパトスに分けたから、分けられたのであって、もし分けなければ一つである。三つに分ければ三つなわけでしょう。つまり、観念操作の問題にすぎないわけですよね。
山崎 大体、人間の精神機能をロゴスとパトスの二つに分けるというのは、西洋でも十七世紀ないし十八世紀以前の考え方で、十八世紀以降になると、だいたい三分法になるんですね。純粋な理性の分野、純粋な感性の分野、その中間に想像力の分野というものを別個に立てる考え方のほうが有力なんですね。
丸谷 カントの考え方……。
山崎 ええ、カントの考え方がその典型でしょうね。
いまはむしろ、三分法で考えるほうが有力になっていますから、それに大脳の右、左を対応させるのは、ちょっと無理だろうと思う。大脳は残念ながら二つしかないから、二分法になるわけですが……。
丸谷 いや、大脳だって三つに分けることができるんじゃないの。
山崎 ええ?(笑)
丸谷 これはまずいかな(笑)。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする