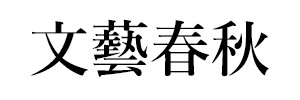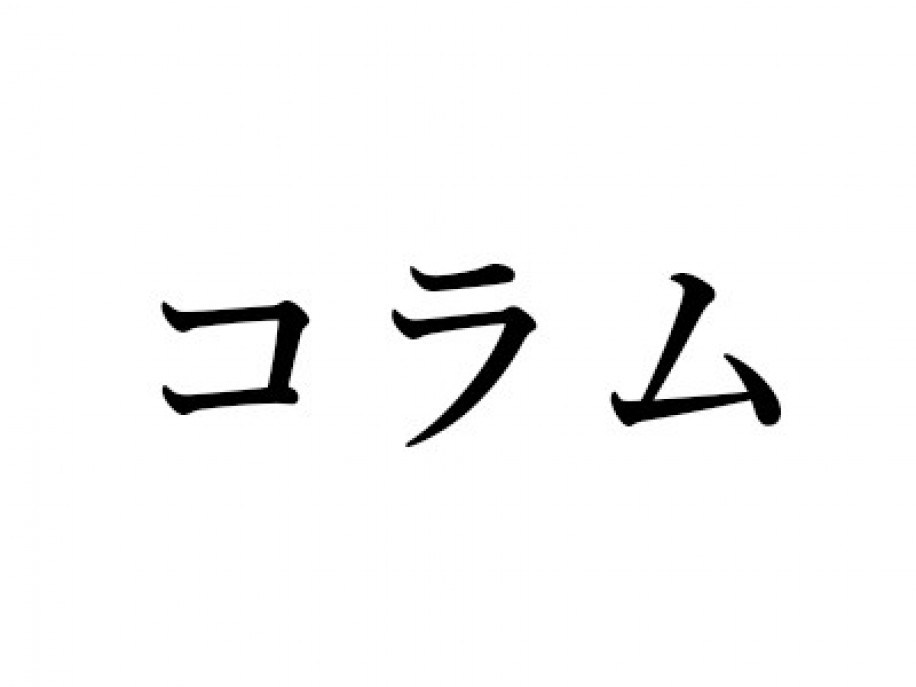対談・鼎談
角田忠信『日本人の脳』(大修館書店)|丸谷才一+木村尚三郎+山崎正和の読書鼎談
山崎 わたくしが何より感動したのは、文化が人間の生理機能にまで浸透するということ。生理的反応そのものが、すでに文化の違いによって影響を受ける、という発見でした。これは、メルロ・ポンティの「身体論」に対する重大な傍証ですよ。ただ、角田さんが発見された科学的な事実を説明するときに、もっぱら日本語の母音の問題のみと結びつけてしまうのは早計だと思うんです。
たとえばわたしたちは、それこそ「虫の声」という言葉を小さいときから聞いて育っている。虫の声を擬人化して聴いているわけですね。言語だけでなくて、もっと綜合的な文化を体験して、その中で脳をつくりあげているはずです。
角田さんが実験されている人間は、大体において、日本語の中で育った二十代以上の人たちじゃないかと思うんです。たとえば、日本語だけは覚えたけれども、文化的体験のない六歳とか七歳の子供についてこれが当てはまるのかどうか、よくわからない。
木村 日本の場合、笙とか、篳篥(ひちりき)の音を左の脳で受けとるわけですね。ということは、音楽的なものを左でも受けとっているわけです。左を言語脳、右を音楽脳という区別は、西欧人の区別で、その分け方が日本人の場合もはたして妥当なのかどうか。
角田先生は右の脳が西洋音楽の器楽曲を受け入れる、とおっしゃっています。しかしそれは、日本人の感覚になじまない音が右に入っているだけ、ともいえる。若いときにクラシックかジャズに夢中になっても、やがて憑き物が落ちるみたいに離れてしまう人が多い日本人の場合、本当に左半球を音楽脳といえるのでしょうか。
丸谷 レヴィ・ストロース以後の考え方でいくと、あの命名はおかしいわけね。
各民族は各民族の文化をもっていて、それはそれでちゃんとしたものだ、それを西欧優先でいくのはおかしい、という考え方をとると、右が音楽脳って考え方は、西欧に限定された思考ですよね。
木村 最後のところで、右の脳と左の脳のバランスを取ることが大事だと書いてありますが、日本人の考え方が左に片寄っているために、科学的な思考に不向きであるような印象を、この本からは何となく感じます。しかし、現代の科学というのは、直感と、きわめて繊細な感覚を実は必要としていて、たとえば日本人がエレベーターをつくると、西欧人は感嘆するわけです。羽根ぶとんの上に停まるようにソフトランディングして、床と一分の狂いもない。日本のコンピューターを使うと、預金通帳の数字がピタッと揃うわけです。ところが、アメリカのコンピューターだと、万の単位、千の単位が○・五ミリくらい多少デコボコするんですって。こういった日本人の繊細さというのは、科学に生きているわけですね。
丸谷 でも、これを読んでいろいろ思い当ったことがありました。たとえば西洋音楽を聴くには特殊な訓練が必要だ、と書いてありますね。
新潟の高等学校には清和寮という、別格の寮があったんです。そこの応接間に電蓄があり、名曲がズラーッと揃っていました。まあ金のかからない名曲喫茶ですね。
山崎 それでこういう文化人が生まれたわけです(笑)。
丸谷 つまり、旧制高等学校がぜひ仕込まなきゃならなかったのは、むずかしい本を読ませること、もう一つは西洋音楽を聴かせることなんですよ。それも強制的に聴かせるくらいにしないと、日本の知識人はできあがらなかったんですね。
新潟高校の初代校長は八田三喜ですけれども、大教育者だからこそ思いついた仕掛けじゃないかと思って、驚嘆したんです。
第二に、日本人はなぜベートーベンの「第九シンフォニー」があれほど好きなのか、ぼくはよくわからなかった。この本を読んだら、あ、「第九」を好きなのは人間の声が入っているからだ、人間の声であれば、外国語であってもいいんだ、ということがわかったんですよ。
山崎 最初に丸谷さんがこの本を紹介されたときに、左側の頭脳は言語および論理能力を扱うものだ、と要約されましたが、ちょっと異を立てますと、普通考えられているように、言語と論理というものは、全面的に重なるものではないんじゃないかと思うんです。論理の機能というのは、じつは数学にも現われるもので、言語がなくても活動できるわけですね。数学というのはボキャブラリーのきわめて少ない言語で、ゼロから十までしかない。それだけの単語を使って、あれほど高度の論理構造をつくることができるわけです。
裏返していえば、言語の機能のうち論理の占める位置は、非常に小さいのではないかと思うんです。残る言語の機能とは何かといえば、すぐ思いつくのは、いろいろな感覚現象をパターンとしてとらえる能力です。ニワトリの鳴き声というのは無限に複雑な音ですけれども、それをコケコッコーという「型」としてとらえる。そのときに、コケコッコーは擬声語という言語になったわけですね。
このパターン化の能力というのが、言語の非常に重大なもう一つの機能であって、日本人において特に発達しているのは、そっちのほうではないかと思う。そうすると、日本人がなぜこれほど擬態語、擬声語を発達させたかということがよくわかるわけです。音のしないものについてまで「音」を発明している。
木村 「シーン」とか。
山崎 ニョロニョロ、ヌルヌルとか、最後には「雪がしんしんと降る」というのまで発明しているわけですね。これはパターン化の能力ですよ。
そうすると、左側の頭脳が受けもっているのは、じつは、パターン化の機能なのであって、それが笙、篳篥の音から虫の声まで、人間的表情を帯びた信号としてパターン化して受けとっていると考えられます。いいかえれば、右側の頭脳が感覚的な音を受けとる前にそれを擬声語としてひっさらってしまう、というふうに見ると、わりあいすっきりするんじゃないでしょうか。
木村 日本人は音を文字に変えて受けとるわけかしら。
山崎 そうなんです。ですから早い話が、日本人は自己紹介をするとき、名刺を交換して相手の名前が字に書いてあると、非常に安心して覚えるんですね。ところが西欧人は名前を耳で聞いて、それを音のままで覚えますよ。
つまり音がパターン化される前に、複雑な音をそのものとして覚えられるんですね。だから、おかしな発音でわたくしの名前を口にしますが、とにかくだれであるかわかる。
丸谷 ところで、この本の対談の章に、
とあるでしょう。とすると、昔の中国人といまの中国人、違っちゃったのかしら。虫の音を聴く風流っていうのは、漢詩を読んでわれわれが教わったものでしょう。
木村 そうですね。
丸谷 それがいつの頃からでしょうか、中国人は虫の音を聴くことを忘れちゃって、日本人だけが虫の音を聴いて「ああ、わびしいなあ」なんていって聞きほれる。こういうことになったとすると、これはたいへんな衝撃ね。感受性の移りかわりの歴史というのは、じつに強烈な感銘を与えるんですね。
山崎 だから、人間というのは非常に不思議なものだということがわかったことが、最大の収穫じゃないですか。
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
たとえばわたしたちは、それこそ「虫の声」という言葉を小さいときから聞いて育っている。虫の声を擬人化して聴いているわけですね。言語だけでなくて、もっと綜合的な文化を体験して、その中で脳をつくりあげているはずです。
角田さんが実験されている人間は、大体において、日本語の中で育った二十代以上の人たちじゃないかと思うんです。たとえば、日本語だけは覚えたけれども、文化的体験のない六歳とか七歳の子供についてこれが当てはまるのかどうか、よくわからない。
木村 日本の場合、笙とか、篳篥(ひちりき)の音を左の脳で受けとるわけですね。ということは、音楽的なものを左でも受けとっているわけです。左を言語脳、右を音楽脳という区別は、西欧人の区別で、その分け方が日本人の場合もはたして妥当なのかどうか。
角田先生は右の脳が西洋音楽の器楽曲を受け入れる、とおっしゃっています。しかしそれは、日本人の感覚になじまない音が右に入っているだけ、ともいえる。若いときにクラシックかジャズに夢中になっても、やがて憑き物が落ちるみたいに離れてしまう人が多い日本人の場合、本当に左半球を音楽脳といえるのでしょうか。
丸谷 レヴィ・ストロース以後の考え方でいくと、あの命名はおかしいわけね。
各民族は各民族の文化をもっていて、それはそれでちゃんとしたものだ、それを西欧優先でいくのはおかしい、という考え方をとると、右が音楽脳って考え方は、西欧に限定された思考ですよね。
木村 最後のところで、右の脳と左の脳のバランスを取ることが大事だと書いてありますが、日本人の考え方が左に片寄っているために、科学的な思考に不向きであるような印象を、この本からは何となく感じます。しかし、現代の科学というのは、直感と、きわめて繊細な感覚を実は必要としていて、たとえば日本人がエレベーターをつくると、西欧人は感嘆するわけです。羽根ぶとんの上に停まるようにソフトランディングして、床と一分の狂いもない。日本のコンピューターを使うと、預金通帳の数字がピタッと揃うわけです。ところが、アメリカのコンピューターだと、万の単位、千の単位が○・五ミリくらい多少デコボコするんですって。こういった日本人の繊細さというのは、科学に生きているわけですね。
丸谷 でも、これを読んでいろいろ思い当ったことがありました。たとえば西洋音楽を聴くには特殊な訓練が必要だ、と書いてありますね。
新潟の高等学校には清和寮という、別格の寮があったんです。そこの応接間に電蓄があり、名曲がズラーッと揃っていました。まあ金のかからない名曲喫茶ですね。
山崎 それでこういう文化人が生まれたわけです(笑)。
丸谷 つまり、旧制高等学校がぜひ仕込まなきゃならなかったのは、むずかしい本を読ませること、もう一つは西洋音楽を聴かせることなんですよ。それも強制的に聴かせるくらいにしないと、日本の知識人はできあがらなかったんですね。
新潟高校の初代校長は八田三喜ですけれども、大教育者だからこそ思いついた仕掛けじゃないかと思って、驚嘆したんです。
第二に、日本人はなぜベートーベンの「第九シンフォニー」があれほど好きなのか、ぼくはよくわからなかった。この本を読んだら、あ、「第九」を好きなのは人間の声が入っているからだ、人間の声であれば、外国語であってもいいんだ、ということがわかったんですよ。
山崎 最初に丸谷さんがこの本を紹介されたときに、左側の頭脳は言語および論理能力を扱うものだ、と要約されましたが、ちょっと異を立てますと、普通考えられているように、言語と論理というものは、全面的に重なるものではないんじゃないかと思うんです。論理の機能というのは、じつは数学にも現われるもので、言語がなくても活動できるわけですね。数学というのはボキャブラリーのきわめて少ない言語で、ゼロから十までしかない。それだけの単語を使って、あれほど高度の論理構造をつくることができるわけです。
裏返していえば、言語の機能のうち論理の占める位置は、非常に小さいのではないかと思うんです。残る言語の機能とは何かといえば、すぐ思いつくのは、いろいろな感覚現象をパターンとしてとらえる能力です。ニワトリの鳴き声というのは無限に複雑な音ですけれども、それをコケコッコーという「型」としてとらえる。そのときに、コケコッコーは擬声語という言語になったわけですね。
このパターン化の能力というのが、言語の非常に重大なもう一つの機能であって、日本人において特に発達しているのは、そっちのほうではないかと思う。そうすると、日本人がなぜこれほど擬態語、擬声語を発達させたかということがよくわかるわけです。音のしないものについてまで「音」を発明している。
木村 「シーン」とか。
山崎 ニョロニョロ、ヌルヌルとか、最後には「雪がしんしんと降る」というのまで発明しているわけですね。これはパターン化の能力ですよ。
そうすると、左側の頭脳が受けもっているのは、じつは、パターン化の機能なのであって、それが笙、篳篥の音から虫の声まで、人間的表情を帯びた信号としてパターン化して受けとっていると考えられます。いいかえれば、右側の頭脳が感覚的な音を受けとる前にそれを擬声語としてひっさらってしまう、というふうに見ると、わりあいすっきりするんじゃないでしょうか。
木村 日本人は音を文字に変えて受けとるわけかしら。
山崎 そうなんです。ですから早い話が、日本人は自己紹介をするとき、名刺を交換して相手の名前が字に書いてあると、非常に安心して覚えるんですね。ところが西欧人は名前を耳で聞いて、それを音のままで覚えますよ。
つまり音がパターン化される前に、複雑な音をそのものとして覚えられるんですね。だから、おかしな発音でわたくしの名前を口にしますが、とにかくだれであるかわかる。
丸谷 ところで、この本の対談の章に、
餌取 秋に虫が鳴くのを意識して聞くというのは、そうしてみると日本人だけの持つ風流さなのですね。
角田 ええ、中国人にさえ通じないようですよ
とあるでしょう。とすると、昔の中国人といまの中国人、違っちゃったのかしら。虫の音を聴く風流っていうのは、漢詩を読んでわれわれが教わったものでしょう。
木村 そうですね。
丸谷 それがいつの頃からでしょうか、中国人は虫の音を聴くことを忘れちゃって、日本人だけが虫の音を聴いて「ああ、わびしいなあ」なんていって聞きほれる。こういうことになったとすると、これはたいへんな衝撃ね。感受性の移りかわりの歴史というのは、じつに強烈な感銘を与えるんですね。
山崎 だから、人間というのは非常に不思議なものだということがわかったことが、最大の収穫じゃないですか。
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする