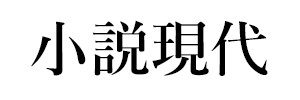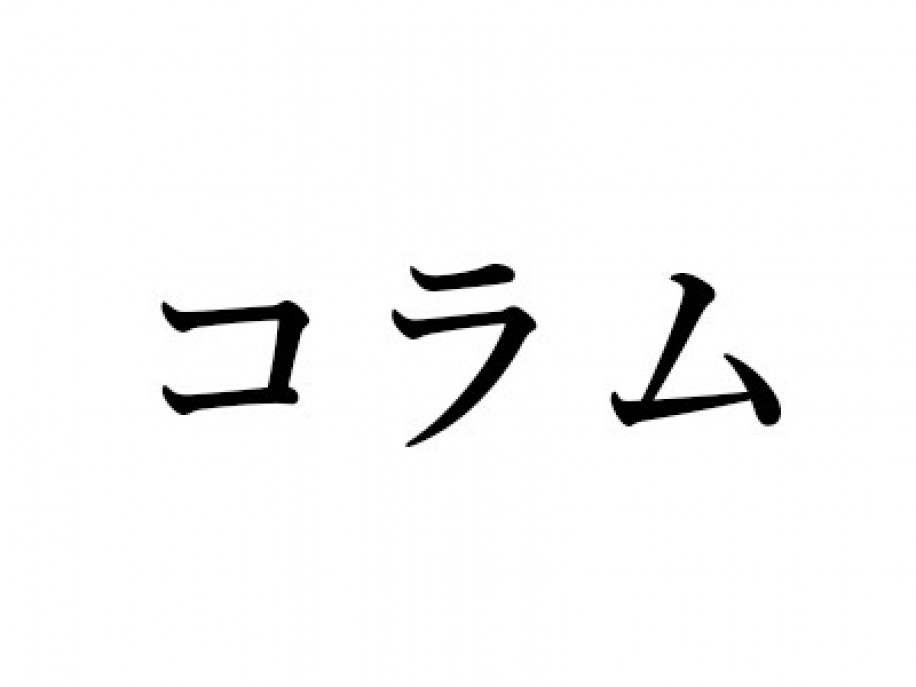コラム
すれ違う妻と夫―堀口雅子『35歳からの女のからだノート』、式田和子著『死ぬまでになすべきこと』、中国新聞文化部編『妻の王国』
すれ違う妻と夫
妻が熱を出して寝込んだとき、夫のあり方が試される。そういう内容の記事が、週刊誌に載っていた。「ごめん、食事の支度できそうにない」と言う妻に、「いいよ、僕は外で食べてくるから」と答えたアナタ、遠からず離婚の危機が訪れるかも知れません、と。「あー、ありがち」
深くうなずいた。
ちょうどその少し前、新聞に、病弱のため家事のできなくなった妻を虐待した老人のニュースが出ていた。身体的危害を加えられなくても、言葉によって深く深く傷ついたという、五十代の主婦からの投書もあった。彼女はやはり体が弱く、寝込みがち。その妻を、夫はいたわるでもなく「使用期限切れの、とんだお荷物を背負わされたものだな」と言い放ったという。
「妻を、家事をする機械だとも思っているのか!」
読むだけで、怒りがこみ上げてきたものだ。
彼らに比べれば、冒頭のような言葉をかける男たちは、「なんとやさしく、理解ある夫であることよ」と、われながら百点満点のつもりかも知れない。そこが大きなすれ違い。
妻の心の中の叫びは、「私のご飯はどうなるの?」。
熟年離婚が急増中と言うが、妻にしたら突然のことではなく、そうした不満が積もり積もってのことだろう。何で読んだか忘れたが、夫が定年を迎え、会社での最後の一日を終え、帰宅していつものように「フロ、メシ」だけ言って風呂に飛び込んだところ、なんと水風呂であった。妻いわく「私も本日をもちまして、主婦を退職させていただきます」。
浴槽を空にしておかず、わざと水を張り、夫に文字どおり「冷水を浴びせる」ところに、積年の恨みのすさまじさを感じる。
熟年で離婚に至るには、たぶんその前の更年期を夫婦がどう過ごしたかも、大きな要因だろう。更年期障害は、これまで女性たちの間でも、あまり声高に語られなかった部分である。婦人科医の堀口雅子著『35歳からの女のからだノート』(新潮OH!文庫)によれば、日本人の平均閉経年齢は五十歳。前後には、さまざまな体の不調が現れやすい。その時期、夫がよくサポートしてくれたと語る人もいれば、夫がよけいストレスをかけたという人もいる。
そもそも更年期にともなう症状は、ホルモンのアンバランスがひきおこす身体的なもので、「気の持ちようで乗り越えろ」などという精神論ではすまない。また、その時期は膣が乾燥し、性交に痛みが生じやすいとか。うーむ、そのあたり夫が無理解だと、夫婦間の亀裂はさらに広がりそう。
(こういう本は男性にもようく読んでもらい、正しい知識を持ってほしいものだわ)
と強く思った。
式田和子著『死ぬまでになすべきこと』(角川文庫)に出てくる妻の例も強烈だ。七十代の女性の友人が、長患いの夫の看取りを終えた。友人の家へ通夜の弔問に出向くと、帰りがけ友人が玄関まで追いかけてきて、
「ねッ、こんどから旅行へ行くときは私を誘うの忘れないでちょうだいね!」
この本、タイトルと、一九二五年生まれ、東京府立第三高女卒なる著者の経歴からして、「貞女たるもの、身を慎み、欲を戒め、後の者たちに迷惑のかからぬように……」といった感じの教えかと思ったら、そういう知恵もあることはあるけれど、出てくる例が、もっとどろどろして具体的。
妻任せで自分では何もしなかった夫に、葬儀や親戚関係いっさいがっさいの面倒くささをたっぷりと思い知らせてやるために、「絶対に亭主より先に死んでやる」を生きがい(?)としている婦人も登場する。話は深刻だが、文章はテンポよく、ユーモアのあるのが救いだ。
著者によれば、夫亡き後の妻の生き方は二つあり、これはもう、はっきりと分かれる。
落ち込んでメゲてどうにもならないタイプと、ひとりでのんびりやるタイプ。意外なのは、どちらになるかは、夫婦仲のよさと関係がないそうだ。「その女性の自立心の問題」と著者は言う。
なるほどな。わかる気がする。一般的に妻に先立たれた夫の方が、逆よりダメージが大きいのも、自立心の問題か。何といっても日常生活における妻への依存度が高いから。
夫側の声も聞こう。そう思い本屋へ行ってみたけれど、熟年男性の書いた本は「定年後、生きがいをみつけ、いかに充実して過ごしているか」といった、セカンドライフを誇る話や、介護がらみがほとんど。妻にしっぺ返しをくらってズタボロだ、みたいな情けない話は、なかなか出ない。そのへんが、今の高齢者の男性の限界か?
もうちょっと若い層になるけれど、中国新聞文化部編の『妻の王国』(ネスコ・文庫版は文藝春秋)は面白い。家にあって男たちは「粗大ごみ」「ぬれ落ち葉」扱いされ、メディアでもさんざんコケにされてきた。「ぬれ落ち葉」とは、退職後することのない夫が、妻にべったりつきまとうこと。
子育て期は、趣味にお金と時間を使いたくても、妻に遠慮し、仕事以外の世界を持てずにいる。それでいて、定年後「ぬれ落ち葉」呼ばわりされては、たまらない。そんな言い分を、三十代、四十代の男性から取材した。
家庭内では妻が制定したルールを守らされ、忍従する夫たち。オシッコも、立ってするとあたりに飛び散り掃除がたいへんになるから「座ってして」と命ぜられる。帰宅後は、靴下が汚れているから、膝でハイハイし風呂場へ直行……。
「ほんと?」
と驚くような、妻の「暴君」ぶりがあきらかにされる。彼らに言わせれば、熟年離婚だって、言い出したい夫は多いだろうが、妻を放り出すに忍びず我慢しているだけ、という声も。
新聞連載中に寄せられたという、女性からの反論も本書にはおさめ、バランスをとろうとする努力は感じられる。なぜそうなるかの、社会史的分析を試みてもいる。核家族化で「イエ」の権威はなくなり、ワーカホリック批判により「仕事」という大義名分も失った夫たちは、従来と違い、何の後ろ盾もなく、妻と向き合わねばならなくなった、と。夫婦間の意思の疎通の不十分には、日本人の討論ベタが、男女ともに共通してあり、それを検証せずして、「性差」にだけ原因を求めるのは問題、という女性読者からの指摘も、なるほどだった。
すれ違う妻と夫。解消には、「自立心」や「言葉によるコミュニケーション」あたりがキイワードとなるのだろうか。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする