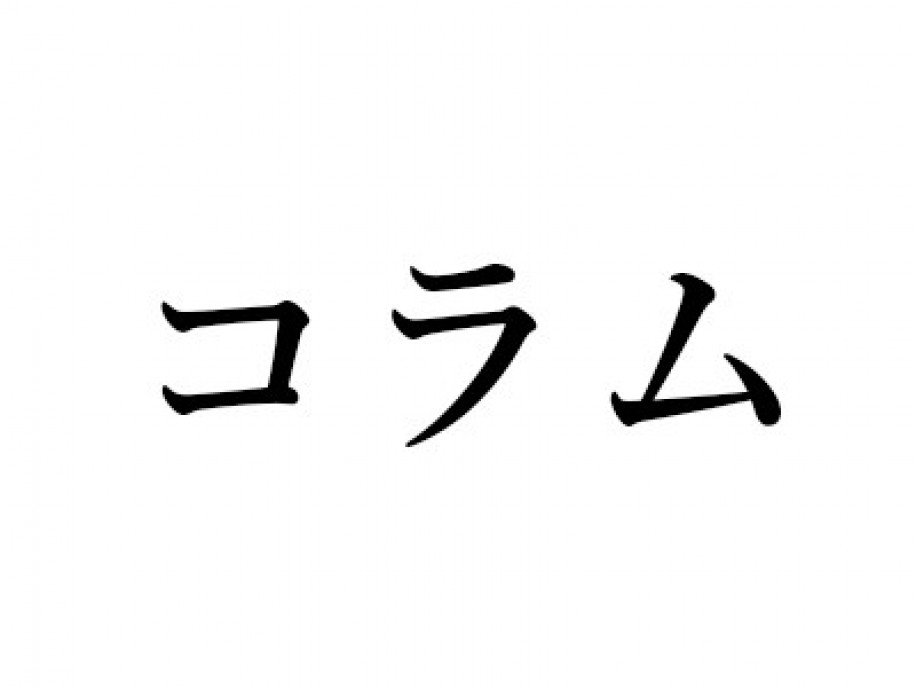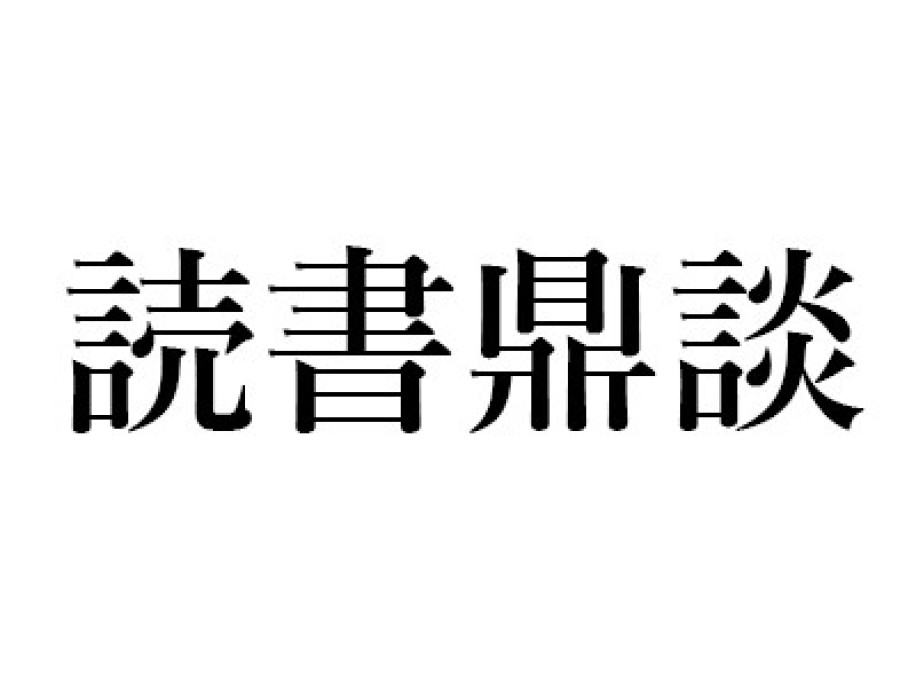書評
『そして夫と姑が残った: 子が巣立ち、試練が始まる』(主婦と生活社)
“家族からの卒業”図る奮闘
矛盾のかたまりである“家族”。著者は「心の奥底では、職業と家族のある生活は、両立などあり得ない」と思いつつも、「家庭というある種のカオス(天地創造以来の大混乱)を体験してこそ、その後、キャリアのうえでも不思議な力を与えられる……女は女以上の人格になる」と矛盾したことを娘につぶやく自分自身を想像する。かつて「父のいる食卓」で、昭和戦前期の束の間の充足を鮮やかに描き出した名エッセイストの、これは平成高齢化時代へむけての“女性の政治学”だ。姑と夫婦と子供とから成る濃密なつながりを前提とした“家族からの卒業”が、子離れの後あってもよいのではないか。家族が時代と共に息づいていたのは、新しい時代の知識を毎日家に持ち込んだ子供のいたあいだだけだ。時代の変化への対応は、子供が出ていった後はかなりきつい。
姑と夫が残った家の中で、著者の思いはまず過去の女性男性へと遡(さかのぼ)る。戦後質素倹約だった時代の日本には、「子供、子供」で時間を超越して暮らす大型の女たちが満ちあふれていたし、威張ってはいるが女性を上まわる生活的ノウハウを持った明治生まれの男たちがいた。今の一億総中流社会に、それらは望むべくもない。
次いで著者の思いは安易かつ気楽な結婚を望む最近の若い女性の情けなさに及ぶ。しかし子供の幸せは母乳で二十四時間育てることにつきるとの確信もある。これは確かに、仕事と家庭との両立を望む女性にとっての永遠の矛盾に他ならない。
では家族をどうやって卒業するのか。アメリカ移住をも視野に入れる著者は、時間の主導権の掌握と心地よい良質の孤独の確保を優先させる。いきつく先は「子供が親の親になる」ことであった。そのために姑と夫と自分が、「ホテル型自主独立ワンルーム」を各々所有する新築プロジェクトを推進することになる。“家族からの卒業”をめざす著者の健闘ぶりを、硬質な文体の中でじっくりと味わいたい。
ALL REVIEWSをフォローする