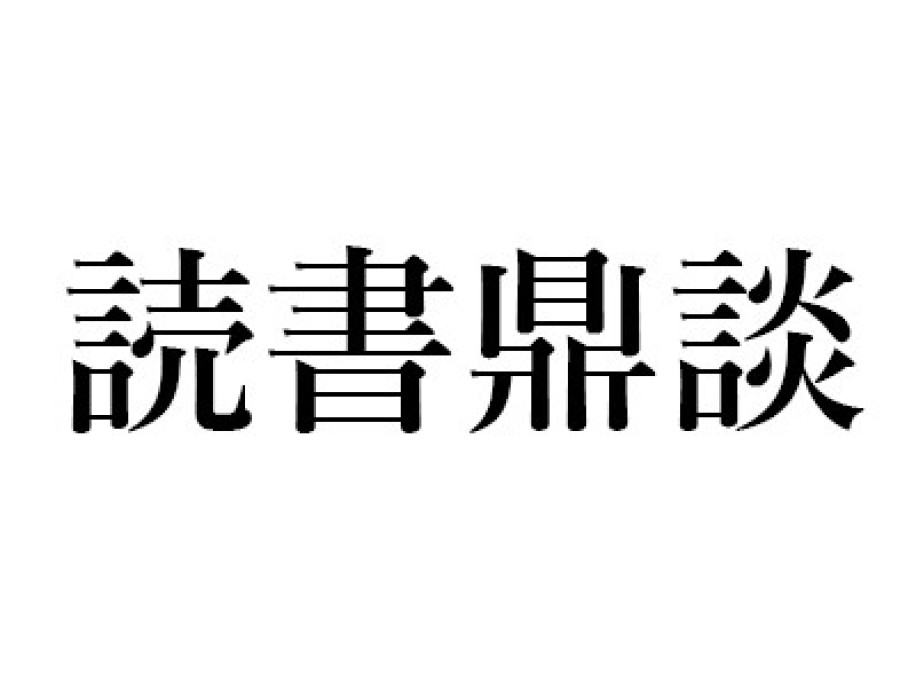書評
『私たちはいつから「孤独」になったのか』(みすず書房)
近代社会が生んだ新しい感情「群」の諸相
いまや孤独は、全世界的な社会問題だ。イギリスが二〇一八年に孤独担当大臣を創設したことは大きく報道された。孤独は言わば、新自由主義時代の疫病のようなものである。それは大流行し、蔓延し伝播する。本書で検討されるのは、そうした「孤独」の歴史である。「孤独」が、実は十八世紀以降に生まれた近代的な感情状態だ、という指摘には意表を衝かれる。著者は過去の文献の詳細な検討から、この結論を導き出す。ここで言われる孤独(ロンリネス)は、単に一人でいる状態(ワンリネス)とも、積極的に選ばれた隠遁などを意味するソリチュードとも異なる。疎外感や居場所のなさといった主観的感覚を意味する言葉だ。著者は孤独を感情の「群(クラスター)」と呼ぶ。恥、怒り、悲しみなど、さまざまな感情が含まれるからだ。
十八世紀以前の古典文学に現れる「孤独」は、ソリチュードに近いという。日本の古典文学でも隠棲や独り寝の侘しさなどは描かれるが、あれもソリチュードに近い感慨なのだろう。『ロビンソン・クルーソー』には孤独は描かれないが、現代の漂流譚である映画『キャスト・アウェイ』には孤独が描かれるという対比は興味深い。
著者によれば、こうした「孤独」の前景化は、社会の構造的変化の帰結である。人口の増加、グローバル化、都市型で流動性の高い労働力、そうした変化が独居世帯を増加させ、それが孤独の遍在化をもたらした。加えて、孤独をやわらげるはずの信仰心が、世俗主義に取って代わられたことも少なからず影響した。
著者は孤独の発生と受容を、多角的に描き出す。ロマン主義的理想としての「ソウル・メイト(魂の伴侶)」という概念の果たした役割が、古典の『嵐が丘』から現代の『トワイライト』シリーズまでを例にとって記述される。この概念が「孤独」に、理想的なパートナーを得られないこと(失うこと)、という意味を付与したのだ。
ならば、ソウルメイトを失った人間の孤独はどのようなものか。「ウィンザーの寡婦」と呼ばれたヴィクトリア女王(一八一九~一九〇一年)は、最愛の夫であるアルバート公と死別した後、悲嘆のあまりその後の生涯の四〇年間を喪に服した。彼女が遺した膨大な日記は、喪失の孤独がいかなる経験であるかを知る上で貴重な資料となっている。
本書でことのほか興味深いのは、ソーシャルメディアと孤独の関係を扱った章だろう。本来人々のつながりをもたらすはずのSNSが、逆説的にも人々の孤独感を増大させているということ。著者は、社会と関わる手段がSNSしかない場合に孤独感が増大するとして、現実の人間関係を補完するような使い方を推奨する。
そのほか本書では、高齢者やホームレスの孤独についても、鋭い議論が展開される。とりわけ認知症の人が時折感じる「自分とほかの人たちとのあいだに埋めがたい溝ができてしまった」かのような孤独感についての示唆は臨床的にも重要である。
評者が専門とする「ひきこもり」も、おそらく近代以降の現象なのだろう。ひきこもりは自己疎外と社会的疎外が重なり合う、特異な孤独の形態だ。直接の言及はないものの、本書はひきこもりを考える上でも多くのヒントを与えてくれる。
ALL REVIEWSをフォローする