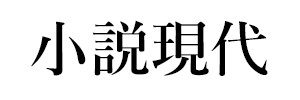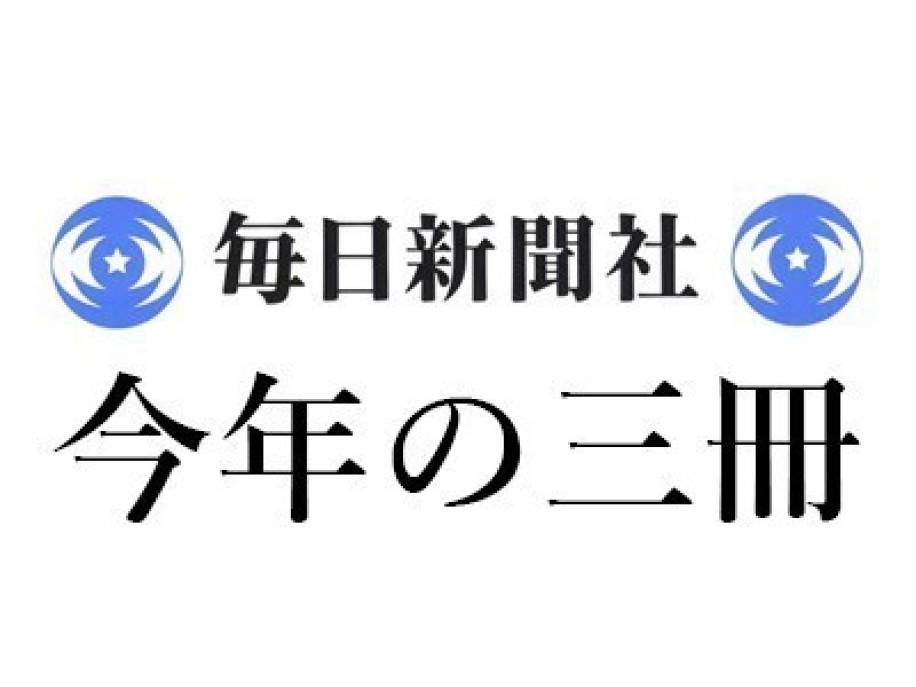読書日記
大平光代『だから、あなたも生きぬいて』(講談社)、武田麻弓『ファイト!』(幻冬舎)、マーシャ,ダーシャ『マーシャとダーシャ』(講談社)
あきらめない人生
ある朝、お茶を飲みながら、いつものようにぼーっと新聞をめくっていたら、「えっ」と思う見出しが目に入った。「いじめ→自殺未遂→組長の妻」。そういう経歴を持つ女性が、二十二歳から猛勉強して弁護士となり、非行少年の立ち直りに力を尽くしていると。『だから、あなたも生きぬいて』(講談社文庫)の著者、大平光代さんである。(そんな人がいるのか)
と、まず驚いた。のんべんだらりと暮らしている自分に、活を入れられる思い。
それにしても、司法試験は難関中の難関の試験。漢字もろくすっぽ読めないレベルからはじめ、一発で合格するなんて。思わず本を買ってしまった。
中二のときいじめで割腹自殺を図ってから、非行に走り、十六歳にして「極道の妻」に。表紙の写真は、知的で清楚な感じの女性で、とてもそんなおどろおどろしい過去があったとは信じがたい。
いけない興味の持ち方だとは思いつつ、口絵にある幼少時の写真を、まじまじと眺めてしまった。赤ちゃんのとき母親に抱かれて。七五三。家族旅行のスナップ。どの一枚をとっても、ごくふつうに愛情を受けて育っている子どもで、この後に、地獄のような日々があろうとは、家族の誰も想像だに、できなかったろう。
「いじめというものは、いじめられた者の人生を大きく狂わす」。「はじめに」で著者は記す。「受ける側の人間性を否定するものと言っても過言ではない」。いじめという行為の残酷さ、けっして許されるものではないこと。幸せな頃の写真の直後にあるだけに、胸に響く。なかなかに考えられた構成だ。
はじまりは、ほんのささいなことだった。同級生の女の子が話しかけてきたのに気づかず、返事をしなかった。無視される、机の上をゴミだらけにされる、トイレに入れば上から水をかけられる。いじめはどんどんエスカレートしていく。
読んで、後から時系列をたどれば、
(あそこで、まわりが別の対応をしていたら)
と思うところが、いくつもある。教師がいじめる側に対しもっと断固とした態度をとっていたら、親が世間体よりもまず、子どもの心と正面から向き合っていたら、その後の道も違ったものを、と。が、転換点となるべきところで、そのつどずれて、冒頭で述べたような道すじに。
立ち直りのきっかけを与えてくれたのは、父の友人である、現在の養父。離婚後、働いていたクラブに、客としてやって来た。説得を重ね、ある日はげしく怒鳴りつけられ、「生まれて初めて叱られたような気がし」て、体が震え、泣き崩れた。再生の第一歩となるシーンである。
この本が児童書として出版されたわけが、よくわかる。極道の妻から弁護士にという経歴がめずらしくて読む人も多いだろうが(私もそうだった)、著者のテーマは「少年問題」。大人の読者に対しては、子どもたちの心に周囲が真剣に向き合うことのだいじさを、子どもたちに向けては、あきらめてはいけないと、訴える。
著者の背中には、極道の妻時代に入れた刺青があるという。司法試験に合格して「めでたし」ではなく、過去の事実は事実として背負ったまま、自分にできることは何かと、模索している。本の最後にも書いているように、著者にとっては常に「今」が「出発点」なのだ。
武田麻弓著『ファイト!』(幻冬舎)の表紙の女性は、これまたぐっと違った雰囲気。
ガングロ、ピアス。そして、とびきり明るい笑顔。考えてみれば、このテのノンフィクションは、著者の写真が表紙のものが多い。さきに書いた「いけない興味」のように、
「えっ、こんな顔の人が、そんな体験を」
とのギャップへの驚きから、読者をひきつけるためなのか。
この人の人生も、ジェットコースターだ。三歳のときに聴力を失い、六歳でレイプされ、一流企業に就職するもヘルス嬢に転身、ろう唖の風俗嬢「豹ちゃん」として名を馳せた。恋人を追っていったアメリカで、別の男性と電撃婚。だが彼はギャングで、しかもHIV感染者だった。
「そりゃ、結婚そのものが、あまりに軽はずみなんだよ」
と言いたくなる。「おおおお、わたしは知らないうちに、ハーレムの住人になっていたのだ!」って、まったく……。夫に何度も殺されそうになりながら、トップレスダンサーとしてやり直し、離婚調停中に出会った男性と恋愛、出産。
ほめられた生き方ではないかも知れない、が、この人、考え方が常にポジティブなのだ。
幸せをつかみたいと豊胸手術し、ヘルス嬢になったのも、きれいになった体でばんばんお金を稼ぎ、アメリカへの移住、その足がかりとしてロサンゼルスに留学する夢を実現したかったからという。障害を恨み、「弱くて泣き虫だったわたし」「今はただ、生きるのを諦めなかった自分に本当に感謝している」。
次に挙げる本の表紙写真はショッキングだ。下半身が結合した状態で生まれた双子の姉妹マーシャとダーシャが、交互に語り手となり、来し方を振り返った『マーシャとダーシャ』(講談社)。
旧ソ連のモスクワ生まれ。生後すぐ親から引き離され、科学者たちの実験材料となった。研究所、養護学校と転々とし、二十歳の若さで老人ホームへ。完全無欠をうたうソ連には建前上、障害者はいないものとされたため、社会には居場所がなかったのだ。
それでも、二人は自分たちの意志で、状況を変えていく。実験を拒否し、少しでも人間らしい環境を求め、軍に直訴したり。「こうしろ、ああしろ、ここに住め、あそこに住めと命令されて生きてきた」けれども「これはわたしたちの人生なのだから」。ペレストロイカ以後は、マスコミを巻き込んで、自分たちの主張を訴える。
おとなしくロマンチストのダーシャと、乱暴者でリアリストのマーシャ。
(双子でもずいぶん性格が違うものだな。マーシャがお姉さんだろうな。そもそも双子って、先に生まれた方が上なんだっけ下なんだっけ……)
と考えかけて、ハッとする。先も後もない、一体だった。そのことを、うっかり忘れてしまうほど、それぞれの語りは個性的だ。
どきっとする話もある。ダーシャが初恋の少年と、キスまで進んだとき、マーシャは思う。二人が結婚したいと言い出したら「わたしは好きでもない男とセックスすることになるのか?」。そんな話題にもタブーなしにふれる、ウィットあふれる語り口が、この本の魅力だ。
ダーシャが自殺を図るたび、マーシャはこっぴどく叱りつけてきた。けれども「ダーシャのやさしさがなければ、わたしもどこかでくじけてしまったかもしれない」。想像を絶する困難と差別をはね返して生き続け、二人は五十歳を迎えたという。
あきらめない人生。しかし、こうした壮絶な体験を書いた本がどんどん出ると、ちっとやそっとのことには、ものを感じなくなってしまいそうで、少し怖い。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする