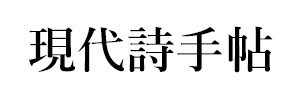コラム
吉本隆明はメディアである
1
吉本隆明氏(以下敬称略)のさぼり気味の読者でしかない私が、特集の執筆依頼を受けてしまった。「メディアと社会システム」につき、社会学的に論ずるように、という。そこで、『重層的な非決定へ』、『マス・イメージ論』、連載中の「ハイ・イメージ論」、そのほかを、読みとおしてみる。そしてー。
まずひと安心。吉本は、健在である。脳軟化の声も一部にあるようだが、まあ根も葉もなかろう。文体も相変わらず。そして、書くものの量の多さも(多すぎだ!)。
にもかかわらず。吉本にはどこか、変化がみえる。言ってることが、新しくなったとかいうのではない。そうではなくて、吉本自身が〈新しいもの〉に、特になみなみならぬ関心を示すようになっている。そこがまた目新しくて、注目を集めているらしい。それでこの特集になったのか。……と納得がいく。
*
俺はこの二十年間、一線に出ずっぱりなんだぞ。と、どこかで吉本がタンカをきっていた。たしかにそりゃ、大したことだ。社会党がダサかったり、知識人が無学だったり、を背景にすると、ひときわ光るというものだ。
最近の彼の仕事は、それなりに面白いし、刺激的である。でもね。「吉本さんすごいですね、社会はこうも変わっていくんですか、いやぁ勉強になりました」と、おだてあげる気にはならない。そんなことより、別の疑問が、だんだん頭をもたげてくる。なぜ彼は、こんなに〈新しいもの〉に吸引されるのか? またどうして、そんな吉本がみんなのなかでいちばん現代的だ(それ以上に現代的な知のありかたが見つからない)、という構図になってしまうのか? それに最近よく言う、「アジア的」っていったいどういうことなんだ。そりゃあないでしょう、吉本さん?!
こうなれば、編集部の依頼の筋などうっちゃらかして、生意気を言わせてもらおう。私が彼に何を言っても、生意気にならずに済むわけないんだから、いまさら悪びれることはない。
2
「ハイ・イメージ論」のなかでは、「映像都市論」が印象的だった。吉本のモチーフがよく現れている。というよりこれは、最近の彼の自画像になっているのではないか。吉本が愛着してみせるのは、映画『ブレード・ランナー』の、近未来都市の映像だ。その映像を斬新にしているのは、上方からの視線(世界視線)である。ポイントは、《この世界視線を高層ビルのすぐ上方を飛ぶ空中カーからの視線として作れる場合でも、この空中カーをさらに上方からみている視線を設定して、空中カーとその下の高層ビルを同時に鳥瞰する映像を作ることだ》(『海燕』八六年一月号)。この世界視線はあとで、人工衛星ランドサットの位置にまで高められ、地質学的な過去と未来を、如実に見取るものとなる。
こうした指摘は映像技法からみて、当をえているのだろう。しかし私は、それはさておき、この空中カーを吉本(の占める位置)と考えたくなった。そう読みかえてみると、こうなるはずだーポイントは、「この世界視線を近未来社会のすぐ近くを生きる吉本(ないし知識人誰でも)の視線(世界認識)として作れる場合でも、彼をさらに上方からみている視線を設定して、彼と近未来社会を同時に鳥瞰する構図をつくることだ」。吉本は、自分の背に、同時代の人びと(読者)が与える「世界視線」を感じている。だからこそ「ハイ・イメージ論」を、もっとも先端的な知の光景として、自信をもって構成できているのではないか。そう、思われる。
*
世界視線と対極的なものに、普遍視線があり、原っぱのような空き地の地べたから、上方に向けてつき出ているのだという。このあたりから議論は錯綜してきて、私の頭ではすっきり理解が行きとどかない。だがこれが、超近代的なもの/アジア的なもの、という対比と繫がっていることは、わかる。
吉本が未来社会を遠望するとき、なぜ世界視線を背にすることを有効と感じるか? それはたぶん、彼が、客観的な歴史というものを信じたことがあるからだ。マルクス主義の描くような、客観的・目的論的に確定した歴史のルートーこれが信じられれば、未来の存在と方向は明らかである。それは、資本主義の向こうに、ない。それがどんなに豊かで、矢のように進歩していくとみえても。しかし、この歴史を信じつづけるためには、今日、あまりにも多くのことに目をつぶり、不条理な教条の鎧を身にまとわなければならない。どうにも、苦しすぎる。
そこで、この歴史の外に出てしまう。と、その途端に、こんどはすべてが現象の渦巻きとみえるだろう。
現象の渦巻くところ。そこでは、同時代が互いに覗きこみあう構造(情報化)がうまれ(それしかうまれず)、メディアがそれを加速する。過去の健忘症+未来への本質的無関心。関心が同時代へ圧着される。新人類の基礎的症侯群。
こうしたなかで吉本は、まだ客観的歴史の記憶を保っている。それをどうにか、この時代の足許から発掘しようとする視線を手放さない。そういえば彼は、宮沢賢治と同じ、自然科学の訓練を受けたのだ。ランドサットからの空間的視線がもたらす、時間の拡張。ここに流れる時間はもともと、歴史を堆積してゆく社会過程と関係がない。それでも吉本は、同時代を離脱する方法を手にしたと気をよくする。ただしこれは、「批判的」方法でない。現象を現象のサイズのまま、自在に(重層的に)観察・記述するばかりだ。背に世界視線を負いながら。あたかも、空中カーのように。
*
この構図によると、吉本が注目を集めるのは、彼がなにか、近未来について「新しいこと」を教えてくれるからではない。二次資料を使っているのだから、どこかで聞いたことのある話がほとんどだ。そうではなくて、ほかならぬ彼が、いまのべたような脱イデオロギー的空中姿勢をとり、観察・記述をおこなう(ようにして社会を眺める)ことが「新しい」のである。そのため、彼は現在見聞きすることをのべるだけなのに、それが近未来の報告のように思われてくる。
ではなぜ、吉本ばかりが、世界視線の所在を感知できるのだろう? それは、逆説的だが、彼が「アジア的」ということを信じているからだ、と思われる。これはかつて、歴史が出発するまえの原点の位置を与えられていた。それゆえ、歴史が疑われるようになっても無傷なのである。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする