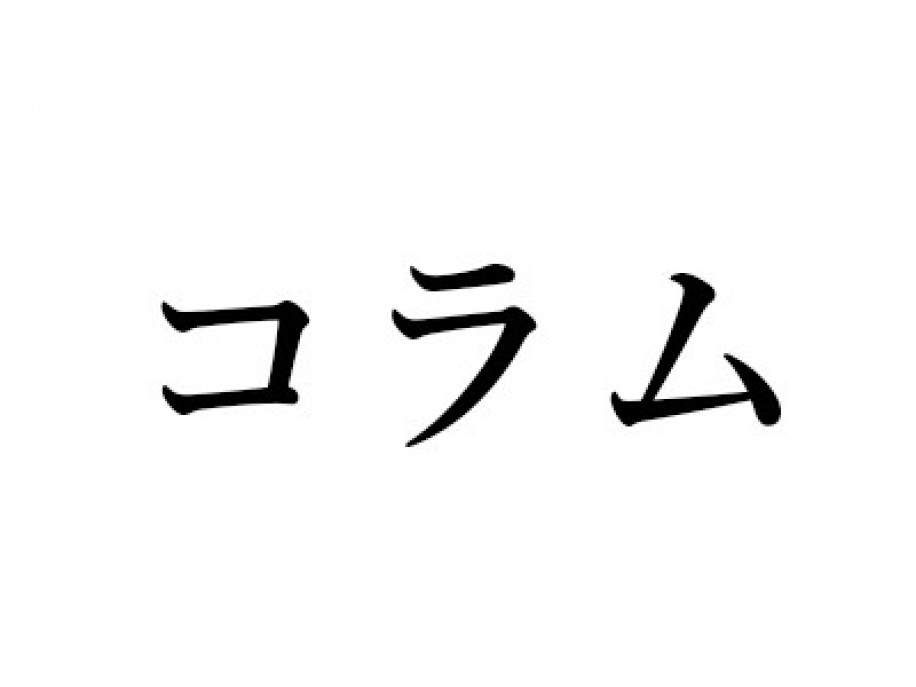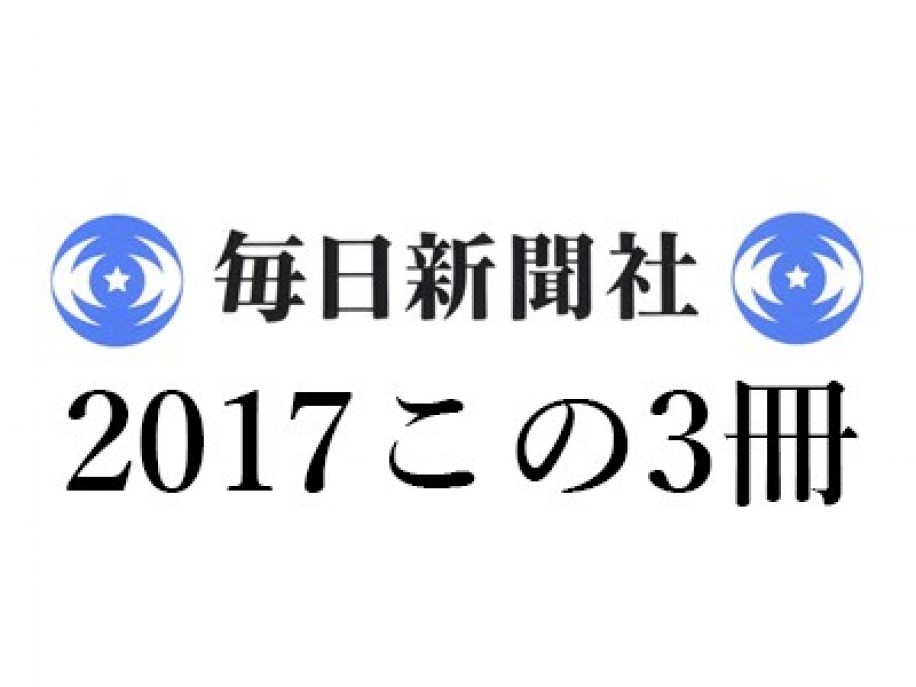書評
『思想の危険について―吉本隆明のたどった軌跡』(インパクト出版会)
吉本隆明に関する著書は数多いが、期待外れが目立った。最近はいちいち読んでもいない。この書はどうであろうか。
著者田川建三氏は、キリスト教学の研究者としてつとに名を知られ、吉本氏とも幾度か交流があった由である。
題名から窺えるように、これは思想家吉本に対する諫言の書とみられる。当然、読書の興味は、吉本が陥ったという「危険」を、著者がどう抉りだし、そこに納得できる説明を与えてくれたかに集まるだろう。
一九六〇年頃の吉本を、著者は高く評価し、それがその後だんだんよからぬ方向に変わってきた、とみる。いわば、吉本「変節」論である。そこで転換点(こけたきっかけ)が探られるわけだが、それが『最後の親鸞』と『共同幻想論』だという。この二書の検討が、大部な本書の前半、後半を占め、間に『反核異論』やイリイチに絡めた批判がちりばめられている。
著者田川氏には少々失礼かもしれないが、ごく大づかみに論点を整理させてもらおう。著者はいう。吉本の親鸞論がまずいのは、吉本が宗教者としての親鸞の実像にもとづかないで、勝手に自分の思想的境位(自分が知識人として大衆から離反してしまい困るので、なんとか大衆になりきりたい)を投影しているにすぎない点である。また共同幻想論がまずいのは、彼の理論と素材とがちぐはぐで論証の体裁をなしていないうえ、理論は理論で、共同性をはなから敵視して国家と同一視したり、女性蔑視まるだしの対幻想の概念を持ち出したりという程度の、おそまつなものでしかない点である。
では、どうしてこんなことになるのか?
著者によると、それは吉本が初心を忘れたからである。
「我々大衆」という位置から戦後派知識人を鋭く告発する当初の姿勢は傑出していたのに、だんだんと理論志向にとらわれ、抽象的な図式にすべてを押しこめてことたれりとする歪んだ態度に迷いこんでしまった。
ではどうすればよいのか。
著者は、初期吉本の優れた仕事のなかにも後々のよからぬ傾向が潜んでいた、と注意し、彼の一貫した一面も見落としていない。ならばそのうえで、どんな可能性が吉本に残されていたというのか、本書からはなかなか読み取りにくかった。それでも、著者が思想家吉本のどこに問題をみているかは十分伝わってくるし、それが吉本読者のよくある反応の一典型になっていそうなこともわかる。
さて、著者の批判は、どこまで急所を突いているだろうか。これは私(評者)の判断だが、本書の論法では吉本を捕まえたことにならないと思う。
なるほど、著者の指摘の半分近くは納得できるものである。私は吉本のあまりよい読者ではないが、私なりに考えてもたしかに吉本には問題がある。しかし率直に言って、著者の議論は総じて大味で、私がいちばん知りたいと思うところを突いてくれなかった。性急な倫理的追究に力点がかかるあまり、吉本の思想的全体像を捉えない(それに興味を示すだけの余裕がない)ままで終わっている。
吉本を語るなら、多作な彼のスピードのようなものをまず押さえないとダメである。
彼はただの文学者でいたいのに、同時に、時代と状況に応答する体系的思想家の役回りも引き受けざるをえなかったため、忙しいのだ。体系への志向を見なければ、彼のユニークなところが台なしである。『言語にとって美とは何か』、『心的現象論』、それに『ハイ・イメージ論』あたりも踏まえて、自らも変化しつつわれわれの時代を語り出す吉本の全体像を描き出すこと。変節ではなく、内在的な必然として。
これを望みたかった。
著者の批判はテキストに密着しているようでいて、その実、細部にこだわりきれていない。吉本の体系的な展開がみえていない(というより、著者が現代にかかわる自分自身の思想的脈絡をよく整備できていない?)からではないか。結果として、吉本のあらぬ影を撃つかたちになった。残念な点である。
個々の論点にわたるなら、吉本の浄土教理解(往相/還相)が彼独自の解釈に支えられているとの指摘、対幻想から共同幻想への展開がきわめて危うい仮説のうえに成り立っているとの指摘など、どれも正当である。たとえばこの二点に絞って批判を内在的に掘り下げたほうが、吉本にはきつかったのではなかろうか。
【この書評が収録されている書籍】
著者田川建三氏は、キリスト教学の研究者としてつとに名を知られ、吉本氏とも幾度か交流があった由である。
題名から窺えるように、これは思想家吉本に対する諫言の書とみられる。当然、読書の興味は、吉本が陥ったという「危険」を、著者がどう抉りだし、そこに納得できる説明を与えてくれたかに集まるだろう。
一九六〇年頃の吉本を、著者は高く評価し、それがその後だんだんよからぬ方向に変わってきた、とみる。いわば、吉本「変節」論である。そこで転換点(こけたきっかけ)が探られるわけだが、それが『最後の親鸞』と『共同幻想論』だという。この二書の検討が、大部な本書の前半、後半を占め、間に『反核異論』やイリイチに絡めた批判がちりばめられている。
著者田川氏には少々失礼かもしれないが、ごく大づかみに論点を整理させてもらおう。著者はいう。吉本の親鸞論がまずいのは、吉本が宗教者としての親鸞の実像にもとづかないで、勝手に自分の思想的境位(自分が知識人として大衆から離反してしまい困るので、なんとか大衆になりきりたい)を投影しているにすぎない点である。また共同幻想論がまずいのは、彼の理論と素材とがちぐはぐで論証の体裁をなしていないうえ、理論は理論で、共同性をはなから敵視して国家と同一視したり、女性蔑視まるだしの対幻想の概念を持ち出したりという程度の、おそまつなものでしかない点である。
では、どうしてこんなことになるのか?
著者によると、それは吉本が初心を忘れたからである。
「我々大衆」という位置から戦後派知識人を鋭く告発する当初の姿勢は傑出していたのに、だんだんと理論志向にとらわれ、抽象的な図式にすべてを押しこめてことたれりとする歪んだ態度に迷いこんでしまった。
ではどうすればよいのか。
著者は、初期吉本の優れた仕事のなかにも後々のよからぬ傾向が潜んでいた、と注意し、彼の一貫した一面も見落としていない。ならばそのうえで、どんな可能性が吉本に残されていたというのか、本書からはなかなか読み取りにくかった。それでも、著者が思想家吉本のどこに問題をみているかは十分伝わってくるし、それが吉本読者のよくある反応の一典型になっていそうなこともわかる。
さて、著者の批判は、どこまで急所を突いているだろうか。これは私(評者)の判断だが、本書の論法では吉本を捕まえたことにならないと思う。
なるほど、著者の指摘の半分近くは納得できるものである。私は吉本のあまりよい読者ではないが、私なりに考えてもたしかに吉本には問題がある。しかし率直に言って、著者の議論は総じて大味で、私がいちばん知りたいと思うところを突いてくれなかった。性急な倫理的追究に力点がかかるあまり、吉本の思想的全体像を捉えない(それに興味を示すだけの余裕がない)ままで終わっている。
吉本を語るなら、多作な彼のスピードのようなものをまず押さえないとダメである。
彼はただの文学者でいたいのに、同時に、時代と状況に応答する体系的思想家の役回りも引き受けざるをえなかったため、忙しいのだ。体系への志向を見なければ、彼のユニークなところが台なしである。『言語にとって美とは何か』、『心的現象論』、それに『ハイ・イメージ論』あたりも踏まえて、自らも変化しつつわれわれの時代を語り出す吉本の全体像を描き出すこと。変節ではなく、内在的な必然として。
これを望みたかった。
著者の批判はテキストに密着しているようでいて、その実、細部にこだわりきれていない。吉本の体系的な展開がみえていない(というより、著者が現代にかかわる自分自身の思想的脈絡をよく整備できていない?)からではないか。結果として、吉本のあらぬ影を撃つかたちになった。残念な点である。
個々の論点にわたるなら、吉本の浄土教理解(往相/還相)が彼独自の解釈に支えられているとの指摘、対幻想から共同幻想への展開がきわめて危うい仮説のうえに成り立っているとの指摘など、どれも正当である。たとえばこの二点に絞って批判を内在的に掘り下げたほうが、吉本にはきつかったのではなかろうか。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
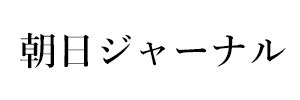
朝日ジャーナル(終刊) 1987年9月25日
ALL REVIEWSをフォローする