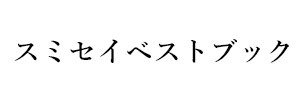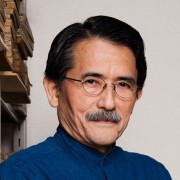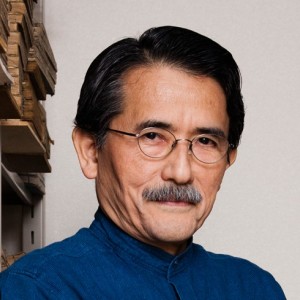コラム
森 鷗外『渋江抽斎』(岩波書店)、寺山 修司『寺山修司全歌集』(風土社)、田中 冬二『田中冬二全集 第1巻 詩 1』(筑摩書房)
これからの百年に残したい三冊
愛国心の源泉としての読書に
古典学者として生きてきた私は現代文学というものには全然興味がない。文学作品の価値は、長い時間の淘汰によってその良否が判定され、残るものは残る、消えるものは消えるのだと思うからだ。その意味で、現代小説や現代詩などのほとんどは、おそらく十年の後にも忘れられてしまうであろうと言うを憚らぬ。さて、これからの百年に残したい三冊というとき、本心を言えば『万葉集』『源氏物語』『平家物語』の三点だと言いたいところだが、それは編集子の意図するところと全然違うに違いない。
そこで近現代の作物で、しかしこれから百年先にも、ぜひ残って欲しい、これを読むことがすなわち日本文学の豊かな実りを知ることだという、そういう意味での名品を三つ選んでみた。
この他にも漱石の『吾輩は猫である』や『萩原朔太郎全詩集』のように、当然挙げなくてはならない書名もあるのだが、これらは、ここで私が言わずとも残るだろうと思って、今回は敢て外した。
さて、まず第一の、鷗外『澀江抽齋』であるが、これは日本の近代が持ちえた最も格調高い散文として選んだ。ここには、読者に媚びたり、多くを売ろうとしたり、そういう意識が皆無で、ただひたすらに渋江抽斎という人物の実相に肉迫したいという鷗外の志が表れている。こういう散文作品は、鷗外のなかでもまた白眉とすべく、しかも外国人には終に理解されない名品という意味でもここに掲げておかなくてはならぬ。日本人が日本人であることを誇りに思うのは、こういう作品を味わい得たときであるに違いない。
次に第2の『寺山修司全歌集』であるが、こういうものがたとえば文庫本のような形でいつでも印行されているということが大切だが、事実はそうなっていない。寺山の和歌は、近代和歌のなかで極めて異色の世界である。どこが異色かというと、それが壮大な虚構だということである。私は和歌というものは、歴史的に虚構の文学であったと信じている。ところが近代になって、妙に真面目ぶってリアリズム的なのばかりが尊しとされてきたのは、和歌がやせ細る第一の原因であった。そういう趨勢に棹さして、独特の魔術的語彙を駆使しつつ独り敢然と立ち向かったのが寺山であったのだ。
【文庫版】
さて第三の『田中冬二全集』は、近代詩の金字塔として挙げた。近代詩の歴史のなかで、最も新しい詩を創造したのは間違いなく萩原朔太郎である。しかし、最も美しい言語美を創作したのは田中である、と私は思う。ここには極度に凝縮した日本語の美しさ、またそれによって表現された日本という国それ自体の美しさが詰まっている。誰もが一読してため息を吐くべき名著である。
ALL REVIEWSをフォローする
初出メディア