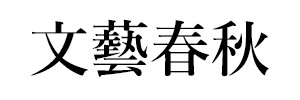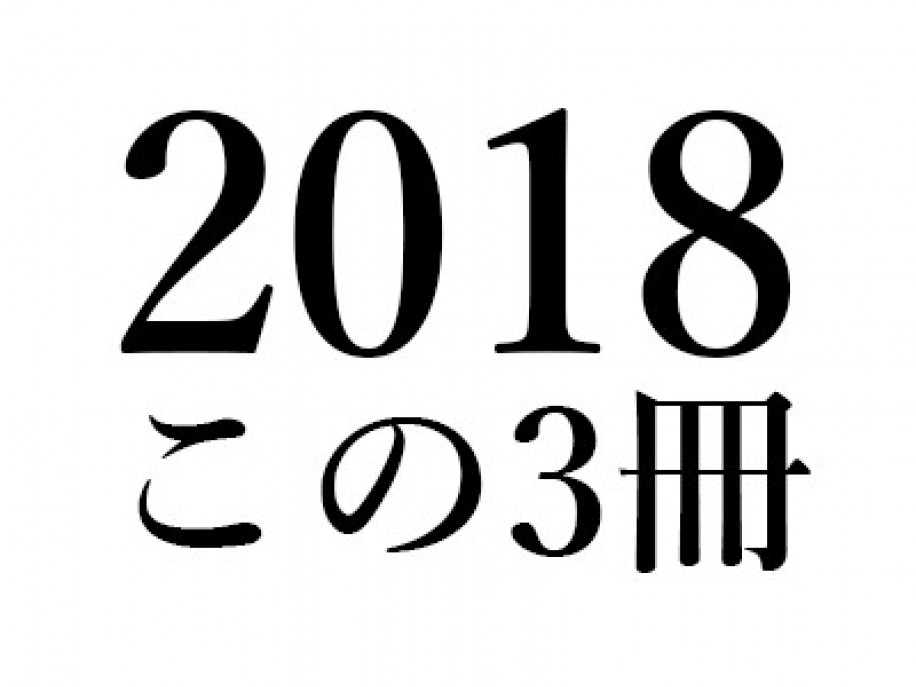対談・鼎談
『ロマノフ家の最期』A・サマーズ/T・マンゴールド|丸谷才一+木村尚三郎+山崎正和の読書鼎談
【文庫版】
丸谷 一九一八年(大正七年)の七月のことなんですが、ロシア革命の結果、ロシア皇帝の一家(ニコライニ世、アレクサンドラ皇妃、アレクセイ皇太子と四人の皇女)が、ソビエト側に捕えられていた。彼らはウラル山中のエカチェリンブルグという町、この町は、三省堂の学生用の地図帳見たら出てないような小さな町ですね(笑)。そういう町のイパチェフ館という館に抑留されていた一家が、とつぜん姿を消す。これがいわゆる「ロシア皇帝一家虐殺事件」でして、一切の革命につきものの残虐さの代表みたいに、われわれの頭にしみついている、センセーショナルな事件です。
ところが、虐殺事件というのは実際にあったのか、どうも怪しいんですね。今度、イギリスの二人のジャーナリストが精細で執拗な調査を行なって真相ににじり寄っていった――その記録が、この『ロマノフ家の最期』という本なんです。つまり、歴史推理というわけですが、その型の読物のなかでも最高級の読物になっている。ベストテン・クラスの名作探偵小説、ヴァン・ダインの『僧正殺人事件』とか、エリック・アンブラーの『ディミトリオスの棺』なんかを読むときと同じくらい興奮したといっていいんじゃないかと思います。
ところで、この謎と謎解きとを説明するには、ソコロフという白軍の調査官が調べた際の五つの証拠というのを取りあげるのが、いちばん便利でしょう。
第一が、電報なんです。白軍に押収された電報の中で、ボリシェヴィキ自身が皇帝の家族全員の殺害を確認しているというが、この電報が怪しい。まず、押収した電報六十五通の中で、この電報だけは電文が異色なくらい文学的である。電報にサインしたべロボロドフ議長のサイン、これが怪しい。さらに当該電報が発信簿にない。ひょっとするとこの電報はあとでつくった贋物ではないか。
第二の問題点は、死体を見た唯一の証人の証言があるんですが、メドヴェージェフというこの証人が、どうもおかしい。第一、ロマノフ一家虐殺に深くかかわった身でありながら、進んで白軍に投降して証言した、それが怪しい。
さらに、これが本当のメドヴェージェフなのかどうか。しかも最後にメドヴェージェフは消されてるらしいんですね。したがって第二の証拠である目撃者の証言は信用できないことになるわけです。
第三、皇帝の家族の非常にたくさんの所持品が発見されたんですが、これは擬装殺人の証拠として、わざと用意したものではないか。その証拠としていちばん説得力があるのは、コルセットの前あてが六つ残ってる。これはその場にいたと目される女性六人の数に合うんですけれども、人間のからだを射撃した場合につくはずの弾痕が、コルセットについていない。さらに肝心の死体がないし、法医学的に重大な人間の歯が一つも残ってない。したがって、大量の所持品は、擬装殺人の小道具にすぎないんじゃないかと考えられる。
第四に、タチアナ王女の愛犬ジェミーの死体、これは「事件」の約一年後に捜索隊が鉱山の竪穴の底で発見したものなんです。ところが、一年間、水や氷の中につかっていたのに、完全な形で残っていた。それに、もう一匹のアレクセイが飼っていたスパニエル犬が、ずいぶんたってから、その街を走ってたのが見られているんですね。それから見て、ジェミーも、ずいぶんあとまで生き残ってたのが殺されて見つかるようにされたんじゃないか。つまりこれもやはり擬装の殺しなんじゃないか。
第五、ロマノフ皇帝の家族七人を「事件」のあとだれも見かけなかったということが、最後の有力な証拠になるわけです。しかし、四人の皇女を見かけたというのはいろいろあって、ことに、例のアナスタシア皇女――これは第二次大戦後にも復活して問題になったわけですけれども、この二人の著者は、アナスタシア皇女の後身であるといいたてる人と会ってる。それで会った感じからいうと、本物らしいという推定がかなり可能である。
その他いろいろな材料がありまして、どうもロマノフ家の七人が、すくなくとも一九一八年の七月に全員ウラル山中で虐殺されたというのは、信じがたいことになってしまう。つまり、歴史が擬装されたわけなんです。
なぜこういうことになったかというと、ボリシェヴィキ側と白軍側の双方の利益が一致したために、虐殺の噂が成立しちゃった。虐殺という事件が捏造(ねつぞう)された。一九一八年七月当時、ウラル地区の赤軍は敗色濃厚であった。ですから皇帝一家をすぐ取り戻せるとわかれば、白軍の士気は増して、いよいよ威勢がよくなる。だから赤軍としては、白軍の勢いを減じるために、皇帝一家はもはやいないということに仕立てる必要があった。一方の白軍としては、いかに赤軍というものが悪逆非道であるかということを宣伝するために、このデマは非常にありがたかった。
またもう一つ大きな背景としては、レーニン、ドイツ皇帝およびイギリス皇帝との取引材料としてロシア皇帝一家を使おうとしていたという状況があって、そのせいでこういうふうに歴史が偽造されたんじゃないか。
これを読むのに、ぼくは四日ぐらいかかりましたけれども、四日もかかって存分に一人で楽しむ、そういう本ですね。知的な娯楽書として推薦できるものだと思いました。最後に付け加えたいのは、翻訳がなかなかいいということ。妙にひっかからなくて意味が明快に通じてスラスラ読めましたね。
木村 真相はどうだったか、よくわからないと思うんですけどね。だから「歴史とは公認された作り話にすぎない」というヴォルテールの言葉が、『ニコライニ世の最期』の項に書いてあるでしょう。実際、歴史には、素材としての事実そのものがどうだったかということと、それをどうやって一つの全体像にまで組み立てていくかという両面があると思うんですけど、この本は事実そのものがどうだったかということを追及している。その執念のようなものがたいへんおもしろいですね。
大佛(次郎)さんの『パリ燃ゆ』とちょっと似てるような感じがしました。レンガを一つずつ積んでって、これでもかこれでもかって迫っていく調子が。
山崎 もっともこれはレンガを積むんじゃなくて、レンガを崩す話ですがね。
木村 逆に解体していくわけだ(笑)。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする