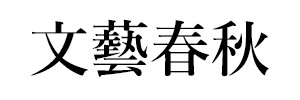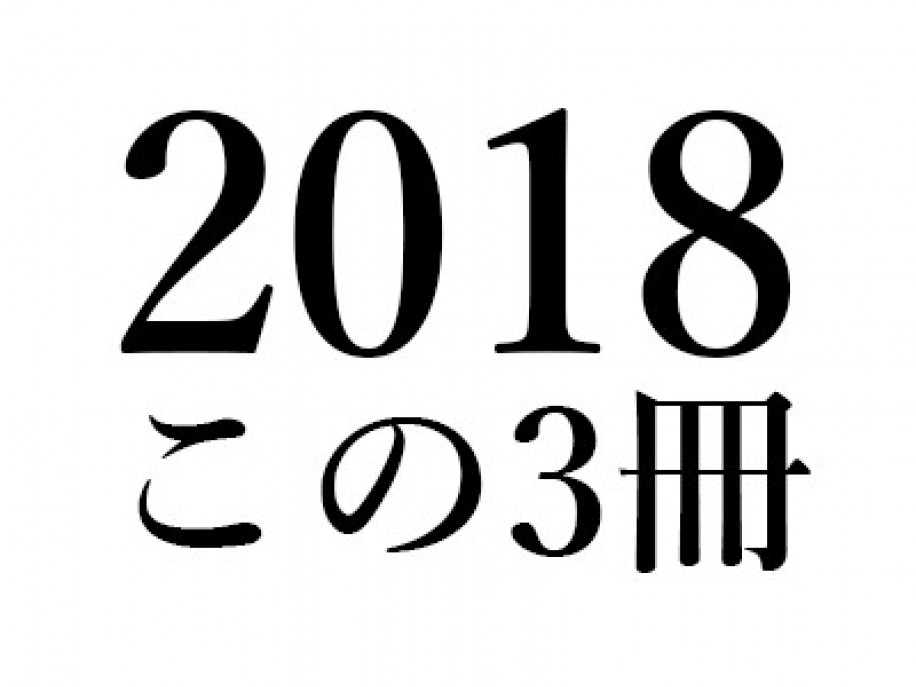対談・鼎談
『ロマノフ家の最期』A・サマーズ/T・マンゴールド|丸谷才一+木村尚三郎+山崎正和の読書鼎談
丸谷 ぼくは、あそこ好きだった。つまらないというのも、そのとおりですけどね。
山崎 一般に人間が描けてないでしょう。この長い長い本を通して、いわゆる描写といえるようなものが、一行もない。これはものについてもなければ、街頭の風景についてもなければ、人間の肖像についてもない。これは非常に驚くべきことですね。
丸谷 ぼくは、こういう頭の働き方の人がいると思うんだよ。
山崎 それが丸谷さんの嫌いな法科的人間じゃないですか(笑)。
丸谷 そうじゃなくて、イギリス人およびイギリス文化の影響をひどく受けた人に、こういう人がいると思う。たとえばダーウィン。
山崎 なるほどね、ガラパゴス島へ行って風景を見なかった(笑)。
丸谷 バーッといろんな材料を集めて『種の起原』という体系をつくる。フレーザーという入が『金枝篇』という本を書く。イギリス文化の影響を受けた人の中に入れておかしいかもしれないけど、マルクスっていう人ね、いろんなゴチャゴチャした材料を集めて、システムをつくっちゃう。もう一人入れてもいいや、トインビーって人(笑)。
山崎 あの人は少しドイツ的じゃありませんか(笑)。
丸谷 イギリス人にはそういう才能があって、イギリス文化ってものには、そういう面があるんじゃないか。
木村 論理性っていうよりは、現実のこまかい一つ一つの材料を重視するわけですね。
丸谷 そうそう、論理性じゃなくて、建築性みたいな何かね。
木村 最近たとえばフランスの歴史学も、そうなってきている傾向があると思うんですよ。まっ白なキャンバスに、小っちゃな色紙をこまかくちぎって、わかってるところだけ一つ一つ細かに貼っていく。じつにテレビ的です。昔はレントゲン写真みたいに、国家や社会の背骨だけを写して、本質はこうだという描き方をした。十九世紀の場合ですね。
ところが、いまの歴史の描き方は、たとえば一人の人間についてわかってるところ、太ってるか、痩せてるか、眉毛がつりあがってるか、さがってるかといった、部分部分を一つ一つ丹念に書きこんでいくといった態度ですね。生活史などに、特にそれがよく出ています。
山崎 林屋(辰三郎)さんにおもしろいことを聞いたんですがね、日本の歴史学でも同じことだそうですね。非常に細部をこまかくやって、時代のパースペクティブってものにはさわらないっていう傾向……。
木村 でも、日本のそれは、自分の研究分野に小さく閉じこもって全体を見ないということで、あんまり褒めた話とは思わないんだけども(笑)。わたしがいいたいのは、いまの新しい歴史学がまさにカラーテレビ時代のように、部分を大写しにして具体的に全貌に迫ろうとしていることですね。しかし全体はこうだ、と決めつける無理は絶対にしない。
山崎 さっきの心やさしさの話に戻していえば、この二人がロマノフ問題をやると決めたときに、たぶん頭の片隅に、アナスタシアの遺産問題がもう現実的問題でなくなったという判断が入ってたと思いますね。
丸谷 やはり、この本のきっかけはアナスタシアですね。アナスタシアに対する愛情が自分たちの中にあることに気がついて、とすれば読者たち、視聴者たち、みんなにアナスタシァに対する愛情があるに違いないと。
木村 だれも傷つく入はいないわけです、この本でね。会見自体はつまらなかったといったような、何か非常に暖かい気持で見ている感じですね(笑)。
山崎 そこにちょっと典型的人物として出てくる、現在のアナスタシアのご主人というのがいますね。アメリカの地方大学の先生で歴史かなんかやってて……。
丸谷 ぼく、あの男好きだったな(笑)。
山崎 それがいかにもアメリカにいる人物だという感じがする。女房に代わって雄弁に、さして証拠もないことを叫んで、あれはほんとのアナスタシアだといって暮らしている。たとえば、奥さんがつまらない細工物なんかつくってると、彼女が世界的大芸術家であるかのごとく、溜々とパーティーでしゃべる人のよい亭主っていうの、アメリカにいるんですよね(笑)。
丸谷 これ読んで、だれかこのご夫婦を主題にして芝居書かないかなあと思ったんだ。
山崎 小説をお書きにならなきゃ……(笑)。小説のテーマですよ。本人が語らない人物じゃ、芝居になりませんからね(笑)。
丸谷 いやいや、本人が語らないでご亭主がむやみやたらに語るんだ。いいと思うよ。ことにアメリカの大学の先生というのは、山崎さんの自家薬籠中の人物でしょう(笑)。
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする