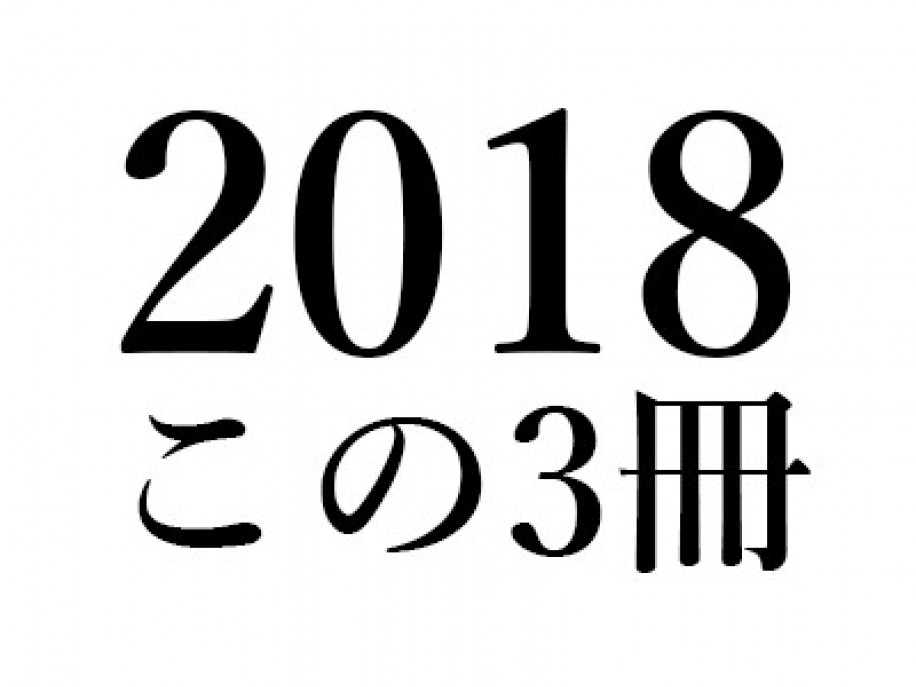書評
『文明としての教育』(新潮社)
経験の仕方、方法論を教えるものこそ
これは外国語教師を三十年やってきた経験から言うのだが、外国語教育において最も好ましいものは「強制」であり、最悪なのは「自由」である。好きなときに好きなものをという自由放任の教育では、外国語は絶対に上達しない。いきなり、学ぶ理由も目的も教えられずに教室に閉じ込められ、頭からたたき込まれて初めて人は外国語に上達する。なぜか? 外国語教育では、まずソシュール言語学でいうところのラング(規範体系としての言語)を徹底的に覚えさせなければならないが、これは、パロール(個人が運用する言語)とは異なり、先験的に存在するものであるから、外国語学習者を外部強制的にそこに着床させなければならないからである。
本書の教育論を理解するには、このラングとパロールの二元論を頭に入れて、前者を「文明」、後者を「文化」と置き換えて読み進めていくのがいい。著者によれば、文明とは、繰り返された共同体の思考・行動が一定の形式(規範)に整えられて「体系」となった言語・技術・法律・礼儀作法・思考などを意味するのに対し、文化とは「文明が人間の身についた姿」であり、「身体化された文明」であるという。
例としてあげられるのが「ピアノと楽譜=文明」と「ピアノが弾けること=文化」の違いである。ピアノや楽譜は西洋文明の典型であり、楽譜は頭の中の秩序、ピアノは頭の中の技術を物質化したものである。では、ピアノが弾けるとはなにか?
たんにマニュアルに従い、順を追って鍵盤を押すということではありません。キーの前に座ったら、もう指が動いてしまっているという状態になったとき、真の意味でピアノが弾けるといえます。当然ながら、この行動には価値の上下があって、上手な人もあれば、下手な人もあるわけです。
著者の教育論の基本は、この「文明の教育」と「文化の教育」を峻別(しゅんべつ)し、国家の施す義務教育は「文明の教育」すなわち「統治としての教育」に限定し、「文化の教育」すなわち「サービスとしての教育」は思い切って民営化し、社会に委ねるべきだというものである。
本来ならばサービスとして理解されるはずの教育が、義務として教えられてきたのは事実です。あえて極論をいえば、私は真に義務とされるべきは、読み・書き・算術と遵法(じゅんぽう)教育だと考えていますので、現行の小中学校でのそれ以外のすべての教科はサービスということになります。
では、なぜ「統治としての教育(義務教育)」が「読み・書き・算術と遵法教育」に限定されるべきなのか? それは、「教育の目的は社会秩序の側にある」と考えるデュルケームにならって、「人間はもともと個人的存在であると同時に社会的な存在であって、教育の役割は後者の形成に使命を限られている」と見なすからである。いいかえると、子供を社会的な存在にするために最低限の基礎的規律(読み・書き・算術と遵法教育)をたたき込むのが国家教育の使命なのである。
基礎的な規律、もっというなら経験のための方法を教え込まなければ、その先の自由教育というものはありえないのです。(中略)私たちは一定の方法を持つことなしには何ごとも経験することはできません。経験とはたんに生きていれば身につくものではなく、教室という抽象的な空間にいったん生徒が隔離され、そのなかで体験のプロセスと技術を教え込まれることによってはじめて身につくものなのです。
それでは、こうした著者の教育観はどこから生まれてきたのか?
日本の敗戦で国家(満州国)が解体してしまった状況で受けた教育によるものである。零下二十度にもなるレンガ壁だけの空間で、その教育は行われた。教室の梁(はり)から首吊(くびつ)り死体がぶら下がっていることさえあった。「カチカチに凍っていますから、悪臭もしないし、病気の危険もない。私たち小学生はその死骸(しがい)を無視して授業に聞き入っていました」
ボランティアの代用教員は熱心だが破天荒で、ある先生はルターの伝記を話し、ある先生は文豪たちの文章を丸暗記させ、別の先生は手回し蓄音機でドヴォルザークとラヴェルを聞かせた。それは遠い世界から聞こえてくる文明の声であり、著者は後に、荒廃の中に閉じ込められていたからこそ、「普遍」とつながっていたのだと悟ることになる。
この満州(現・中国東北部)での教育は先生も生徒も授業が何かの役に立つとは意識していなかったし、また知識は現実世界から完全に遊離していた。しかし、逆説的ながら、この特殊な教育が著者に「教育とは生徒にたいして経験を拡大させる技術ではなく、生徒にたいして経験の仕方や経験の方法論を教えるもの」であるという真理を教えたのである。中央教育審議会会長を務める著者の教育論が一刻も早く実現することを願いたい。それだけが、ジリ貧・日本を救う道であるように思えるからだ。
ALL REVIEWSをフォローする