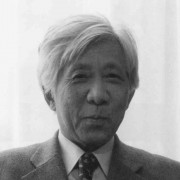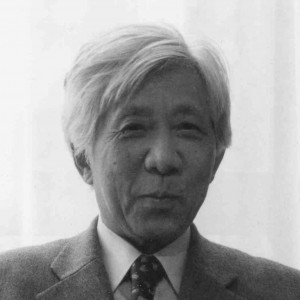書評
『いつか王子駅で』(新潮社)
映像ものに市場を制圧されてしまったせいだろう、世に広く出回っている小説の文章は日を追って目が荒くなりつつある。中で、まだ三十代の堀江敏幸は、よく目の詰んだ柔軟・濃密な文章で小説作品を綴る。
「位置関係」という漢語を「よじれ」という優しくエロチックな和語がうまく包み込んで、ああ、いい感じだなあと読み手を寛やかな気分にさせる。戦後の無原則な国語いじりと欧米からの新規流入語で日本語はここ数十年、荒れに荒れてきた。一九六四年生まれの、フランス文学の研究者でもあり翻訳家でもある若き日本人が、こんなにも濃(こま)やかな文体を身につけているのは快い驚きだ。
そもそもの書き出しがこれだ。瀧井孝作や島村利正の端正さにあこがれ、小説なのに堂々とそうした簡潔・端正派たちの文章を引用するほどの半時代的な姿勢を隠さぬまま、堀江敏幸自身の文体はセンテンスがけっこうのびのびと長い。流れに身をまかせて読み進むうち、初期の石川淳を思い出したが、やはりまるで違う。石川淳の作中人物はどれほど落魄してもなんとなく凄(すご)んでいる。堀江敏幸の描く市井人には、インテリやくざふうに凄む者はいない。語り手の「私」は東京湾岸の小公園で雀に餌を撒いている老人に、自分は米屋で今撒いているのは買い手のつかない古々米だと言われ、
そんなふうに考え行動する凄くない人間である。作者の分身という設定だが、時代を読み切った頭のいい技法だと思う。良質な小説読者は、ずっと前から”異常”に食傷している。
筋のない小説とは違う。筋はちゃんとある。昇り龍の入れ墨をした印章彫りの正吉さんと、非常勤講師をしたり翻訳をしたりの落ちこぼれ知識人「私」、この二人が中心になる。そこへ都電荒川線が絡み、居酒屋「かおり」が絡み、競馬が絡む。日常性への偏執などこの小説は少しも看板にしていない。人殺しも不倫もないが話はスリルに満ちている。紙数がないので、小説としての面白さについてはここで責任を持つことにし、あと一つ、どうしても言いたかったことを書かせてもらう。
もう指摘したことだが、『いつか王子駅で』には先人たちの小説の引用がふんだんに織り込まれている。小説の作法としてはルール違反だ。作品引用はエッセーや評論の特権なのだから。だがその点、堀江敏幸は確信犯というに近い。徳田秋声の『あらくれ』の一節をいとおしそうに引用し、主人公のお島について、
「お島は『待つこと』のできない女だった。計画や失敗の中にながく居座れず次々に手札を切り、切る瞬間の喜びに浸ったあとは堪え性もなくさらに次の手札を切る」と書く。つまり作中人物評をやってのける。一般受けはしないだろうが、心ゆたかな小説読みなら四の五の言わずに受容するはずだ。
オーディベルティという往年のフランス前衛作家が突然呼び出されたり、「風呂屋による風呂屋の自己言及」などという高級な冗談が飛び出したりもするが、この小説は徹底的に”もの”と”ひと”への触覚的ともいうべき執着をつらぬいている。「ニョッキみたいに真ん中がへこんでいる柔らかそうな耳朶」――この種の幼年感覚めいた直接性こそ小説の宝だ。
カウンターのむこうで、女将さんはドリップポットを持った右手の手首と肘のなかほどをまたあのぽちゃりとした白い左の手で支えながら、無言のまま神経を集中して珈琲を落としている。身体の線とその手の位置関係の不思議なよじれには、たぶんこちらからは見えない両足の使い方がかかわっているのだろう。
「位置関係」という漢語を「よじれ」という優しくエロチックな和語がうまく包み込んで、ああ、いい感じだなあと読み手を寛やかな気分にさせる。戦後の無原則な国語いじりと欧米からの新規流入語で日本語はここ数十年、荒れに荒れてきた。一九六四年生まれの、フランス文学の研究者でもあり翻訳家でもある若き日本人が、こんなにも濃(こま)やかな文体を身につけているのは快い驚きだ。
やはり正真正銘の極道者だった時代があるのだろうか、左肩から上腕にかけてびっしりと彫られた紺青の龍の刺青が湯あかりに火照った肌からひときわ色濃く浮き出し……
そもそもの書き出しがこれだ。瀧井孝作や島村利正の端正さにあこがれ、小説なのに堂々とそうした簡潔・端正派たちの文章を引用するほどの半時代的な姿勢を隠さぬまま、堀江敏幸自身の文体はセンテンスがけっこうのびのびと長い。流れに身をまかせて読み進むうち、初期の石川淳を思い出したが、やはりまるで違う。石川淳の作中人物はどれほど落魄してもなんとなく凄(すご)んでいる。堀江敏幸の描く市井人には、インテリやくざふうに凄む者はいない。語り手の「私」は東京湾岸の小公園で雀に餌を撒いている老人に、自分は米屋で今撒いているのは買い手のつかない古々米だと言われ、
連れ合いがいたいけな雀の舌でも切ってしまったのだろうか、雀のお宿へは謝罪に出かけてもきっとお土産に小さいほうのつづらを選ぶに違いないこの優しい心根の持ち主にむかって、雀にやるくらいなら譲ってくださいとも言えず、私は憮然として帰路についた。
そんなふうに考え行動する凄くない人間である。作者の分身という設定だが、時代を読み切った頭のいい技法だと思う。良質な小説読者は、ずっと前から”異常”に食傷している。
筋のない小説とは違う。筋はちゃんとある。昇り龍の入れ墨をした印章彫りの正吉さんと、非常勤講師をしたり翻訳をしたりの落ちこぼれ知識人「私」、この二人が中心になる。そこへ都電荒川線が絡み、居酒屋「かおり」が絡み、競馬が絡む。日常性への偏執などこの小説は少しも看板にしていない。人殺しも不倫もないが話はスリルに満ちている。紙数がないので、小説としての面白さについてはここで責任を持つことにし、あと一つ、どうしても言いたかったことを書かせてもらう。
もう指摘したことだが、『いつか王子駅で』には先人たちの小説の引用がふんだんに織り込まれている。小説の作法としてはルール違反だ。作品引用はエッセーや評論の特権なのだから。だがその点、堀江敏幸は確信犯というに近い。徳田秋声の『あらくれ』の一節をいとおしそうに引用し、主人公のお島について、
「お島は『待つこと』のできない女だった。計画や失敗の中にながく居座れず次々に手札を切り、切る瞬間の喜びに浸ったあとは堪え性もなくさらに次の手札を切る」と書く。つまり作中人物評をやってのける。一般受けはしないだろうが、心ゆたかな小説読みなら四の五の言わずに受容するはずだ。
オーディベルティという往年のフランス前衛作家が突然呼び出されたり、「風呂屋による風呂屋の自己言及」などという高級な冗談が飛び出したりもするが、この小説は徹底的に”もの”と”ひと”への触覚的ともいうべき執着をつらぬいている。「ニョッキみたいに真ん中がへこんでいる柔らかそうな耳朶」――この種の幼年感覚めいた直接性こそ小説の宝だ。
ALL REVIEWSをフォローする