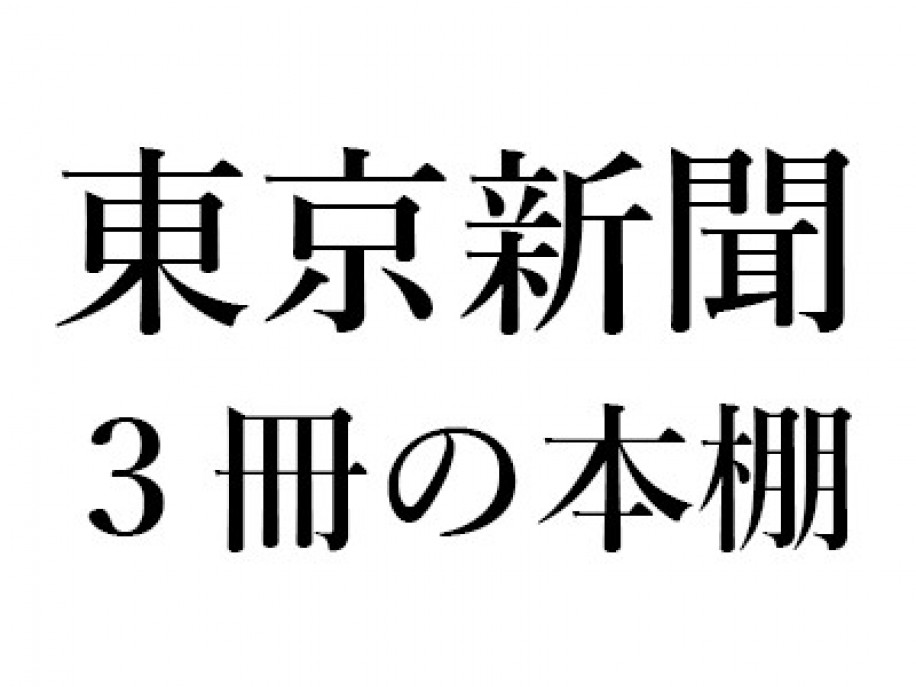書評
『東京島』(新潮社)
トヨザキ的評価軸:
「金の斧(親を質に入れても買って読め)」
「銀の斧(図書館で借りられたら読めば―)」
「鉄の斧(ブックオフで100円で売っていても読むべからず)」
無人島に最初に漂着したのは清子と夫の隆。その三カ月後、与那国島のアルバイトから逃げ出した二十三人の若者が、台風に遭って漂流していたところを清子たちに助けられ、二年後には日本への密航途中に捨てられた中国人の団体さんも島民に。島を「トウキョウ」と飛び、みんなが集まる場所を「コウキョ」と名づけるなど、かつての生活様式に固執し、生存のための技術も開発せず、野生の花を使ったレイ作りなど役にも立たないことで時間を潰している日本人の若者とは違って、「ホンコン」と呼ばれるようになった中国人たちはすぐに島の生活に馴染み、自分たちで作った調味料で美味しそうな料理を作ったり、食材の枯渇を防ぐための生産に腐心。無人島に漂着した子供たちが殺し合いをする様を描いた、ゴールディング『蝿の王』(新潮文庫)のような覇権をめぐる凄惨な争いなど起きない、せいぜいが清子をめぐってのせこい殺人が起きる程度の、ぬるいサバイバル生活の描写が大変リアルで、桐野夏生の現代人を視る眼差しの確かさに唸らされます。
容色が衰え、男たちをセックスの力で制圧することが不可能になってきたことに焦り、あられもない生き残り戦略を巡らせる清子のキャラクタライゼーションが見事なのは、これまで意地の悪い視線で数々の個性的な女性キャラを創出してきた桐野さんだから当然としても、核廃棄物っぽいドラム缶が捨て置かれた浜「トーカイムラ」に追いやられたワタナベというキモメンの造型の素晴らしさはどれほど賛辞を尽くしても足りません。全裸で海亀の甲羅を背負い、清子の夫が遺した日誌を読んで思考することを覚えていくワタナベが出てくるシーンは、笑いなくしては読めないんですの。
でも、この読んで無類に面白い物語の最終章が、わたしには残念。そこまで描く必要があったのかなあ。こんな理に落とさないでほしかったなあ。というわけで、わたしは開かれた最終章を自分で勝手に作って余韻を楽しんでいるんでありました。
【この書評が収録されている書籍】
「金の斧(親を質に入れても買って読め)」
「銀の斧(図書館で借りられたら読めば―)」
「鉄の斧(ブックオフで100円で売っていても読むべからず)」
二十一世紀仕様の無人島小説。はたまた国造り物語の傑作!
〈今年で四十六歳になったが、髪が薄くなった以外、まだ衰えはない。そんな自分を巡って、どれほどの死闘が繰り広げられたか。清子はまたしても笑いを浮かべた。人が死んだり、怪我したり。これほど男に焦がれられた女が世界に何人いるだろう〉なんてうっとりしている中年女が、自分の夫を籤引きで選ぶ儀式に参加したい男が激減してしまったことに気落ちする冒頭から、読者のハートを鷲づかみ。桐野夏生の『東京島』は無人島小説、また国造り物語として二十一世紀仕様になっている、かなり斬新な傑作なんであります。無人島に最初に漂着したのは清子と夫の隆。その三カ月後、与那国島のアルバイトから逃げ出した二十三人の若者が、台風に遭って漂流していたところを清子たちに助けられ、二年後には日本への密航途中に捨てられた中国人の団体さんも島民に。島を「トウキョウ」と飛び、みんなが集まる場所を「コウキョ」と名づけるなど、かつての生活様式に固執し、生存のための技術も開発せず、野生の花を使ったレイ作りなど役にも立たないことで時間を潰している日本人の若者とは違って、「ホンコン」と呼ばれるようになった中国人たちはすぐに島の生活に馴染み、自分たちで作った調味料で美味しそうな料理を作ったり、食材の枯渇を防ぐための生産に腐心。無人島に漂着した子供たちが殺し合いをする様を描いた、ゴールディング『蝿の王』(新潮文庫)のような覇権をめぐる凄惨な争いなど起きない、せいぜいが清子をめぐってのせこい殺人が起きる程度の、ぬるいサバイバル生活の描写が大変リアルで、桐野夏生の現代人を視る眼差しの確かさに唸らされます。
容色が衰え、男たちをセックスの力で制圧することが不可能になってきたことに焦り、あられもない生き残り戦略を巡らせる清子のキャラクタライゼーションが見事なのは、これまで意地の悪い視線で数々の個性的な女性キャラを創出してきた桐野さんだから当然としても、核廃棄物っぽいドラム缶が捨て置かれた浜「トーカイムラ」に追いやられたワタナベというキモメンの造型の素晴らしさはどれほど賛辞を尽くしても足りません。全裸で海亀の甲羅を背負い、清子の夫が遺した日誌を読んで思考することを覚えていくワタナベが出てくるシーンは、笑いなくしては読めないんですの。
でも、この読んで無類に面白い物語の最終章が、わたしには残念。そこまで描く必要があったのかなあ。こんな理に落とさないでほしかったなあ。というわけで、わたしは開かれた最終章を自分で勝手に作って余韻を楽しんでいるんでありました。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする