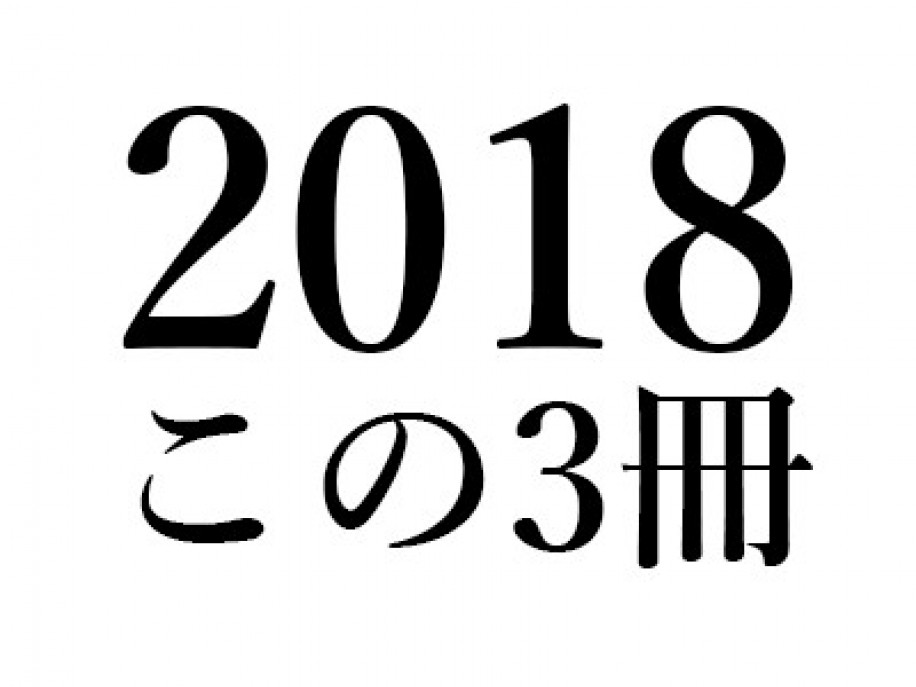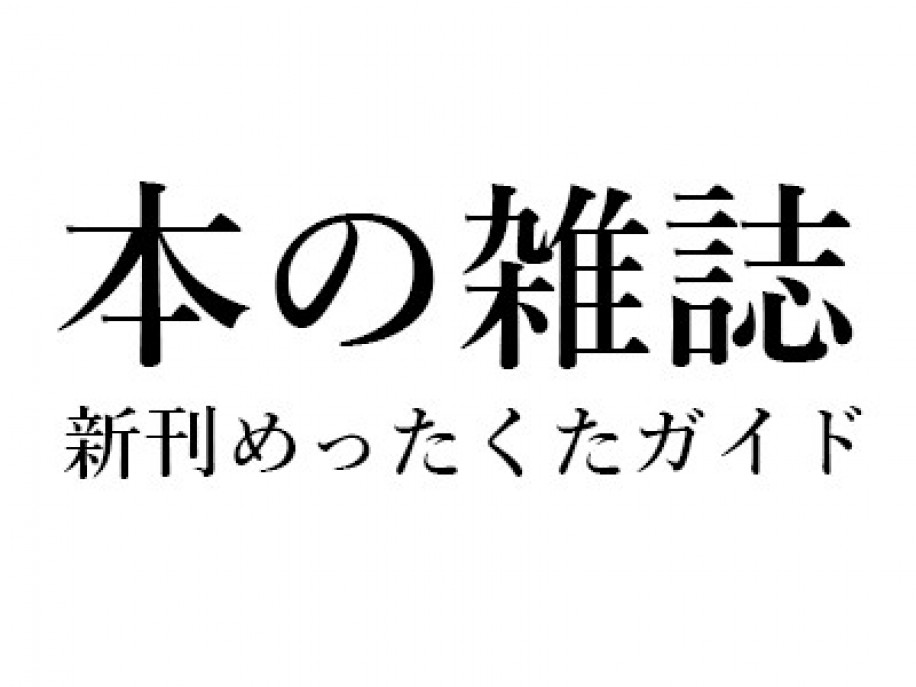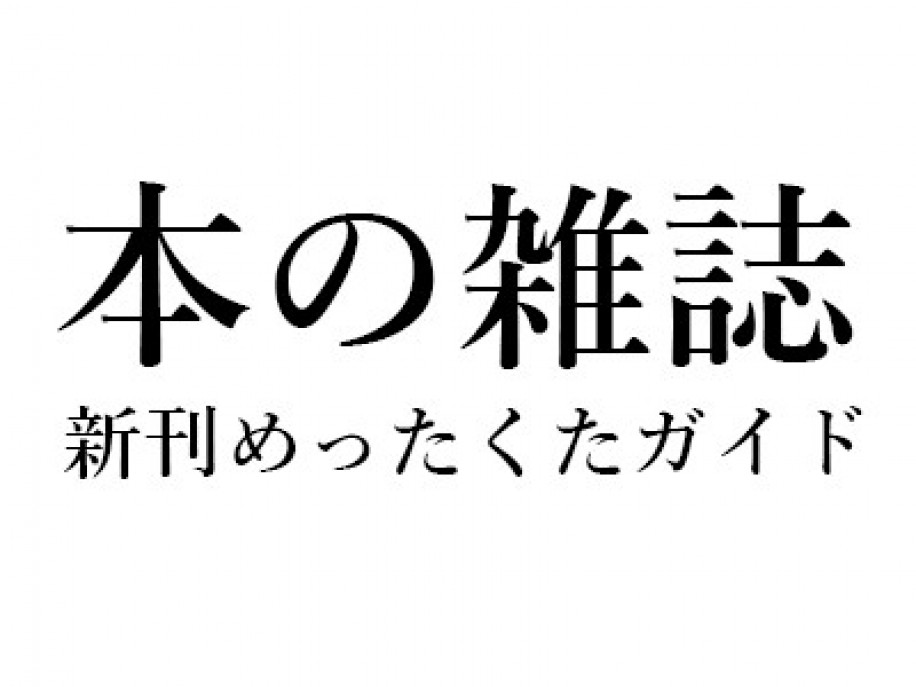書評
『バナールな現象』(集英社)
奥泉光は断じてバナールではない
奥泉光の新作のタイトルは『バナールな現象』(集英社)である。それでもってタイトルを見るたびに、バナール……バナール……バナーナ……バナーナ……おお、英会話を勉強している中村雅俊の気分になってしまうのだが、こういうのを「バナールな現象」というのである。なお、本書の最後にはbanalの意味がちゃんと載っている。すなわち、形容詞で「陳腐な、凡庸な」。さて、みなさんは奥泉光の作品をお読みになったことがあるだろうか。芥川賞をとったのは知っているが、まだ読んでない? そりゃあ、いけない。わたしの考えでは、わたしより年下の男性作家では、いまや奥泉光がNo.1のはずだからだ。
次々と旺盛に発表されている奥泉光の作品にはいくつかの、はっきりと目につく特徴がある。すなわち、
現実と幻想の区別がいつの間にか溶けてしまうこと、
ミステリアスな謎が示されること、
「政治」への積極的な言及があること、
観念的な用語が積極的に用いられていること、等々。
もちろん、この『バナールな現象』も例外ではない。そればかりか、
一面の砂漠である。
両手を頭部の後ろに組み、脇腹を無防備に晒した、一団の人間が窪地に蹲(うずくま)っている。ステップに棲む齧歯(げっし)類に似て、穴から首を出した人は、顔面をつるりと剥き出し、黒い頭髪に陽の光を存分に浴びている。人々は無帽である。それは彼らの武装解除の何よりの証拠である。鉄兜なく戦場にあるのは危険なばかりでなく、熱砂のなかでは程無く日射病にやられ動けなくなってしまうだろう。
という冒頭の部分を読んで、戦後文学の出発点となった野間宏の『暗い絵』を思いうかべてしまうことだってできるだろう。
はて、いまごろ野間宏? 近代文学? ふるーい、とお思いになったら、それはあなたのいいところ、ではなくて、勘違いなのである。
奥泉光はまじり気なしに新しい。それは、彼が五十年近く日本の作家の精神を規定してきた「戦後」から脱する道を見つけようとしているからだ。
いったい、いつまでが「戦後」なのか――それ自体としては単に時代を区分するだけの用語にすぎないこの言葉(概念)が作家たちに作用してきた力は、きわめて大きい。なぜなら、作家はまず自分がどういう存在であるかを規定しなければなにも書けず、その規定の最初は時代との関係だったからだ。戦争直後は戦前的なものとの訣別が「戦後」的な精神としてあった。それから、「政治と文学」の対立と文学の自立が「戦後」的なもののシンボルとなった。やがて、戦争は遠い記憶となる。しかし、ほんとうに「戦後」がおそろしいのはそれからである。「戦後」的精神。それはひとことでいうなら「過去を懐かしく回想する精神」である。わたしの先輩たちも、わたしも、わたしの同時代の作家も、わたしより遥かに若い作家たちも、その構造は変わらない。わたしたちは「後ろ向きに」ものを考えてきたのである。回想する過去が近ければ愛憎が深く、遠い過去であれば無関心となる。そこにあるのは関心の違いだけであって、精神的な態度に違いはない。古い作家は自覚して「戦後」的であり、若い作家は無自覚に「戦後」的だったのだ。
奥泉光の作品を決定づけているのはその「戦後」的なるものからの切断である。そこには懐旧すべき過去はない。だからこそ、自由に過去に戻ることができるのだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする