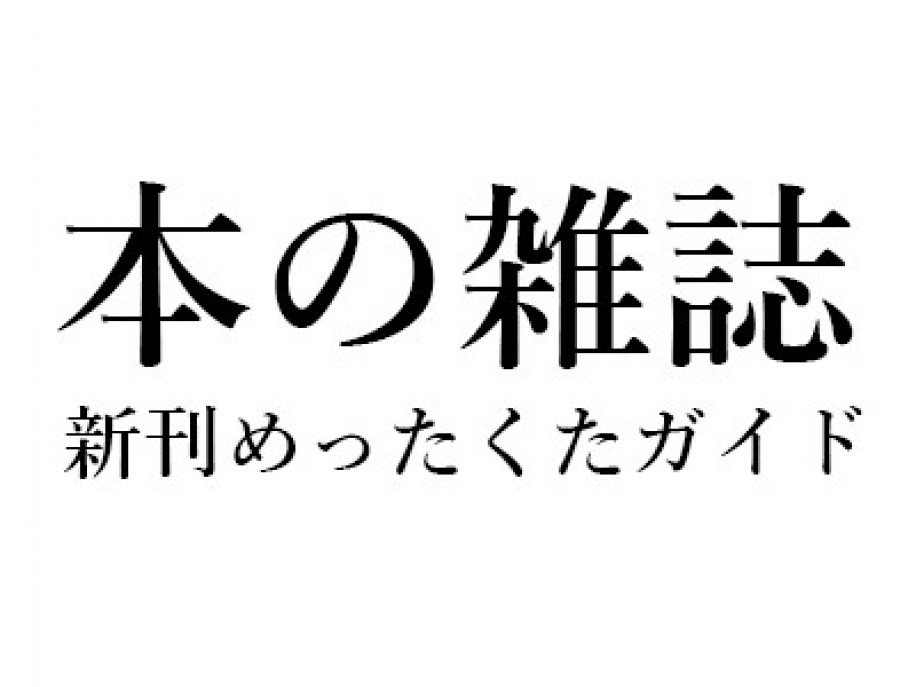書評
『てつがくのライオン―工藤直子少年詩集』(理論社)
戦前に、仙台にひとりのドイツ人の哲学教授がいた。ドイツ系ユダヤ人ということで亡命を余儀なくされ来日したのだが、およそ五年にわたる滞在も終わり近くなったころに、雑誌「思想」に、日本における〈哲学〉のあり方をめぐって辛口の批評の文章を寄せた。
日本人がヨーロッパの近代文明を知ったときにはヨーロッパ人はそれをむしろ一箇の問題とみなし、もはやじぶんでも信じなくなっていた。ヨーロッパ人が戦慄を感じながらみずからと対決していたときに、日本人はそれを無批判的に受けとった。そしてヨーロッパ精神の最上のものである自己批判にたいしては少しも注意を払わなかった……。
かれはもうひとつ、強烈な皮肉も放っている。日本の哲学者は二階建ての家に住んでいて、二階には欧米の学説が干し物のように紐に吊るしてならんでいるが、それが一階での日本人としての日常の感じ方や考えと、なにひとつ結びついていないというのである。
少々紋切り型の批判であるとはいえ、西洋文明そのものが内蔵する形而上学への批判、あるいはそのエスノセントリズムの批判まで、欧米の枠組みを直輸入し、それが「現代思想」として流通しているのだから、これ、いまもなかなか耳の痛い言葉である。
工藤直子の『てつがくのライオン』、この「少年詩集」は哲学について何かを語っているわけではない。
「てつがく」というのは坐り方からして大事だというので、いろいろ工夫する。尾を右にまるめたので前肢を重ねて顔を右斜め上に向ける、すると遠くに風に吹かれる梢が見えた。だれも来てくれないのでもう帰ろうかと思っていたら、かたつむりがやってくる。
「みえてはいるが誰れもみていないものをみえるようにするのが、詩だ」とは、やはり詩人の長田弘の言葉だが、「てつがく」についてもそっくりおなじことが言える。が、それにはそれなりの身がまえというものが必要だろうし、なによりもそれが他人によって支えられているのだということを忘れてはならない。
工藤直子のこの詩集は、「てつがく」がひとのあいだにあり、書斎でのモノローグではなく、ひととの出会いのなかでのダイアローグだということを教えてくれた。考え、論じるだけでなく、聴くことのたいせつさを教えてくれた。言葉とともに考え、話し、聴くことがわたしたちの生活のなかでどういう意味をもつのか、そのことをくりかえし問うなかではじめて、「てつがく」はひとりの人生の芯になりうる、と。
【この書評が収録されている書籍】
日本人がヨーロッパの近代文明を知ったときにはヨーロッパ人はそれをむしろ一箇の問題とみなし、もはやじぶんでも信じなくなっていた。ヨーロッパ人が戦慄を感じながらみずからと対決していたときに、日本人はそれを無批判的に受けとった。そしてヨーロッパ精神の最上のものである自己批判にたいしては少しも注意を払わなかった……。
かれはもうひとつ、強烈な皮肉も放っている。日本の哲学者は二階建ての家に住んでいて、二階には欧米の学説が干し物のように紐に吊るしてならんでいるが、それが一階での日本人としての日常の感じ方や考えと、なにひとつ結びついていないというのである。
少々紋切り型の批判であるとはいえ、西洋文明そのものが内蔵する形而上学への批判、あるいはそのエスノセントリズムの批判まで、欧米の枠組みを直輸入し、それが「現代思想」として流通しているのだから、これ、いまもなかなか耳の痛い言葉である。
工藤直子の『てつがくのライオン』、この「少年詩集」は哲学について何かを語っているわけではない。
ライオンは『てつがく』が気に入っている。かたつむりが、ライオンというのは獣の王で哲学的な様子をしているものだと教えてくれたからだ。きょうライオンは『てつがくてき』になろうと思った……
「てつがく」というのは坐り方からして大事だというので、いろいろ工夫する。尾を右にまるめたので前肢を重ねて顔を右斜め上に向ける、すると遠くに風に吹かれる梢が見えた。だれも来てくれないのでもう帰ろうかと思っていたら、かたつむりがやってくる。
「やあ、かたつむり。ぼくはきょう、てつがくだった」
「やあ、ライオン。それはよかった。で、どんなだった?」
「うん、こんなだった」
ライオンは、てつがくをやった時のようすをしてみせた。さっきと同じように首をのばして右斜め上をみると、そこには夕焼けの空があった。
「ああ、なんていいのだろう。ライオン、あんたの哲学は、とても美しくてとても立派」
「そう? …とても…何だって? もういちど言ってくれない?」
「うん。とても美しくて、とても立派」
「そう、ぼくのてつがくは、とても美しくてとても立派なの? ありがとうかたつむり」
ライオンは肩こりもお腹すきも忘れて、じっとてつがくになっていた。
「みえてはいるが誰れもみていないものをみえるようにするのが、詩だ」とは、やはり詩人の長田弘の言葉だが、「てつがく」についてもそっくりおなじことが言える。が、それにはそれなりの身がまえというものが必要だろうし、なによりもそれが他人によって支えられているのだということを忘れてはならない。
工藤直子のこの詩集は、「てつがく」がひとのあいだにあり、書斎でのモノローグではなく、ひととの出会いのなかでのダイアローグだということを教えてくれた。考え、論じるだけでなく、聴くことのたいせつさを教えてくれた。言葉とともに考え、話し、聴くことがわたしたちの生活のなかでどういう意味をもつのか、そのことをくりかえし問うなかではじめて、「てつがく」はひとりの人生の芯になりうる、と。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする