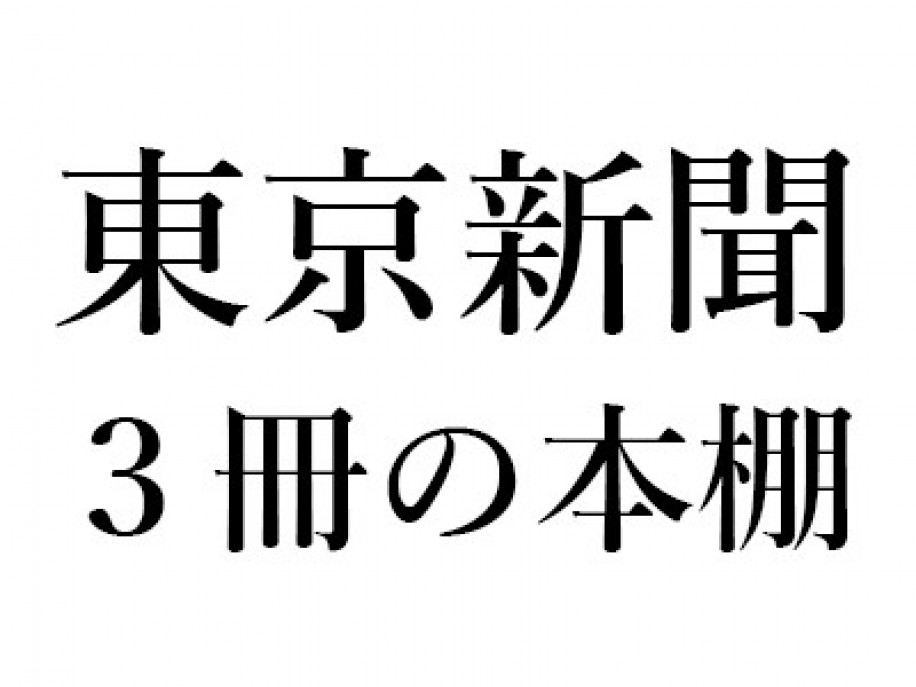書評
『そうはいかない』(小学館)
弱くて強い人間、いとおしむ
佐野洋子さんの文章を読んでいるといつも、ページの奥から「人間」という文字が、じわじわと浮かび上がってくるように思うのです。「人間」の後に「だもの」はつかない。単なる「人間」。この本に収められているのは、物語のようであり、エッセーのようでもある掌編の数々。それは佐野さんの経験なのか想像なのか判然としないけれど、ファミレスや団体旅行、介護といった、読む者の日常生活のどこかにもありそうなシーンが切り取られています。
しかしその読み応えは、単なる「そうそう」「わかるわかる」という共感を、はるかに越えるのでした。残酷さや醜さ、弱さといった負の部分を、誰しもが隠し持っているという事実。その中に少し交じっている、しぶとさと優しさ。すなわち人間そのものを、佐野さんは日常生活の一コマの中から「ほれ」と提示し、私たちは急所を押されたかのように、「うっ」とうなってうずくまる。
提示の仕方は、決して露悪的ではないし、自慢げでもありません。真実そのものが、あまりにさりげなくすくい出されるものだから、読む側は必ず、うずくまった後に笑ってしまう。「笑わせてやろう」という意気込みすら無いからこそ、ますます上質なユーモアがそこには漂うのであり、これはもう天才にしかできない技。
急所ばかりを提示され、読後はへとへとになるかと思いきや、そうではありません。精神の急所はツボでもあるのであり、短編の数だけツボを刺激されることによって、何やら昂揚(こうよう)感が湧いてくるではありませんか。
人間のツボがはっきり見える大きな眼(め)を持っていた佐野さんは、昨年11月(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2011年)にこの世から旅立たれました。余命を知らされた後に書かれたエッセーにおいては、死に至る人間の中身と行動とを、カラリと世に晒(さら)しておられた佐野さん。弱くて強い人間というものを、そのまま見つめて、受け入れて、そしていとおしんできた方だったのだと思います。
朝日新聞 2011年1月30日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする