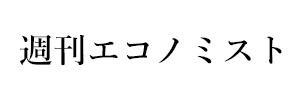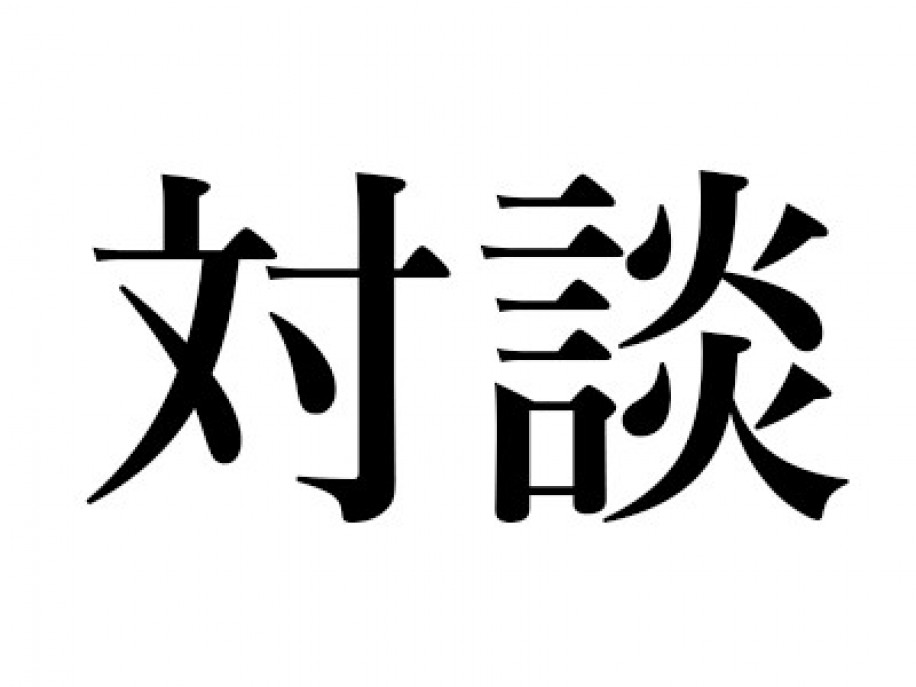書評
『ビジネスモデル全史』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)
「稼ぐ手口」の歴史的変遷 過剰なまでに平易に語る
ビジネスモデル、すなわち「稼ぐ手口」。本書は、それぞれの時代で革新をもたらした商売の手口を歴史的に概観する。商売の基本となる決済から話は始まる。少し前のペイパルや今のスクウェアといった最近の事例はもちろんだが、本書は15世紀にメディチ家が開発した国際決済システムにまで遡り、19世紀末のトーマス・クックとアメックスによるトラベラーズ・チェック、1950年代に生まれたクレジット・カード…、と連綿と続く手口の変遷を追いかける。次から次へと「新しいビジネスモデル」が生まれる。ところが、その手口を支える論理の本質部分は時代に関わらずほとんど変わらない。ここが実に面白い。それもそのはず、普通の人間が普通の人間に対して普通にやっているのが商売。人間の本質が変わらない限り、商売の本質もまた変わらない。
近代的小売業の世界的パイオニアの三井越後屋に始まり、チェーンストアの始祖のA&P、百貨店のメイシーズ、総合スーパーのシアーズを経て、ディスカウントストアのウォルマート、さらにはセブン-イレブンに至る小売業の稼ぐ手口とその背後にある論理の変遷がとりわけ興味深い。それぞれに革新的なビジネスモデルだが、いずれも満たそうとしている顧客のニーズは、「利便性」や「信頼性」「安価」など、言葉にしてしまえばありきたりのものばかり。いつの時代も変わらない。
にもかかわらず、ビジネスモデルの革新と進化には終わりがない。ある商売の手口がそれまで顧客が抱えていた問題を解決し、それが支配的なビジネスモデルとして定着する。しかし、今度はその商売のやり方それ自身が新しい問題や矛盾を生み出す。そうなると、ほとんどの人は「この商売はそういうものだ」と思い込んでしまう。問題は直視されず、矛盾が矛盾のまま放置される。そしてある時、思い込みから解放された革新者が登場する。この繰り返しで小売業が進化してきたことがよく分かる。
いつの時代もやたらにバタバタ忙しいのが商売。「いま・ここ」にばかり目が向き、時間軸での奥行きをもった視点や理解が希薄になる。そこに「全史」の価値がある。
文章は過剰なまでに平易。それぞれのビジネスモデルについての記述もごくあっさりしている。個人的な好みでいえば、対象の数を絞ってでも、もう少しこってりと論じてもらいたかったが、それは著者の意図ではないのだろう。幅広い層の読者にお薦めする。ビジネスに対する興味と関心をそそること請け合いだ。
ALL REVIEWSをフォローする