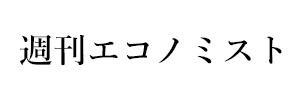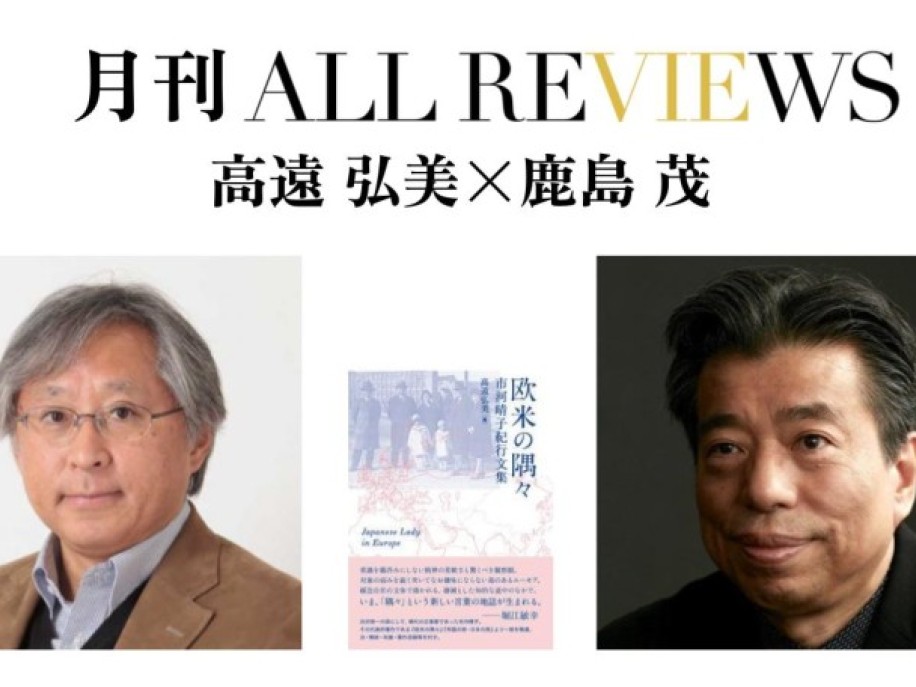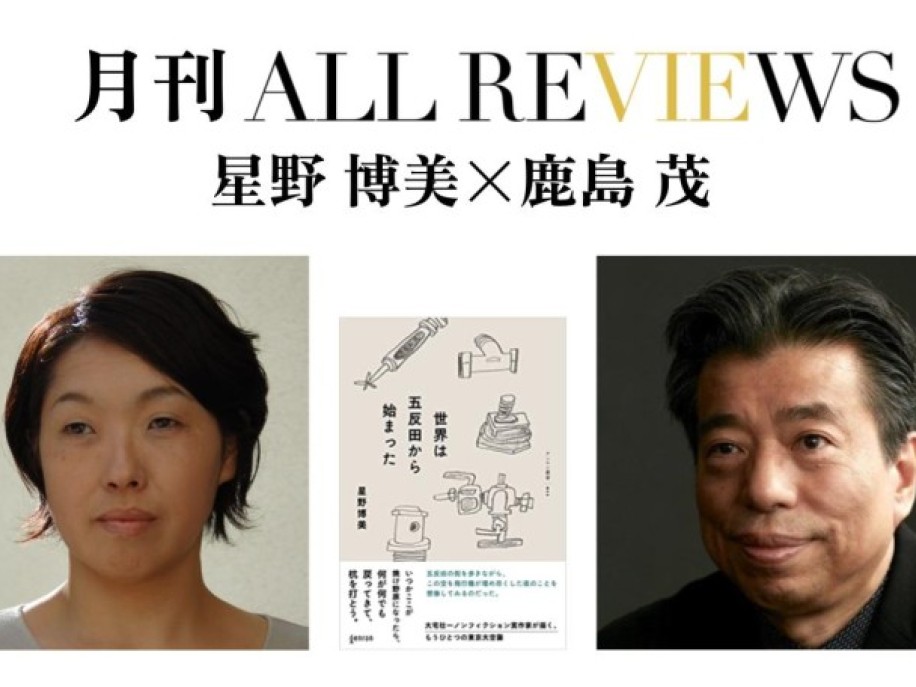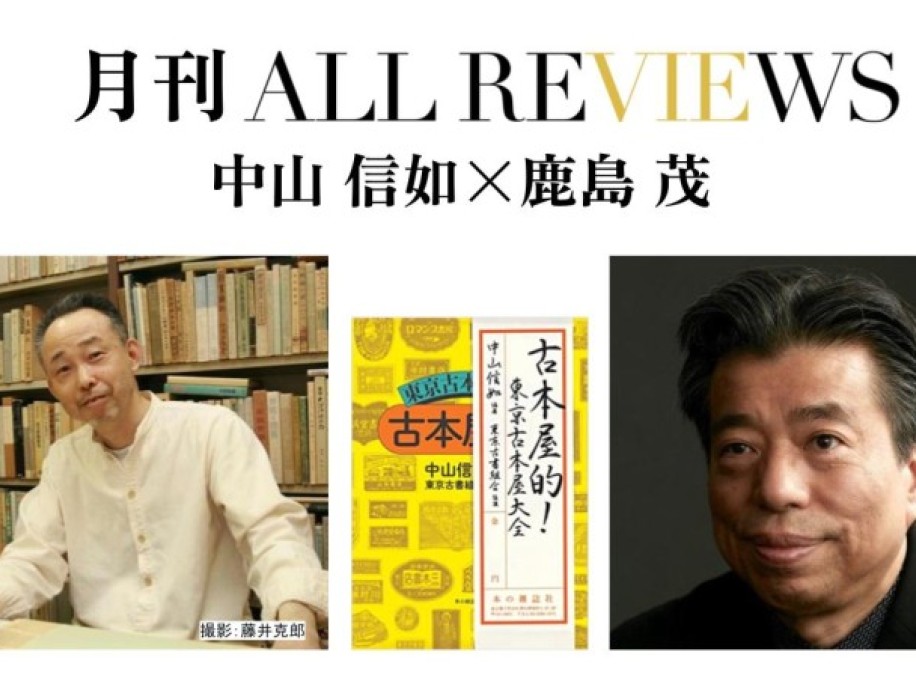書評
『小林一三 - 日本が生んだ偉大なる経営イノベーター』(中央公論新社)
文化的生活を創造した経営者の思考を解明
タイトルにうそはない。阪急電鉄をはじめ、不動産開発、デパートから宝塚歌劇団や東宝などのエンターテインメントまで、数々の独創的事業を一代でつくり上げた小林一三。彼こそは近代日本が生んだとてつもない経営者だった。その偉大さは松下幸之助に比肩する。同時代を生きた小林と松下には共通点が多い。徹底して考える経営。人間の本性に対する洞察に基づいた大構想。そこから演繹(えんえき)的に出てくる事業展開。戦後の公職追放の経験。長寿を全うしたこと。何よりも、2人は日本人の生活を大きく変えたイノベーターだった。
違いもある。「水道哲学」(水道水のように低価格で良質なものを大量供給せよ)に集約されるように、松下は不便や不足といったマイナスを解消しようとした。いっぽう小林は、ゼロからプラスを創ろうとした。居心地の良さ、快適さ、健全さ。宝塚のモットーである「清く正しく美しく」。モノよりもコト、人間生活の「意味」にこだわった。
本書を読むと、小林のやることが完璧な「ストーリー」になっていたことに改めて気づかされる。二流経営者は「シナジー」(相乗効果)という言葉を連発するが、戦略を単に組み合わせの問題として考えていて、時間的な奥行きがない。小林は「こういうことをやるとこうなる」と、いつもストーリーを考える。論理と思考が時間軸上でつながっている。
小林には常人とは違う景色が見えていた。鉄道事業にしても乗客数ではなく初めから住人数と生活に目が向いていた。鉄道が先にあって不動産開発が出てきたのではない。小林にとっての鉄道事業は小林が理想とする都市開発の手段に過ぎなかった。
デパート事業。どのデパートも客を集めるのに多くのコストをかけている。これは無駄であり、客がいっぱいいるところにデパートを作ればいいと小林は考える。これが「ターミナルデパート」というコンセプトになった。「薄利多売」について、普通なら「薄利だから多売しなければならない」というロジックになる。ところが小林は、多売が初めからあって、だからこそ薄利でいいと考える。これが顧客にとって魅力となり、好循環が生まれる。
松下について語る本は多い。しかし、小林一三という偉大な経営者の評伝は少ない。とくに、その思考と行動の様式の解明にまで深く切り込んだ本はなかった。死後60年余り、平成も終わりになってついに決定版が生まれたことを喜びたい。
ALL REVIEWSをフォローする