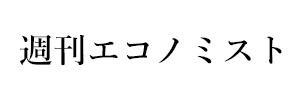書評
『日本の工芸を元気にする!』(東洋経済新報社)
行政の助成に頼らず工芸大国をつくる方法
稼ぐ力の源泉には大別して二つある。一つは外部環境がもたらすオポチュニティー(機会)、もう一つは企業が自ら内部でつくる価値のクオリティー(質)である。どちらに軸足を置くかでオポチュニティー企業とクオリティー企業に分かれる。オポチュニティー企業は、外部環境から生まれる商機をいかに早く強い握力で捉えるかが勝負になる。高度成長を謳歌(おうか)している新興国では、オポチュニティー企業が表舞台に出てくる。
しかし、成長期は永続しない。経済が成熟するにつれて、稼ぐ力の源泉は、企業内部でつくり込む独自価値へとシフトしていく。立ち位置を明確に設定し、一貫した戦略ストーリーを持ち、競合他社と差別化した独自の顧客価値を創出するクオリティー企業が主役となる。
中川政七商店は300年続いた奈良の老舗企業。長寿企業であること自体に価値があるわけではない。家業に就いて以来15年間の試行錯誤の成り行きと独自の戦略、将来の構想までをあけすけに語る。
日本の工芸を元気にして、工芸大国日本をつくる。この「100年の計」を掲げる著者が行き着いた形は工芸の製造小売業(SPA)。川下に向かっては、直営店展開で顧客接点をつくり込み、顧客のニーズをくみ上げ、ブランド・マネジメントの能力を地道に蓄積していく。
それ以上に著者の戦略の妙味があるのは、川上にある工芸メーカーとの連携である。その多くは零細家業で、流通販売はもちろん、マーケティングや経営管理の能力に欠ける。こうした製造業者のコンサルティングに入り込み、二人三脚でプロダクト・ブランドを構築していく。その結果として生まれたユニークな工芸品の価値を直営店で顧客にきっちり発信し、販売へつなげ、適正利益を獲得する。
こうした戦略ストーリー全体を動かすことによって、工芸という小宇宙に局所的ではあるが、「産業革命」を起こした。
何をやるときでも商売の持続性と発展性にこだわる。ここに著者の戦略思考の最大の美点がある。一発モノの助成金やプロモーション、ハコづくりに終始しがちな行政の「伝統産業助成」では決してできない仕事だ。中川政七商店の達成と成果は商売の本懐である。
日本最良のクオリティー企業の姿がここにある。成熟した日本にあって、経営環境の逆風を嘆いているばかりの経営者にこそ読んでもらいたい。
ALL REVIEWSをフォローする