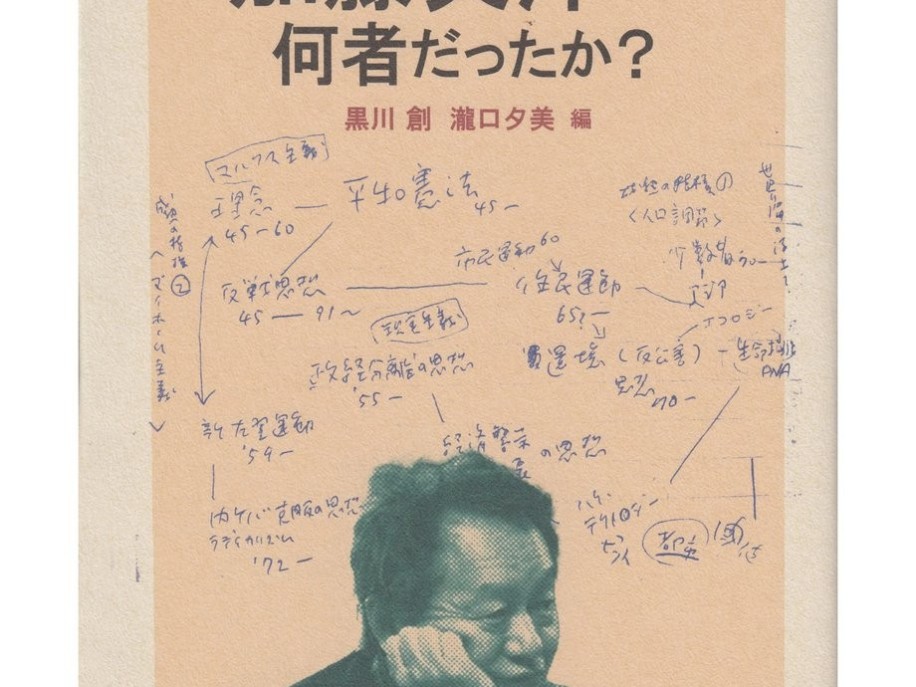書評
『可能性としての戦後以後』(岩波書店)
加藤典洋氏の『敗戦後論』(一九九七)は大きな論争を巻き起こした。本書は、そこに収めるはずだった「『痩我慢の説』考」を含め、七本を集めた姉妹編である。
基調となるのは、戦後の言説空間のゆがみと分裂を直視し、その先に次の時代を拓こうとする意思である。例えば「失言と癋見(べしみ)」で、著者はこう指摘する。
タテマエ/ホンネの使い分けは、日本の古い伝統と信じられているが、誤りである。新聞や辞書の用例から検証できるように、それはたかだか一九七〇年頃から一般化した言い方にすぎない。そしてこれは、戦後日本がどのようにスタートしたかの記憶をおおい隠すための《自己欺瞞の装置》として、無意識にうまれた。戦後の相対主義、ニヒリズムの表明なのだ。
こうした驚くべき事実は、戦後日本を考え直す際の補助線となる。本書では続けて、古代に「日本人」が存在したと考えるのは歴史の《遠近法的倒錯》であること、福沢諭吉はなぜ勝海舟を批判し「私情」を肯定したか、現憲法を起草したGHQ民政局次長ケーディスの深慮、現代資本主義社会の光と闇を対等に踏まえた視点に立つべきことが論じられる。こうして浮き彫りとなるのは、われわれの間に、新しい公共性をいかに立ち上げるかという課題だ。
加藤氏の議論は、果敢かつ挑戦的である。戦後という特殊な空間で通用してきた言説の多くから、効力を奪い、退場を迫る勢いがある。そのため、戦後知識人の流れをくむ人びとや、ポストモダン派、新保守主義のグループから反対の声があがった。
評者に言わせれば、加藤氏の言論こそ「普通の言論」で、勝負は明らかだが、論争そのものはなお続いている。本書は『敗戦後論』とともに、日本の文学史・思想史の画期をなす書物として記憶されることになろう。
【この書評が収録されている書籍】
基調となるのは、戦後の言説空間のゆがみと分裂を直視し、その先に次の時代を拓こうとする意思である。例えば「失言と癋見(べしみ)」で、著者はこう指摘する。
タテマエ/ホンネの使い分けは、日本の古い伝統と信じられているが、誤りである。新聞や辞書の用例から検証できるように、それはたかだか一九七〇年頃から一般化した言い方にすぎない。そしてこれは、戦後日本がどのようにスタートしたかの記憶をおおい隠すための《自己欺瞞の装置》として、無意識にうまれた。戦後の相対主義、ニヒリズムの表明なのだ。
こうした驚くべき事実は、戦後日本を考え直す際の補助線となる。本書では続けて、古代に「日本人」が存在したと考えるのは歴史の《遠近法的倒錯》であること、福沢諭吉はなぜ勝海舟を批判し「私情」を肯定したか、現憲法を起草したGHQ民政局次長ケーディスの深慮、現代資本主義社会の光と闇を対等に踏まえた視点に立つべきことが論じられる。こうして浮き彫りとなるのは、われわれの間に、新しい公共性をいかに立ち上げるかという課題だ。
加藤氏の議論は、果敢かつ挑戦的である。戦後という特殊な空間で通用してきた言説の多くから、効力を奪い、退場を迫る勢いがある。そのため、戦後知識人の流れをくむ人びとや、ポストモダン派、新保守主義のグループから反対の声があがった。
評者に言わせれば、加藤氏の言論こそ「普通の言論」で、勝負は明らかだが、論争そのものはなお続いている。本書は『敗戦後論』とともに、日本の文学史・思想史の画期をなす書物として記憶されることになろう。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする